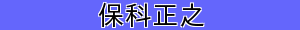保科正之の情報(ほしなまさゆき) 政治家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

保科 正之さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
保科正之と関係のある人
浜田学: 葵 徳川三代(2000年) - 保科正之 役 中村彰彦: 『保科正之 徳川将軍家を支えた会津藩主』中公新書 1995 中公文庫 2006 栩原楽人: 大奥 第一章(2011年10月2日 - 27日、明治座 / 11月4日 - 27日、中日劇場) - 保科正之 役 清水将夫: 箱根風雲録(1952年、新星映画) - 老中保科正之 徳川忠長: 5月7日は異母弟保科正之の、12月3日は異母兄長丸の誕生日が誤伝したと考えられ、また曲直瀬玄朔の『医学天正記』には6月1日生まれの「大樹若君様」(将軍の若君)への診療記録があることから6月1日説が有力と考えられており、『大日本史料』では諸説を紹介しつつ6月1日生まれとして章立てしている。 永井秀明: 大奥 第14話「京より天女が舞い降りた」(1983年、KTV / 東映) - 保科正之 山村聰: 服部半蔵 影の軍団(1980年) - 保科正之 徳川忠長: これと前後して忠長は弟で後の会津松平家開祖となる保科正之に葵紋の入った家康の遺品を与えたり、正之に松平への復姓を薦めたりしたと『会津松平家譜』には記されている。 西郷隆盛: 社倉はもともと朱熹の建議で始められたもので、飢饉などに備えて村民が穀物や金などを備蓄し、相互共済するもので、江戸時代には山崎闇斎がこの制度の普及に努めて農村で広く行われていた(闇斎に学んだ会津藩主保科正之も導入している)。 中村彰彦: 『保科正之 民を救った天下の副将軍』洋泉社歴史新書y 2012 徳川家綱: 特に保科正之を主導者にして外様大名などに一定の配慮を行ない、末期養子の禁を緩和し、大名家臣から証人をとることの廃止や殉死禁止令が出されるなど、これまでの武力に頼った武断政治から文治政治への政策切り替えが行われた。 外山高士: 徳川の夫人たち(1974年) - 保科正之 中村彰彦: 『名君保科正之 歴史の群像』文春文庫 1996 徳川家綱: 家綱が元服するまでは、保科正之ら家光時代の遺産ともいうべき人材に恵まれていたのが安定した時代を築ける幸運でもあった。 徳川頼房: 当時、家光の弟は2人いたが、同母弟忠長は改易となり高崎に幽閉中であり、異母弟保科正之は養子先の高遠藩3万石を継いでまだ2年目であった。 中村彰彦: 『慈悲の名君 保科正之』角川選書 2010 中山昭二: 第117話「名君、会津に入る」(1986年) - 保科正之 山鹿素行: 素行の流罪を主導したという保科正之も会津人としての記載あり。 梶川翔平: ワールドチェイン(李白、アルミニウス、保科正之) 中村彰彦: 『保科正之言行録 仁心無私の政治家』中公新書 1997 中公文庫 2008 筒井巧: 将軍家光忍び旅II 第9話「鳥居峠 葵の印籠を持った女」(テレビ朝日) - 保科正之 役 中村彰彦: 『名君の碑 保科正之の生涯』文藝春秋 1998 のち文庫 栩原楽人: 大奥 第一章(2013年6月1日 - 21日、大阪松竹座 / 7月2日 - 27日、博多座) - 保科正之 役 |
保科正之の情報まとめ

保科 正之(ほしな まさゆき)さんの誕生日は1611年6月17日です。東京出身の政治家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 20:45更新
|
hoshina masayuki
保科正之と同じ誕生日6月17日生まれ、同じ東京出身の人
TOPニュース
保科正之と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】話題のアホネイター