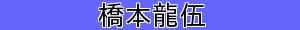橋本龍伍の情報(はしもとりょうご) 政治家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

橋本 龍伍さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
橋本龍伍と関係のある人
小金義照: 戦後の1949年第24回衆議院議員総選挙に旧神奈川3区から無所属で立候補し当選する(当選同期に佐藤栄作・前尾繁三郎・橋本龍伍・麻生太賀吉・小渕光平・西村英一・橋本登美三郎・福永健司・塚原俊郎・木村俊夫・藤枝泉介・稲葉修・河本敏夫・森山欽司・有田喜一など)。 小山長規: 佐藤栄作・岡崎勝男・前尾繁三郎・橋本龍伍・麻生太賀吉・小渕光平・西村英一・橋本登美三郎・福永健司・塚原俊郎・藤枝泉介・木村俊夫・稲葉修・河本敏夫・床次徳二・有田喜一など 西村英一: 1949年、第24回衆議院議員総選挙に吉田茂率いる民主自由党公認で立候補し初当選(当選同期に池田勇人・前尾繁三郎・橋本龍伍・麻生太賀吉・小渕光平・橋本登美三郎・福永健司・塚原俊郎・藤枝泉介・木村俊夫・稲葉修・河本敏夫・森山欽司・床次徳二・有田喜一など)。 中馬辰猪: 帰国後は水産会社役員、鹿児島県煙草耕作連嘱託等を経て、1949年第24回衆議院議員総選挙に吉田茂率いる民主自由党公認で旧鹿児島2区から立候補し当選(当選同期に池田勇人・岡崎勝男・前尾繁三郎・橋本龍伍・麻生太賀吉・小渕光平・西村英一・橋本登美三郎・福永健司・塚原俊郎・藤枝泉介・木村俊夫・稲葉修・河本敏夫・森山欽司・床次徳二・有田喜一など)。 橋本岳: 実業家の渋沢栄一の来孫、大日本麦酒(現・サッポロビール)の常務を務めた橋本卯太郎の曾孫、厚生大臣、文部大臣などを歴任した橋本龍伍の孫、第82・83代内閣総理大臣橋本龍太郎の次男。 橋本大二郎: 大蔵官僚・橋本龍伍の次男として東京都にて出生。 高橋等: 以降、在職中に死去するまで連続6回当選(当選同期に佐藤栄作・岡崎勝男・前尾繁三郎・橋本龍伍・麻生太賀吉・小渕光平・西村英一・橋本登美三郎・福永健司・塚原俊郎・藤枝泉介・木村俊夫・中川俊思・稲葉修・河本敏夫・森山欽司・床次徳二・有田喜一など)。 福田篤泰: ^ この選挙で当選した同期に、池田勇人・佐藤栄作・岡崎勝男・前尾繁三郎・麻生太賀吉・橋本龍伍・小渕光平・西村英一・橋本登美三郎・福永健司・塚原俊郎・藤枝泉介・木村俊夫・稲葉修・河本敏夫・森山欽司・床次徳二・有田喜一など 池田勇人: 1952年1月、戦死者遺族援護費をめぐり橋本龍伍厚生大臣と対立し、橋本が辞任した。 橋本龍太郎: 東京府東京市渋谷区(現:東京都渋谷区)に大蔵官僚・橋本龍伍、春の長男として生まれた。 塚原俊郎: ^ 当選同期に池田勇人・岡崎勝男・前尾繁三郎・橋本龍伍・小渕光平・西村英一・橋本登美三郎・木村俊夫・藤枝泉介・稲葉修・河本敏夫・森山欽司・床次徳二・有田喜一などがいる。 梅沢浜夫: 当時の厚生大臣橋本龍伍の計らいにより、このカナマイシンの特許料を基金として、1959年財団法人微生物化学研究会を設立、理事長に就任。 篠田弘作: 戦後は中央政界入りを志し、1946年・1947年の落選を経て、1949年の第24回衆議院議員総選挙に民主自由党公認で旧北海道4区から立候補し初当選(当選同期に池田勇人・佐藤栄作・前尾繁三郎・橋本龍伍・麻生太賀吉・小渕光平・西村英一・橋本登美三郎・福永健司・塚原俊郎・藤枝泉介・木村俊夫・稲葉修・河本敏夫・森山欽司・床次徳二・有田喜一など)。 木村俊夫: ^ この選挙での当選同期に、池田勇人・前尾繁三郎・橋本龍伍・麻生太賀吉・小渕光平・西村英一・橋本登美三郎・塚原俊郎・藤枝泉介・福田篤泰・稲葉修・河本敏夫・森山欽司・床次徳二・有田喜一など 久野忠治: 1949年の第24回衆議院議員総選挙に再び民主党公認で立候補し初当選を果たす(当選同期に池田勇人・前尾繁三郎・橋本龍伍・麻生太賀吉・小渕光平・西村英一・橋本登美三郎・福永健司・塚原俊郎・藤枝泉介・木村俊夫・稲葉修・河本敏夫・森山欽司・床次徳二・有田喜一など)。 |
橋本龍伍の情報まとめ

橋本 龍伍(はしもと りょうご)さんの誕生日は1906年6月2日です。東京出身の政治家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/07 04:30更新
|
hashimoto ryougo
橋本龍伍と同じ誕生日6月2日生まれ、同じ東京出身の人
TOPニュース
橋本龍伍と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター