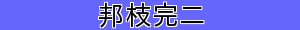邦枝完二の情報(くにえだかんじ) 作家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

邦枝 完二さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
邦枝完二と関係のある人
木村功: 入隊前に梢との結婚を申し込むが、この時は父で作家の邦枝完二の許しは得られなかった。 神保朋世: ほかに邦枝完二の「振袖役者」の挿絵が著名である。 林達夫: 第二次世界大戦末期より、隣家の邦枝完二や親交のあった長谷川巳之吉らと協力して藤沢市鵠沼在住の文化人から蔵書の提供を受け、貸本屋「湘南文庫」を開設したり、文化人を講師に「鵠沼夏期自由大学」を開催、芥川比呂志らによる演劇公演をするなど、地方文化の振興に尽くした。 霧島昇: 安蔵の唄(1937) - 作詞:邦枝完二/作曲:大村能章 木村梢: 邦枝完二の長女として東京市麹町区(現千代田区麹町)に生まれる。 小村雪岱: 昭和8年(1933年)に、挿絵の代表作となった邦枝完二作の新聞小説『おせん』(東京および大阪朝日新聞)、『江戸役者』(東京日日新聞夕刊)、翌昭和9年(1934年)の『お伝地獄』(読売新聞)など数々の作品を発表するなど、挿絵の分野においても大きな足跡を残した。 沢田正二郎: 『城山の月』『明暗録』(邦枝完二作)、『岩見重太郎』(菊池寛作)、市村座 (1924.9) 柳原白蓮: 3月に『指鬘外道』を刊行、邦枝完二の演出で6月に東京市村座で上演されることになり、燁子は原作者として芝居の本読み会や舞台稽古の見学のため、何度か義妹の初枝を伴って上京、その間に龍介と2人の逢瀬を持つようになる。 山中貞雄: 一方、自分の監督作については、日活へ三好十郎原作の『斬られの仙太』の映画化を申し込んだが拒否され、その次に企画した邦枝完二原作の『浮名三味線』も実現せず、結局同年秋は1本も監督作を作ることがなかった。 霧島昇: 喧嘩鳶(1939) - 作詞:邦枝完二/作曲:阿部武雄 風間完: 1953年(昭和28年)、朝日新聞夕刊小説の邦枝完二「恋あやめ」で挿絵デビュー、翌年には新制作派協会会員となった。 |
邦枝完二の情報まとめ

邦枝 完二(くにえだ かんじ)さんの誕生日は1892年12月28日です。東京出身の作家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 09:57更新
|
kunieda kanji
邦枝完二と同じ誕生日12月28日生まれ、同じ東京出身の人
TOPニュース
邦枝完二と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター