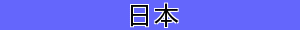日本(にっぽんこく) |Wiki【もしもし辞書】
もしもしロボ調査[Wiki(ウィキ)情報]
日本
|
日本国(にほんこく、にっぽんこく)は、東アジアに位置する国家。面積は377,975.64 km(平方キロメートル) 、人口は1億2377万9000人。首都は東京都(事実上)。 通称は日本(にほん、にっぽん)。 日本は東アジアの島国であり、北海道・本州・四国・九州の主要4島をはじめとする約1万4125の島嶼群から構成される。国土面積は世界63位であり、ほかに世界第6位の広大な排他的経済水域を持つ。起伏に富んだ地形であり、国土の75%は山地・丘陵地で、平地は比較的少ない。最高峰の富士山(3776 m〈メートル〉)をはじめ、3000 mを超える高山は国土の中央部にあたる中部地方に集中する。気候は温暖湿潤気候が中心で、四季が明瞭である。一方で外国に比べ自然災害が多く、地震や津波の被害を受けやすい。国土の67%が森林で、固有種6342種を含む多様な生物相を有する。(→#地理) 日本列島には約3万8000年前から人類が住み始め、紀元前10世紀頃から稲作がはじまった。4世紀末までにはヤマト王権が列島の大部分を支配するようになり、伝承上、その王権が現在の皇室とつながっている。8世紀ごろまでには律令国家としての体制が整った。また、この頃より国号として「日本」が用いられるようになった。律令制は平安時代にはおおむね失われ、荘園および在地勢力の発達にともない、政治の実権は武士に移っていった。武家は鎌倉幕府・室町幕府のような政権を築いた。戦国期の動乱を経て成立した江戸幕府は強固な幕藩体制を築いたが、明治維新を経て天皇親政の新政府が樹立され、のちに立憲政治が採用された。日本は積極的な近代化政策のもと国力を伸長させたが、第二次世界大戦に敗北したのち連合国軍に占領された。戦後日本はサンフランシスコ講和条約を経て主権を回復し、高度経済成長期を経て先進国・経済大国へと伸長した。(→#歴史) 1947年施行の日本国憲法に基づき、天皇は「日本国および日本国民統合の象徴」として位置づけられている。立法府として、衆議院と参議院の二院からなる国会を有する。行政権は内閣に属し、内閣総理大臣を中心に運営される。司法権は裁判所に属する。また、憲法をふくむ六法を中心とする法体系を有する。地方公共団体は、47都道府県と1718市町村、23特別区からなる。国際連合や主要国首脳会議などに参与するが、外交は日米関係を基軸とするものとなっている。防衛力として自衛隊を有するほか、在日米軍が駐留する。日本国憲法にて、戦争の放棄が定められている。(→#政治) 日本は名目GDPと購買力平価で世界第4位、労働力人口は世界8位である。日本は世界最大の債権国で、対外純資産残高が高い一方、国債発行額がGDPの248%に達している。工業は、日本のGDPの27.5%を占め、特に自動車産業が有力である。一方で、1970年代から1980年代にかけてポスト工業化が進展し、2021年時点で第三次産業は日本のGDPの69.5%を占めている。日本には多くの科学技術研究者が存在し、研究開発費はGDP比で世界3位である。過去には学術論文数や特許出願で世界トップだったが、近年は研究力の低下が問題視されている。(→#産業・経済)日本の旅客輸送は鉄道が主流で、貨物は自動車が中心となっており、20,000 km(キロメートル)の鉄道網、1,280,000 kmの道路網を有する。エネルギーとしては原油・石炭が多く利用されており、輸入エネルギーへの依存度が大きい。(→#インフラ) 日本の人口は1億2377万9000人(2024年国勢調査)であり、世界12位である。都市部への集中が顕著であり、また少子高齢化が進んでいる。民族・文化的にみて比較的均質性の高い社会であるといわれているが、外国人人口も全体の3%を占める。日本語が事実上の公用語・共通語である。宗教は神道と仏教が中心である一方、多くの国民は組織宗教の自覚的信者というわけでもない。義務教育は9年間であり、高等教育修了率は55.6%。平均寿命は男性81歳、女性87歳であり、これは都市国家を除いて世界首位である。国民皆保険制度と年金制度が整備された福祉国家である(→#国民)。日本は美術・工芸・芸能、あるいは食文化などの文化的蓄積を有している。また、スポーツも盛んである。(→#文化) 日本において、国号を直接かつ明確に規定した法令は存在しない。『漢書』地理志などに見られるように、古く中国においては日本列島の国家をあらわす呼称として「倭」を用いており、ヤマト王権もこれに倣っていた。しかし、『新唐書』の記述にみられるように、「倭国」は「夏の音(漢音)を習いて倭の名を悪(にく)み」、「日本」の国号を用いるようになった(他説も併記)。『続日本紀』には大宝2年(702年)の遣唐使が、唐側の用いた「大倭国」という国号を退け、「日本国」を主張したという記述があるほか、開元22年(734年)の井真成墓誌にも「日本」の国号があらわれる。国号変更の正確な時期については明らかでないものの、天武天皇治世下又は少し後であるという説、あるいは大宝元年(701年)の大宝律令の成立前後であるという説などが知られている。 「日本」の読み方については、「にほん」と「にっぽん」の2通りがある。室町時代の謡曲においては日本人に「ニホン」、中国人に「ニッポン」と読ませる描写があるほか、安土桃山時代の『日葡辞書』や『日本小文典』には「にほん」「にっぽん」「じっぽん」の読みがあらわれる。1930年代には「にっぽん」に統一する試みもあったが、最終的に決定には至らなかった。両者はいずれも広く通用しており、2009年には日本政府により「どちらか一方に統一する必要はない」とする閣議決定がおこなわれている。 外名としては、英語・ドイツ語において「Japan」、フランス語において「Japon」、スペイン語において「Japón」などが用いられており、これらは「日本」の中国語(閩語ないし呉語)読みが、交易を通じて西洋世界に伝わったものであると考えられている。 通常、日本の歴史は、日本列島における歴史と同一視される。しかし、厳密な「日本」の成立は、国号にあるように7世紀後期であり、それまでは「倭国」と呼び記されていた。この倭国がどのような地理的範囲あるいは系統的範囲をもつ集団であるかについては史料に明確にされておらず、多くの学術上の仮説が提出されている。倭国と日本国との関係は諸説あり、「日本の歴史」と「日本列島の歴史」とを明確に区別して捉えるべきとする考えも示されている。 日本列島に人類が到達したのがいつごろであるかは、定かではない。旧石器時代は前期・中期・後期の3つに分けられているが、日本列島では後期旧石器時代から始まると考える研究者がほとんどである。ホモ・サピエンスのものとして、国内で発見されている最古の遺跡は、いずれも3万8000年前のものである。1万5000年前には隆起線文土器が登場し、日本列島は1万1000年前までに本州北端(および北海道)までが縄文時代に突入する。その後、紀元前10世紀頃より福岡平野で灌漑式水田稲作がはじまり、伝統的理解においては、紀元前3世紀には弥生時代がはじまることとなる。農耕社会の首長層は2世紀中葉より大型の墳墓を築くようになり、200年前後にはヤマト王権の宮都と考えられる纏向遺跡があらわれる。3世紀中葉には箸墓古墳のような本格的な前方後円墳が登場し、多くの研究者は遅くともこの時代には古墳時代がはじまると考えている。4世紀末までにはヤマト王権は列島のかなりの部分を支配する国家となった。 ヤマト王権は中国や朝鮮の諸国との交流をもつとともに、世襲の大王(天皇)と氏姓制度を中心とする国家を確立した。6世紀頃には仏教が伝来したほか、隋・唐の東方進出に圧迫されるかたちで国政改革の必要がうまれる。大化改新や壬申の乱を経て、701年(大宝元年)には大宝律令が完成する。このようにして、日本には中央集権の律令国家が形成された(飛鳥時代)。710年(和銅3年)の平城京遷都によりはじまった奈良時代において、日本は仏教を中心とする律令国家として運営されたものの、この時代より公地公民制にほころびがあらわれはじめ、794年(延暦13年)の平安京遷都よりはじまる平安時代にはこれが崩壊する。王朝国家となった日本においては地方政治は国司に一任されるようになり、10世紀後期には藤原氏が天皇の摂関家として政権を掌握するようになる。貴族・寺社の私有地である荘園の発達にともない、地方ではのちに武士となる在地勢力が力をつけていった。 11世紀後期には摂関家の勢力が下降し、院政期に突入する。この時代には、武士が国家的に重要な位置を占めるようになり、12世紀後期には平氏が政権を握るようになる。平氏を追討した源頼朝は鎌倉幕府を樹立し(鎌倉時代)、その死後は、御家人のひとりであった北条氏が執権として権力を握った。所領を通じた幕府と御家人の関係は、貨幣経済の発展や、元寇に対する恩賞の不十分さなどにより、困窮する御家人が多くなったことでゆらぎはじめ、1333年(元弘3年・正慶2年)には後醍醐天皇による建武の新政がはじまった。足利尊氏は後醍醐天皇を吉野に逐い、1336年(延元元年・建武3年)に自ら天皇を擁立して室町幕府を築いた(室町時代)。南北朝は1392年(明徳3年・元中9年)に解消されるものの、1467年(応仁元年)にはじまる応仁の乱を契機として地方領主は戦国大名として自立し、1573年(天正元年)にはそのひとりである織田信長により幕府が滅ぼされる(安土桃山時代)。 信長の死後、その後継者となった豊臣秀吉は日本をふたたび統一し、検地と刀狩を通して兵農分離を確立した。秀吉の死後、1603年(慶長8年)には徳川家康が江戸幕府を開いた。幕府は幕藩体制を敷いて大名を統制したほか、鎖国政策により外国との交流を制限した。17世紀後期までに幕藩体制は確固たるものとなったが、1800年代よりロシアやイギリスといった西洋諸国が日本と接触するようになり、1853年(嘉永6年)にはアメリカのマシュー・ペリーによる開国が実現する。幕府が朝廷の意向を無視するかたちで日米修好通商条約を結んだことを引き金として、長州藩や薩摩藩など西国雄藩の間で尊王攘夷運動と討幕運動が起き、大政奉還と王政復古を経て、江戸幕府は倒壊した。 1868年(明治元年)の王政復古により、明治天皇を中心とした新政府が開かれた(明治時代)。新政府は積極的な近代化政策を推し進め、版籍奉還や廃藩置県を経て中央集権体制を整え、富国強兵・殖産興業を旗印に封建主義から資本主義社会への移行を推し進めた。この一連の近代化改革は明治維新と呼ばれた。1889年(明治22年)には自由民権運動をうけて大日本帝国憲法(明治憲法)が制定され、それに基づき1890年(明治23年)には帝国議会が設立され。アジア初の議会政治が始まった。 明治時代のほぼ全期を通じて、対外政策の中心課題に不平等条約の撤廃があり、欧米諸国との交渉には紆余曲折があったが、日清日露の勝利など日本の国力の伸長に伴って交渉が成功し、明治27年(1894年)に治外法権の撤廃、明治44年(1911年)に関税自主権の回復を果たして不平等条約を解消した。日清日露に勝利した日本は朝鮮への影響力を強め、1910年(明治43年)には韓国併合をおこなった。また日清・日露の間に産業革命が急速に進展し、日本資本主義の確立を見た。第一次世界大戦後の国際連盟において常任理事国の地位を確保した日本は、国際連盟規約への人種差別撤廃明記を呼びかけたが(人種的差別撤廃提案)、実現に至らなかった。 大正デモクラシーを受けて政治的・文化的発展が進み、政党政治の慣例の確立や普通選挙法成立など民主主義の発展が見られたが、昭和初期の世界恐慌とそれに続くブロック経済化の中で五・一五事件や二・二六事件、政党の汚職事件などに揺れて政党政治が後退、軍の影響の強い挙国一致内閣が常態化した。満州事変に続き日中戦争を経て第二次世界大戦で枢軸国として参戦、連合国軍と太平洋戦争で対決し、1945年8月に日本の降伏に至った。 連合国占領中の1946年(昭和21年)に帝国議会で憲法が改正され、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三原則とする日本国憲法が成立。1951年(昭和26年)にはサンフランシスコ講和条約が締結されて主権を回復したが、沖縄県はアメリカ施政下となる。また同時に日米安保条約を締結した日本は西側諸国の一員となった。1950年代から1970年代初頭にかけての高度経済成長期を経て日本は世界有数の経済大国へと伸長した。1972年(昭和47年)に沖縄返還協定により沖縄県が日本に復帰した。1989年(平成元年)には平成時代がはじまったが、この時代に日本経済は停滞をはじめた。2019年(令和元年)には、平成から令和への改元がおこなわれた。 日本は、東アジアに位置する島国であり、東および南は太平洋、西は日本海と東シナ海、北はオホーツク海に面する。北東から南西にかけて広がる島嶼群から構成され、総体ではおよそ14,125島から成る。北海道・本州・四国・九州の4島が主要な島であるが、この4島に沖縄本島を加えた5島を「本土」と呼称することもある。日本は明治以来、憲法における領土規定がなく、これは比較法学の観点では特殊なものであった。 面積は、2024年10月1日時点で377,975.64 km であり、中央情報局の『ザ・ワールド・ファクトブック』によれば世界63位である。海岸線の総延長は35,268 m。領海は、原則として、基線からその外側12海里、国際航行に用いられる特定海域(宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡西・東水道、大隅海峡)については、基線からその外側3海里の線と、これに接続して引かれる線までの海域。また、基線から200海里までを排他的経済水域とする。日本は島嶼から構成されるゆえ、約4,050,000km におよぶ、広大な排他的経済水域を有する。これは、世界で6番目に広い。 日本列島は太平洋に向かって弓状に張り出すような形をしており、地形学的には東日本島弧系(千島弧、東北日本、伊豆・小笠原弧)と西日本島弧系(西南日本、琉球弧)に大別される。これらの島弧-海溝系は、日本列島付近に位置する太平洋プレート・フィリピン海プレート・北アメリカプレート(オホーツクプレート)・ユーラシアプレート(アムールプレート)の沈み込みによって成立したものとして理解されている。 地形は概して起伏に富み、国土の75%が山地である。これらの標高は、中部地方周辺では3,000 mに達する。同地域を南北に走る、特に高峻な山脈である、飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈を日本アルプスと総称する。これらの山脈は、東北日本、西南日本、伊豆・小笠原弧の接合部付近に位置する凹地帯であるフォッサマグナの西縁でもある。日本の最高峰は標高3,776 mの富士山であり、伊豆・小笠原弧の北部に位置する成層火山である。平野・盆地はほとんどの場合小規模であり、各地に散在する傾向がみられる。最大の関東平野をはじめとして、国内の多くの平野はテクトニックに沈降する盆地を堆積物が埋め立てることによって成立することが多い。 日本列島は環太平洋火山帯に沿っているため、地震・津波・噴火といった自然災害が多い傾向にある。2016年の『World Risk Index』によれば、日本の自然災害リスクは世界で17番目に高かった(世界の自然災害リスク順リスト(英語版))。日本には111の活火山が存在する。また、しばしば津波をともなう大地震が数十年に一度程度発生し、1923年の関東大震災においては140,000人が死亡した。より近年の例としては、1995年の阪神・淡路大震災や、2011年の東日本大震災があった。 ケッペンの気候区分において日本はほぼ温暖湿潤気候か湿潤大陸性気候に属するが、一部に例外が見られる。道南の沿岸部、青森県や岩手県の沿岸部、宮城県、山形県、福島県、栃木県、山梨県、長野県の高原の一部には西岸海洋性気候が分布する。また、群馬県の一部には温帯夏雨気候が存在する。富士山頂や、大雪山山頂付近 にはツンドラ気候が分布する。南西諸島南部には熱帯雨林気候、小笠原諸島の南鳥島には、サバナ気候が分布する。 世界的に見ると四季がはっきりしており、中国や朝鮮半島同様、気温の年較差と日較差が大きい。また、降水量が多いこと、梅雨や秋霖の影響で降水量の年変化が大きいことが特徴として挙げられる。 日本の気侯は、太平洋側か日本海側かで大きな違いが見られる。日本海側では、日本海の上を越えてくる北西の季節風により、冬に雪や雨が多く、太平洋側では、太平洋から吹き込む 南東の季節風により、夏に雨が多い。また、瀬戸内海沿岸や中央高地では年中降水量が少ない。また、南北に長い日本では、緯度による気候の差異も大きい。 日本の面積のうち、67%を森林が占める。日本では2019年現在90,000種以上の生物種が確認されており、6,342種が固有種である。日本は、36か所ある生物多様性ホットスポットの1つに選定されている。国内には53ヶ所のラムサール条約登録地が存在するほか、世界自然遺産も5件登録されている。 日本の植物相は約5,560の種(被子植物4,720・裸子植物40・シダ植物800)によって構成されている。植物区系(英語版)をみると、琉球諸島・小笠原諸島・南鳥島が旧熱帯区系界(英語版)(うち南鳥島はメラネシア・ミクロネシア区系区、それ以外の地域は東南アジア区系区)に、それ以外の地域が全北区系界(英語版)に属する。これらの地域に関しても、極地・高山区系区(高山帯)・東シベリア区系区(北海道北東部)・日華区系区(それ以外の地域)に分類される。動物地理区をみると、日本列島の大部分は旧北区に属する。うち哺乳類については、さらにブラキストン線を挟んでシベリア亜区と満州亜区 (または旧北亜区のシベリア地方と満州地方)に区分される。ただし、渡瀬線以南の奄美・琉球諸島に関しては、旧北区と東洋区の移行帯域としての性質を有する。このように多くの固有種を含む豊かな生物相を持つにもかかわらず、自然林の伐採と植林、里地里山の荒廃、また外来種の蔓延等によってその生物多様性は大きく損なわれている。 戦後の高度経済成長期にあたる1950年代から1960年代、工業復興を経た日本においては深刻な公害問題が発生した。これに対処すべく、1970年には公害関連法が相次いで可決され、1971年には環境庁が設立された(2001年に、改組されて環境省になる)。1973年のオイルショックを契機として産業公害は減少するものの、都市・生活型の大気汚染が増加し、政府は排ガス規制などで対処した。 2018年、環境パフォーマンス指数(英語版)で日本は世界20位である。2020年、日本は国の二酸化炭素排出量リストで世界5位である。日本は1997年に第3回気候変動枠組条約締約国会議を開催し、京都議定書の締結国となった。2020年、日本政府は2050年までのカーボンニュートラルの実現を盟約した。 現行の日本国憲法は1947年に施行されたものであり、日本の国家形態・統治組織・統治作用を規定する。天皇は憲法第1条にもとづき、日本国および日本国民統合の象徴としての地位を有する(象徴天皇制)。現在の日本の天皇は、徳仁である。天皇は内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命、法改正・法律・政令および条約の公布、国会の召集および衆議院の解散などを国事行為としておこなうが、国政に関する権能は有さない。 日本の主権は国民に帰属し、代表者がこれを行使する(代表民主制)。国会は選挙によって選ばれた代表者から構成され、憲法第41条により「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関」としての地位を認められている。衆議院と参議院の二院制であり、法律の制定・予算の議決・条約の承認などの権限を有する。両院の関係は対等なものではなく、衆議院の優越が認められる。 日本の選挙制度は戦後以降複数回改組されているが、1996年以降は衆議院において小選挙区比例代表並立制、2000年以降は参議院において選挙区制と非拘束名簿式比例代表制が採用されている。議会政治は、政党を基軸として展開される。戦後日本においては1955年以来、1993年まで自由民主党が長期政権を握り(55年体制)、その後も1993年の八党派連立政権結成時と2009年から2012年にかけての民主党政権時代を除けば、与党の座にありつづけている。 憲法第65条にもとづき、行政権は内閣に属する。内閣は、内閣総理大臣および、内閣総理大臣の任命する国務大臣から構成され、国会の制定した法律・予算を執行する。また、内閣の下には、行政の実務を担当する中央省庁が置かれる。内閣の存立は国会の信任に基づくものであり、衆議院から不信任ないし信任の不承認を受けた場合、内閣は総辞職するか、衆議院を解散して総選挙をおこなうことができる。内閣総理大臣は、国会議員の互選に基づき指名される。また、国務大臣のうち過半数は国会議員のなかから選定する必要がある。一般に、総理大臣は与党の議員から選ばれ、国務大臣に関しても国会議員以外の者が選ばれることはごくまれである。 司法権は、最高裁判所および法律で定められた下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所および簡易裁判所)に属する。最高裁長官は天皇が形式的に任命し、裁判官は内閣が任命、天皇が認証する。裁判所は民事事件、刑事事件を通じて法律や国家行為が憲法に違反していないかを判断する司法審査制を有しており、その最終判断は最高裁が下す。 日本法は、明治維新以来、信託など一部の民法の規定を除き、大陸法系(特にドイツ法及びフランス法)を基礎としているが、立憲君主制や議院内閣制については英国法、最高裁判所以下司法についての規定につき米国法の影響を強く受けているなど、憲法を中心として英米法の影響も見られる。また、運用には慣習や条理といった国内独自の事情も影響を与えるほか、行政指導も独特の地位を占める。国内の法源は大きくは制定法と不文法にわけられるが、おもに前者が主要である。制定法の中でもっとも重要とされるのは憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法のいわゆる六法であり、うち憲法が国内の最高法規として位置付けられている。とはいえ、法実務においても憲法解釈学においても憲法はその他の具体法一般に優越するものと理解されるよりは、公法私法二元論的な文脈から観念される傾向が強い。 国内の治安維持は、主に警察が担う。警察の機構は、内閣府の外局である国家公安委員会とこれに属する警察庁、そして各都道府県の公安委員会・警察本部による二層構造であり、交番システムなどを通して市民生活に密接に介入する。特殊急襲部隊は、国際特殊部隊競技会などを通じて非常に高い練度を評価されることも多い。銃砲刀剣類所持等取締法により、銃・刀剣などの武器の所持を厳しく規制している。国連薬物犯罪事務所の統計によれば、国連加盟192ヶ国の内、犯罪・刑事司法の統計を報告している国の中で、殺人、誘拐、強制性交、強盗などの凶悪犯罪の発生率が著しく低い。 なお、上記警察組織の他にも、特定の専門分野において犯罪事件の捜査にあたるため、一定の権限を付与された特別司法警察職員も存在する。 普通地方公共団体の広域単位として都道府県、基礎単位として市町村を設ける。地方公共団体は1718市町村および、47都道府県から構成され、都道府県は市町村が及ばない広域の行政・政策を担当する。東京都には23の区(特別区)が設置されており、都はこれら特別区に関する一定の調整機能を有するが、府県の間には法律上の違いはなく、名称の差異は歴史的なものである。 地方公共団体は、首長と議会議員をともに住民が直接選挙で選ぶ、二元代表制を採っている。 2024年現在、市町村のうち最大の人口を有するのは神奈川県横浜市(375万2969人)、最小の人口を有するのは東京都青ヶ島村(156人)である。一定以上の規模を有する大都市は政令指定都市としての地位を与えられ、都市計画・福祉などについてより大きい権限を委ねられるほか、区(行政区)および区役所を設置できる。東京都の特別区は、ほかの政令指定都市の行政区と異なり、公選の区長や区教育委員会、区立小中学校が存在するなど、市町村に近い権限を有している。 都道府県以上の地域分類は様々であるが、1903年(明治36年)の第1期国定地理教科書以来、地理教育の場では、以下のような8地域区分を採用している。 日本は1956年に国際連合に加盟し、安全保障理事会の非常任理事国を過去11回つとめている。これは、国連加盟国中最多である。また、国連通常予算および国連PKO予算の8.033%を負担しており、米国および中国に次ぐ第3位の分担金負担国となっている。日本は、G4諸国の一員として安保理改革の実現に向けた活動をおこなっている。日本は主要国首脳会議(G7)・アジア太平洋経済協力(APEC)・ASEAN+3に加盟するほか、東アジアサミットに参加している。 日本は19億6,000万ドルの政府開発援助実績を有しており、これは開発援助委員会加盟国中3位である(2023年)。日本は156の国家・地域に251の在外公館を有しており、これは世界で4番目に多い。また、157ヶ国が日本に大使館を、42の国際機関が日本に事務所を設けている。2023年7月現在、日本からビザなしで渡航できる国の数は189か国で、韓国やフランスなどと並んで世界3位である。日本は過去5年間、世界1位を維持してきたものの、首位をシンガポールに明け渡した。 日本はアメリカ合衆国と日米安全保障条約を結んでおり、経済的・軍事的に緊密な関係にある。1957年に外務省は日本外交の三原則として「国連中心主義」「アジアの一員としての立場の堅持」「自由主義諸国との協調」を打ち出しているが、実際のその後の日本の外交は日米関係を基軸とする傾向が強かった。2016年には、日本は自由で開かれたインド太平洋戦略を打ち出した。また、日本はインド・太平洋地域における中国の台頭に対処するための日米豪印戦略対話に、アメリカ・オーストラリア・インドとともに参加している。 日本は、周辺諸国といくつかの領土問題を抱えている(日本の領土問題)。北方領土問題は、北方地域に関して、日本とロシアの間で生じている。竹島問題は、竹島に関して、日本と大韓民国および朝鮮民主主義人民共和国の間で生じている。尖閣諸島問題は、尖閣諸島に関して、日本と中華人民共和国および中華民国の間で生じている。 日本は2024年の世界平和度指数でアジア3位であった。2024年度の防衛関連予算はGDPの1.6%であり、ストックホルム国際平和研究所によれば2023年の世界軍事費ランキングで日本は10位であった。日本国憲法第9条により、陸海空軍その他の戦力を保持しないとされているが、「自衛権を行使するための実力を保持することは可能であり、その実力を超えるものが憲法が保持しないとする戦力である」という政府解釈によって1950年の朝鮮戦争勃発以降再軍備がはじまり、1954年には自衛隊が成立した。自衛隊は陸上・海上・航空自衛隊によって構成され、内閣総理大臣(自衛隊の最高指揮監督権を持つ)の指揮監督を受けた防衛大臣のもと組織される。また、事実上の準軍事組織として沿岸警備隊たる海上保安庁が存在するが、海上保安庁での対処が困難な事態が発生した場合は海上警備行動により海上自衛隊が対処する。2020年における自衛官の定員は合計22万7000人である。また、防衛省の文官は、約2万1000人である。 自衛隊の憲法上の位置付けは長沼ナイキ訴訟をはじめとする複数の裁判で争われているが、多くの裁判所は自衛隊を違憲とする判断に消極的であり、実際の判断は政治の場に委ねられている。1992年には国際平和協力法が成立し、自衛隊による海外でのPKO活動がおこなわれるようになった。また、同年の国際緊急援助隊法改正にともない、国際緊急援助活動もおこなわれている。また、2014年には集団的自衛権の行使を容認する閣議決定がおこなわれた。(武力の行使の「新三要件」) また、日本国内には1960年の日米安全保障条約にもとづき在日米軍が駐留している。在日米軍の地位は日米地位協定により保証されており、2013年時点で10万5677人の在日米軍関係者が居留していた。 日本の人権問題としては、性別の不平等・同性婚の不受理・警察のレイシャル・プロファイリング・死刑制度の存続などを批判する団体がある。また、民族的マイノリティや難民および庇護希望者の処遇なども問題視する団体がある。 日本の国内総生産(名目GDP)は世界4位であり(各国の名目GDPリスト)、アメリカ・中国・ドイツに次ぐ。また、購買力平価(PPP)でも中国・アメリカ・インドに次ぐ世界第4位である(国の国内総生産順リスト (購買力平価))。2021年現在、日本の労働力人口は約6860万人であり、世界8位である(各国の労働者人口順リスト(英語版))。2022年現在、日本の失業率は約2.6%と低い水準にある。一方で、相対的貧困率は15.7%以上であり、G7諸国の中で2番目に高い。日本の通貨である日本円は、3番目に有力な準備通貨であり、アメリカドルとユーロに次ぐ。国際経営開発研究所による2024年の世界競争力年鑑によれば、日本の競争力順位は38位である。 日本は世界最大の債権国であり、世界経済からの配当や利子の受け取りが次第に増大している。2023年末時点で、日本の対外資産残高は1,488兆3,425億円、対外負債残高は1,017兆364億円で、差し引き対外純資産残高は33年連続世界最大の471兆3,061億円である。日本は世界で3番目の計上黒字国であるが、日本政府は歳入の35.9%が公債で賄われている状況である(2022年度補正後予算)。しかしながら、日本国債の92.3%が国内保有であり、日本国内の資産となっている。1990年代以降における財政政策により、国債は1000兆円を超える。国庫短期証券を合わせると約1100兆円である。両方を合わせた海外債権者の割合は12.7%である。日本の債務残高の対GDP比は2022年現在で248%に達しており、先進国の中では最も高い。 日本は世界5位の輸出国(国別輸出額の一覧)、世界4位の輸入国(国別輸入額の一覧)である。2021年現在、日本のGDPに占める輸出額は18.2%である(2022年)。最大の輸出先は中国(香港をふくむ)であり、アメリカがそれに次ぐ(2022年)。主要な輸出品目は自動車・鉄鋼製品・半導体・自動車部品である。最大の輸入先も中国であり、アメリカ、オーストラリアがそれに次ぐ。主要な輸入品目は機械および装置・化石燃料・食料品・化学製品・原料品である。 日本型資本主義においては、企業間組織が影響力をもつ。また、雇用システムにおいては終身雇用および年功序列が特徴的である。労働組合に関しては、民間主要組合の多くは労使協調の立場にある。協同組合に関しては、2018年現在、世界でもっとも大規模な10組織のうち3組織が日本の組合であり、うち生活協同組合および農業協同組合は日本のものが世界最大である。OECD調査によれば、日本は人口に占める公務員の比率はOECD中で最小であり(2019年)、経済に占める公営企業の規模も小さい。なお、GDPあたりの租税負担率においては、日本は28.6%であり、OECD諸国平均以下である(2011年)。 経済複雑性指標では世界首位と評価されている。 日本のGDPに占める農林水産業の割合は、2021年時点で1.01%である。2022年の農業生産額は4兆7920億円、漁業生産額は6346億円であり、食料自給率は生産額ベースで58%、供給熱量ベースで38%である。日本の総面積のうち耕作に適しているのは11.5%にすぎないが、単位面積あたりの作物収量は世界最高水準に達している。日本の農業は補助金や関税などにより保護されているが、農業従事者の高齢化と後継者不足は進行中の課題である。日本の漁獲量は世界7位であり、2016年の漁獲量は316億7610トンであった。一方で、これは過去10年間の年間平均である400億トンから減少している。日本の漁船団は世界最大級のものであり、世界の漁獲量のおよそ15%を占めている。このことはマグロをはじめとする水産資源の枯渇を招くものであるとの批判がある。また、日本は商業捕鯨を支持する立場にあり、これも国際的論争となっている。 日本の国土のおよそ3分の2は森林であり、うち40%が人工林である。2022年度の林業生産額は5,807億円であった。国内の林業は木材価格の下落などにより厳しい状況にあったが、2023年度の林野庁『森林・林業白書』によれば、木材価格の回復などにより若干の回復傾向にある。日本においては、2007年時点で11の金属鉱山が稼働している。日本は鉱物資源に乏しく、唯一自給可能な資源は石灰岩である。それ以外の大部分は、海外からの輸入に依存している。 工業は、日本のGDPの27.5%を占める(2021年)。『ザ・ワールド・ファクトブック』は、日本の製造業について「自動車・工作機械・鉄鋼および非鉄金属・船舶・化学製品・繊維・加工食品の分野で、世界最大かつ最先端の技術をもつ企業を有する」と評している。日本の製造業出荷額は2021年時点で302兆33億円であり、2023年時点で世界4位である。特に、日本の製造品出荷額等に占める自動車製造業の割合は17.4%と高く、自動車輸出台数、輸入台数はともに世界3位以内に入る。 日本におけるポスト工業化は1970年代から1980年代にかけて進展し、2021年時点で第三次産業は日本のGDPの69.5%を占める。東証プライム市場に上場する非製造業の純利益(2024年4-9月期)では、銀行が最も高く(約3.7兆円)、商社(約2.6兆円)、通信(約2兆円)がそれに次ぐ。 2019年時点における訪日観光客数は3190万人、国際観光収入は461億ドルであった。同年の世界観光ランキングでは世界11位である。2021年の旅行・観光競争力レポートにおいては、日本は1位であった。 日本には86万7000人の研究者が存在し、およそ19兆円の科学技術研究費を共有している(2017年)。日本のノーベル賞(生理学・医学賞・物理学賞・化学賞)受賞者は22人、フィールズ賞受賞者は3人である。日本の科学技術分野の研究者数は1000人あたり14人であり、これは人口比としては世界2位である。研究開発費は対GDP比率で見ると3.43%と世界3位の高水準にある(2016年、OECE基準は3.15%)ものの、90-08年は1位であったので、相対的には減少している。 1990年代から2000年代前半にかけて、学術論文数(分数カウント)でアメリカに次ぐ世界2位、国際特許出願件数では世界一であった。しかし、1990年代より経済成長の減速とともに研究開発費の増加は鈍化し、2000年代前半には論文数こそ増加しても、世界シェアは低下し始めた。リーマンショック後の2009年から研究開発費が減少・横ばいになると、研究力の低下が露わになる。2017-19年の平均論文数は世界4位に後退した。また、Top10パーセント補正論文数は世界10位まで下がっている。特許出願件数でも2012年に中国に1位の座を明け渡すと、翌年にはアメリカにも抜かれ3位になった。ただし、パテントファミリー数(2カ国以上への特許出願数)は10年以上1位を保っている(2014-16年)。2016年、日本は特許協力条約に基づく全世界の全特許出願数で世界第2位となった。 日本はロボット分野で世界を先導しており、2020年の産業用ロボット製造台数の45%が日本製であった。ただし、これは2017年の55%から低下している。日本の家電産業は世界有数の評価を得ていたが、韓国や中国などの東アジア諸国との地域競争が激化し、衰退傾向にある。 2022年現在、輸送機関別旅客輸送の分担率(人キロ)は自動車が9.1%、鉄道が73%、航空機が17.9%である。また、貨物輸送の分担率(トンキロ)は自動車が55.6%、鉄道が4.4%、内航海運が39.8%、航空機が0.17%である。 日本の道路総延長(私道・林道・農道を除く)は128万3,725.6 kmであり、うち高速自動車国道が9,286.2 km、一般国道が66,416.1 km、都道府県道が142,942.2 km、市町村道が1,065,081.1 km(2021年)である。また、鉄道の総延長は2万7311 km(2015年)である。鉄道は、新幹線などによる大都市圏の幹線ネットワークとして、あるいは大都市・中都市の都市交通において重要な役割を担っており、JRおよび複数の私鉄が乗り入れる新宿駅は、世界で最も乗降客数の多い駅として『ギネス世界記録』に認定されている。 日本では1965年ごろより自家用自動車交通が急速に発展し、地方の過疎化とモータリゼーションの進行により経営が圧迫された日本国有鉄道は1987年に分割民営化された。うち、JR北海道・JR四国の経営環境は非常に厳しく、地方私鉄および路線バスについてもおおむね同様である。一方で、幹線道路ネットワークの整備は進みつつあり、高速道路は1990年時点の4,661kmから30年で9,100 km(2020年)まで伸長している。日本には97の空港(ヘリポート・非公共用飛行場を除く)がある。最大の空港は東京国際空港であり、2019年時点でアジアで2番目に旅客数の多い空港であった。民間人向けの航空会社としてはじめて運行がはじまったのは日本航空(JAL)であり、その後も片手で数えられるほどの航空会社しかなかったが、2000年の航空法改正後は多くの格安航空会社が設立された。 2020年現在、日本には994の港湾があり、中でも重要度の高い港湾は国際戦略港湾(5港)国際拠点港湾(18港)に指定されている。また漁港は2,790あり、中でも漁業の中心地かつ漁業の振興に欠かすことの出来ない漁港13港は特定第3種漁港に指定されている。京浜港(東京港・横浜港・川崎港)および阪神港(神戸港・大阪港・堺泉北港・尼崎西宮芦屋港)はそれぞれ798万・522万 TEUを取扱い(2017年)、世界有数の港湾となっている。 2023年現在、日本の一次エネルギー供給量のうち31.4%を原油、24.4%を石炭、20.7%を天然ガス、3.7%を水力、4.1%を原子力、8.2%を再生可能エネルギー(水力を除く)が占める。原子力は2010年時点の11.2%から減少している。これは、2011年3月の福島第一原子力発電所事故以降、世論により2012年5月までに国内のすべての原子力発電所が一時稼働を停止したからである。日本政府はこれらの発電所を再稼働させようとしており、2015年の川内原子力発電所再稼働を皮切れに、いくつかの発電所が再稼働している。 日本の電力は1951年以降、電気事業再編成により成立した9(のちに沖縄電力をふくめ10)の電力会社によって供給されていたが(日本の電力会社)、2016年に電力小売全面自由化、2020年に発送電分離がおこなわれ、2024年4月時点で全販売電力量に占める新電力のシェアは17.5%を占めている。日本はエネルギー資源の国内埋蔵量にとぼしく、輸入エネルギーへの依存度が大きいため、エネルギーミックスおよび高いエネルギー効率の維持につとめている。 2021年時点で、日本の水道普及率は98.2%となっている。同年の年間取水量は約153.2億 mであり、うち4分の3が河川ないし湖沼から取得した水である。日本の上水道は地方公営企業として独立採算制で運営されるが、全国6,000以上の水道事業者のうち8割が給水人口5,000人未満の簡易水道事業者であり、5,000人以上の上水道事業者についても全体の3分の2が給水人口5万人未満である。これらの小規模事業者は経営状況の悪化や技術者不足に直面しており、2016年末時点で水道管路の14.8%(全国平均)が耐用年数を超過している。 日本の下水道普及率は81.4%、浄化槽などによるものもふくめた汚水処理人口普及率は93.3%であり、人口5万人未満の市町村の汚水処理人口普及率は84.0%まで下がる。汚水処理人口普及状況は改善しつつある一方で、大都市圏の多くではいまだ汚水と雨水を分離しない合流式下水道が使われており、改良が必要であるほか、老朽化する下水道管も増えつつある。 2020年国勢調査によれば、日本の人口は1億2614万6000人であり、うち1億2339万9000人が日本国籍保持者である。日本の人口は世界で12番目に多い。国土の4分の3が山地や丘陵地であることから日本の可住地は限定されており、沿岸部を中心とする都市の人口は非常に稠密となっている。ただし、日本の人口密度は世界40位と、このような人口集中を考慮しなくても高い。2022年時点で、人口の92%が都市部に住んでいる。東京都は日本の首都であり、およそ1420万人が居住している(2024年)。これは、全国人口の11.5%を占めており、日本で最も人口が多い都道府県である。また、人口が増加している唯一の都道府県でもある。首都圏は3814万人が居住している世界最大の都市圏である。総務省統計局によれば、東京都市圏・名古屋都市圏・大阪都市圏が日本の三大都市圏であり、これらの都市圏の人口の総計は2023年現在、全国の人口の53.1%を占めている。 少子高齢化が進んでおり、65歳以上人口の割合は29.3%、15歳未満人口の割合は11.2%である。これは戦後のベビーブームによる人口増加と平均寿命の延伸、出生率の低下によるものである。合計特殊出生率は1.20と世界的に見ても低い水準にあり(国の合計特殊出生率順リスト)、一般に人口置換水準とされる2.1を下回る。中位数年齢は世界有数に高く、2020年時点で48.5歳である。若年層の多くが結婚しない、あるいは子どもを持たない傾向にあり、日本の人口は2070年までに8700万人に減少するであろうと推計されている。この人口構造の変化は、労働力人口の減少や社会保障費の増加といった社会問題を引き起こしている。 日本を単一民族国家とみなすことには問題があるとしても、日本は民族・文化的にみて比較的均質性の高い社会であるといわれている。2023年末時点で、国内には341万992人の外国人が居住している。内訳としては中国人がもっとも多く、ベトナム人、韓国人、フィリピン人と続く。また、日本政府は2019年のアイヌ施策推進法をもって、アイヌを国内の先住民族と認めている。 国内に公用語に関する法律は存在しないものの、日本語が事実上の公用語かつ共通語である。伝統的理解においては、日本語は大きく琉球方言と本土方言に分けられ、琉球方言は北琉球方言と南琉球方言、本土方言は八丈方言・東部方言・西部方言・九州方言にわけられる。東京方言を中心とした「共通語」が標準的に用いられる。 琉球方言と八丈方言は独自性が強く、相互理解性も低い。このため、琉球諸語および八丈語を独立した言語とし、日本語とともに日琉語族を構成するとみなす考えもある。ユネスコは日本の言語のうち危機的状況にあるものとして八丈語・奄美語・国頭語・沖縄語・宮古語(危険)、八重山語・与那国語(重大な危機)、アイヌ語(極めて深刻)を挙げている。手話としては日本手話が広く用いられており、ある程度は公的な承認も得ているものの、歴史的には差別的政策や教育支援の欠如などにより、利用が妨げられていた。 くわえて民族的マイノリティ・移民・外国語学習者などによって、韓国・朝鮮語(在日朝鮮語をふくむ)、中国語、ポルトガル語などが話されている。外国語のなかでは、英語がビジネスおよび国際交流の観点から重視されており、2020年からは初等教育における英語教育がはじまった。 2023年末時点で、341万992人の外国人が居住している。国内の外国人としては中国人がもっとも多く、ベトナム人、韓国人、フィリピン人と続く。2020年国勢調査の時点で、総人口に占める外国人の割合は 2.2%であった。 中国籍の半分は永住者及び定住者であり定住者は中国残留邦人の家族である。 韓国籍、朝鮮籍、および台湾籍については、戦前の旧・日本領の出身者、および両親のうちいずれか(あるいは両方)がその出身である者の子孫が多く韓国籍、朝鮮籍に関しては、戦後になってから朝鮮戦争や貧困・圧政から逃れて渡来してきた難民が一部含まれている。 1895年に台湾を、1910年に朝鮮半島を併合後、第二次世界大戦敗戦まで日本の一部として、台湾人、朝鮮人にも日本国籍を与えていたため、これらの地域にルーツを持つ人々が多く、順次、経済的に豊かであった本土に移住してきた者も少なくない。明治の日本は西欧人の居住や移動、営業に関しては領事裁判権を認める代わりとして居留地制による制限を設けていたが、朝鮮人や中国人については制限がなく、日本国内の各地での雑居が認められていた。1899年に西欧各国との領事裁判権の撤廃が成り、居留地制度は一律に廃止され(内地雑居)たが、中国(清・中華民国:支那)人を含む外国人労働者には居住・就労の制限が設けられた(勅令第352号)。これはおもに華人(支那人)を規制する目的のもので朝鮮人には実質的に適用されなかったとされる。台湾人もまた併合後は帝国臣民であり居住に制限はなかったが、台湾・朝鮮とも戸籍(台湾戸籍、朝鮮戸籍)の離脱は認められず、あくまで内地での寄留であった。台湾人の移住は戦前は少なく、日本在住の台湾人は総じて学歴があり、華人(支那人)や朝鮮人とは異なり、オランダや明遺臣、清朝の植民地支配の歴史的経験があり、民族的な屈託がなく日本語(や外国語)に通暁しよく働くので厚遇された。華人(支那人)は三刀(料理人・理髪師・仕立屋)が、朝鮮人は労働者が中心で、移住規模も多かった。 朝鮮人労働者の日本内地への移動は日韓併合の1910年に2600人であった移動者が1923年には13万人あまりと増加傾向であり、1919年4月の「朝鮮人の旅行取締に関する件」(警務総覧部第3号)により朝鮮人の日本渡航への直接規制(旅行証明書制度)に転換し、移動制限を口実に実質的な居住規制に方針が転換された。朝鮮半島領域では実施されていなかった参政権も普通選挙法(1925年)施行後の内地では認められており、希望を持ち移動し定住した者も多かったが生活は決して恵まれたものではなかった。大戦中には軍人・軍属、あるいは就業目的として渡海した。また徴用労働者として800名以上が渡海した。 終戦の後、彼らの多くが祖国へ引き上げたが、各人の判断や事情によって日本に留まった者もいる。また、戦後相当の数の朝鮮人が祖国の混乱(朝鮮戦争)(国連による難民認定がされている)や韓国軍による虐殺(済州島四・三事件、保導連盟事件など)を逃れて日本に渡った。その後、サンフランシスコ平和条約締結によって彼らは日本国籍を喪失し朝鮮籍となる。その後協定永住者から現在の特別永住者として変遷し日本に在住し続けている。帰化して日本国籍を取得する者も多く、在日コリアンは減少を続けている。 アイデンティティと国籍の問題は明治の開国以来、日本が否応なく直面することになった人権問題であり、戦前から華僑・印僑の人々や様々な移住者、戦後ながらくは台湾・中国系日本人コミュニティの間で葛藤を生んできた。1990年代以降、ブラジルなどの日系移民2世3世の出稼ぎ労働や、東南アジア・中国からの技能実習生といった外国人労働者の人権問題などが発生している。 日本国憲法は信教の自由を認めており、国内には神道・仏教・キリスト教などさまざまな宗教文化が混在している。文化庁の『宗教年鑑』によると、各宗教団体の信者数は、2023年12月時点で合計1億6299万1299人である。『宗教年鑑』に記載される総信徒数は、しばしば日本の人口を超過しているが、これは全国の社寺が氏子や檀家、あるいは初詣の参詣客などを信者数に加え入れていることが一因となっている。統計上は神道の信者数が8790万人(48.5%)、仏教が8390万人(46.3%)、キリスト教が190万人(1%)、その他の宗教団体の信者730万人(4%)となっている(2020年)。その他宗教団体には、イスラム教・バハーイー教・ヒンズー教・ユダヤ教が含まれる。多くの移住者・外国人労働者は仏教・神道以外の宗教を信仰しており、たとえば日本国内のイスラム教徒およそ23万人のうち、日本人は約4万7,000人にとどまる。 NHK放送文化研究所の2018年の調査によれば、宗教を信仰していると答えた人口は36%であった。組織宗教の自覚的信者であることを自認する日本人が比較的少数派にとどまる一方で、日本人が仏教や神道、あるいはキリスト教といった、複数宗教の行事に参加することは珍しいことではない。阿満利麿は、日本人の宗教観は「ご先祖を大切にする気持ちや村の鎮守にたいする敬虔な心」に基づく「自然宗教」であると論じる。また、岡本亮輔は、教えの体系を信者が受容して自らの行動規範とするというキリスト教的宗教モデルは現代日本の宗教を考えるうえで不適当であり、これらは信仰よりも実践や所属によって特徴づけられるものであると論じている。 1947年の教育基本法にもとづき、小学校(6年)・中学校(3年)の計9年間が義務教育の期間と定められている。OECDにより2022年に実施された、義務教育終了後の15歳の児童を対象とする生徒の学習到達度調査(PISA)によれば、日本は数学的リテラシーで5位、読解力で3位、科学的リテラシーで2位であった。ほとんどの児童はその後3年制の高等学校に進学する。日本のGDPに占める教育支出の割合は4.0%(2024年)で、これはOECD平均の4.9%よりやや少ない。 2021年時点で、日本の25歳から64歳の人口のうち55.6%が高等教育を受けており、これは世界3位である。25歳から34歳までの人口のうち、およそ65%がなんらかの高等教育の学位を、34.2%が学士号を有している。学士号の取得率は、OECD諸国では韓国の次に高い。 2017年度の平均寿命は、男性81.09歳、女性87.26歳である。女性は世界で2番目、男性は3番目の順位である。健康寿命では、男性72.14歳、女性74.79歳。終戦直後まで結核などの感染症が多かったが、2018年現在では、1位が悪性新生物(癌)、2位が心疾患、3位が老衰と、生活習慣病を中心とする慢性疾患が主である。また、自殺率はOECDの中では第7位であり、OECD平均と比べ未だ高い数値であるため明らかに要注意であるとOECDは勧告している。 GDPに占める医療支出の比率は7.8%、政府負担比率は81.3%で、一人当たりのGDPが20,000ドル以上の国々の中における標準的な水準である。公費負担率はOECD平均より1割ほど上回っている。医療従事者の人数は、2016年統計では医師が人口1000人あたり2.5であり、一方で看護師は人口1000人あたり11.8であった。一方で病床数では供給過剰が指摘されており、人口あたりの病床数は世界1位でOECD平均の2倍以上、また患者の平均入院日数もOECD各国中で1位であった。 日本は国民皆保険制度を敷いており、国民全員が国民健康保険や被用者保険などに加入する。医療費の自己負担率は原則として3割である。また、20歳から60歳の国民は国民年金を納める必要があり、公的年金制度を通して老齢・障害・死亡などによる稼働所得の減少を補填する。少子高齢化の進展と社会保障の範囲の拡大にともない、これらの制度には運用上の困難が生まれている。 日本文化は有形のものに関しても、無形のものに関しても、豊かな文化的蓄積を有する。現代日本文化はかなり同質性をもち、米山俊直はその淵源を近世におよそ250年間続いた鎖国体制と、近代日本が国民国家を形成するためにおこなった諸政策に求めている。一方で、日本文化は海外からの影響も強く受けている。たとえば、仏教・儒教・道教といった精神文化や、漢字といった、国内の多くの文化要素は大陸部の先進文明によるものであるし、16世紀以降のキリスト教文化の流入や、近代以降に本格化した西欧文明の摂取、あるいは戦後のアメリカ化などもその延長線上にあるものとして理解することができる。また、多彩な地域性や社会的階層の存在なども、日本文化の多面的な発展に影響を与えてきた。また、佐々木利和の論じるように、日本列島においては日本文化のほかにも、アイヌ語を母語とするアイヌ文化および琉球語を母語とする琉球文化(英語版)も存在しており、これらは相互に影響をあたえることもありながら、それぞれ独特の文化形態をつくりあげた。 洋服が日常の衣服としては一般的だが和服の一つである浴衣は私服の一種であり若者にも人気がある。 主に和装する場面としては、祭、行事、儀式が行われるときや、茶道、華道、俳句、武道などの習い事をするときなどがある。 ^ 東京都区部は特別区の集合体であり、ひとつの地方公共団体ではない。 ^ 第9条第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ^ 『三国史記』には唐より4年早く698年に「日本国」の使者が新羅に来た記録があるが、日本の史書との対応に困難があり慎重な意見がある。また『万葉集』では持統天皇の伊勢行幸(692年)時に初めて「日本」が詠まれ(巻1-44番)、次いで694年に遷都した藤原京を称える歌の中で詠まれている(同52番)。678年に唐で死去した百済人・禰軍の墓誌にも「日本」があるが議論が続いている。『三国遺事』には157年に新羅から日本に渡った延烏郎・細烏女の伝説が収められており、『日本書紀』は垂仁天皇の時代に新羅から日本に来たアメノヒボコの伝説を記している。 ^ 日本の憲法体系では、新旧憲法ともに領土規定が存在せず、比較法学の観点ではこれは異例である。明治憲法には領土規定がなく、ロエスレル案の段階においては、領土は自明のものであり、また国体に関わり議院に属さないものだとして領土規定は立ち消えたのであるが、実際にはロエスレルの認識とは異なり、日本の領土は北(樺太・北海道)も南(琉球)も対外政策は不安定な中にあった。この事情は明治政府にとって好都合であったことは確かで露骨なものとしては「我カ憲法ハ領土ニ就イテ規定スル所ナシ、諸国憲法ノ或ハ領土ヲ列挙スルト甚タ異レリ、サレハ我ニ在リテハ、領土ノ獲得ハ憲法改正ノ手続ヲ要セス」(上杉慎吉「新稿・憲法述義」1924年P.143)と解されていた。 ^ によるもの。温帯と冷帯が最寒月平均気温0 ℃で区分されていることに注意すること。 ^ 在日台湾人は1930年代に入るまでは少なく、しかもその大半は留学生であったといわれている。 ^ 朝鮮領域の外に出るものは居住地所轄警察署ないし駐在所が証明書を下付することを規定した。旅行届出許可制。朝鮮籍臣民は日本への旅行(あるいはその名目での転出)は大幅に制限されたが、満州への旅行はほとんど制限がなく、税関審査程度での渡航や旅行が認められていた。李良姫、「植民地朝鮮における朝鮮総督府の観光政策」『北東アジア研究』2007年3月 第13号 p.149-167, 島根県立大学北東アジア地域研究センターNAID 40015705574, ISSN 1346-3810 ^ これは戦時中に隣組の一員として認めてもらうことができず、配給が受けられないなどの具体的な困難として現れた。 ^ “全国都道府県市区町村別面積調 | 国土地理院”. www.gsi.go.jp. 2024年7月9日閲覧。 ^ “人口推計(令和6年(2024年)9月確定値、令和7年(2025年)2月概算値)”. 総務省統計局 (2024年10月21日). 2025年2月20日閲覧。 ^ “令和2年国勢調査”. 総務省統計局 (2020年). 2022年3月23日閲覧。 ^ “Report for Selected Countries and Subjects”. IMF (2023年10月). 2023年10月26日閲覧。 ^ 「紀元節」『改訂新版 世界大百科事典』。https://kotobank.jp/word/%E7%B4%80%E5%85%83%E7%AF%80。コトバンクより2024年9月30日閲覧。 ^ 百科事典マイペディア. “日本”. コトバンク. 2022年11月25日閲覧。 ^ 安倍晋三 (2018年2月13日). “衆議院議員逢坂誠二君提出日本の首都に関する質問に対する答弁書”. 衆議院. 2025年5月30日閲覧。 ^ “世界と日本の気候・自然災害” (PDF). Z会. 2025年5月30日閲覧。 ^ “季節│食文化あふれる国・日本”. 文化庁. 2025年5月30日閲覧。 ^ “自然災害の多い国 日本”. 国土技術研究センター. 2025年5月30日閲覧。 ^ “日本の森林面積について教えてください。”. 農林水産省. 2025年5月30日閲覧。 ^ “都道府県別森林率・人工林率(令和4年3月31日現在)”. 林野庁 (2022年3月31日). 2025年5月30日閲覧。 ^ 国際政治文化研究会『世界の国旗 - 国旗が教えてくれる世界の国々』(創樹社美術出版、2014) ^ 「日本」『改訂新版 世界大百科事典』。https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC。コトバンクより2024年9月28日閲覧。 ^ 神野志隆光『「日本」 国号の由来と歴史』〈講談社学術文庫〉、講談社、2016年、12頁。 ^ 吉田東朔「国号」節(「日本」項 『国史大辞典』、吉川弘文館、1990) ^ 神野志隆光『「日本」とは何か』(講談社現代新書、2005年) ^ 「ニホン」と「ニッポン」 浦部法穂の憲法雑記帳第4回、法学館 ^ 第171回国会 質問第570号 日本国号に関する質問主意書 衆議院公式サイト ^ Batchelor, Robert K. (2014年). London: The Selden Map and the Making of a Global City, 1549–1689. University of Chicago Press. pp. 76, 79. ISBN 978-0-226-08079-6。 ^ 網野善彦『「日本」とは何か 日本の歴史00』(講談社、2000)など ^ “History of Japan” (英語). www.britannica.com. ブリタニカ百科事典 (2024年9月28日). 2024年9月29日閲覧。 ^ 藤尾慎一郎『日本の先史時代 旧石器・縄文・弥生・古墳時代を読みなおす (中公新書)』中央公論新社、2021年、23–24頁。 ^ “発掘!古代いしのまき 考古学で読み解く牡鹿地方>いつから人が住んでいたの?”. 河北新報オンライン (2022年4月27日). 2024年9月29日閲覧。 ^ “縄文文化と北の遺跡 – 北海道デジタルミュージアム”. hokkaido-digital-museum.jp. 2025年2月21日閲覧。 ^ 藤尾 2021, pp. 80–84. ^ 藤尾 2021, p. 128. ^ 藤尾 2021, pp. 106–108. ^ 藤尾 2021, p. 203. ^ 藤尾 2021, p. 265. ^ 藤尾 2021, p. 204. ^ 「飛鳥時代」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E9%A3%9B%E9%B3%A5%E6%99%82%E4%BB%A3。コトバンクより2024年9月30日閲覧。 ^ 「奈良時代」『旺文社日本史事典 三訂版』。https://kotobank.jp/word/%E5%A5%88%E8%89%AF%E6%99%82%E4%BB%A3。コトバンクより2024年9月29日閲覧。 ^ 「平安時代」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3。コトバンクより2024年9月30日閲覧。 ^ 日本大百科全書(ニッポニカ)『日本(にほん)』 - コトバンク ^ 「室町時代」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E5%AE%A4%E7%94%BA%E6%99%82%E4%BB%A3。コトバンクより2024年9月30日閲覧。 ^ 「明治維新」『改訂新版 世界大百科事典』。https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0。コトバンクより2024年9月30日閲覧。 ^ 百科事典マイペディア「明治維新」 ^ ドナルド・キーン『明治天皇』下、新潮社、2001年、91頁。ISBN 978-4103317050。 ^ 五百旗頭薫『条約改正史 - 法権回復への展望とナショナリズム』有斐閣、2010年、334頁。ISBN 978-4641173705。 ^ 改訂新版 世界大百科事典. “産業革命”. コトバンク. 2022年11月25日閲覧。 ^ A.J.P. テイラー(著)『ウォー・ロード―戦争の指導者たち』〈目で見る戦史〉、藤崎利和(訳)、新評論、1989年、187–217頁。ISBN 4-7948-0039-8。OCLC 833262126。 ^ “外交史料 Q&A 大正期”. www.mofa.go.jp. 外務省. 2022年5月11日閲覧。 ^ 世界の歴史まっぷ 「政党政治の展開」 ^ “挙国一致内閣”. コトバンク. 2022年11月25日閲覧。 ^ “日本国憲法の「三原則」って何なの 日本国憲法の「三原則」って何なの の「三原則」って何なの”. 学研. 2021年5月6日閲覧。 ^ 改訂新版 世界大百科事典 日米安全保障条約 ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 沖縄返還 ^ 「新元号は「令和」と日本政府発表 200年ぶりの天皇譲位」『BBCニュース』。2024年9月30日閲覧。 ^ 「Japan」『Encyclopedia of Japan』講談社、2002年。 ^ “日本の島の数”. 国土地理院. 2024年7月22日閲覧。 ^ “知る-基本情報-|知る・調べる|日本離島センター”. www.nijinet.or.jp. 2024年7月9日閲覧。 ^ 石村修第39巻第4号、新潟大学法学会、2007年。 ^ 「植民地法制の形成-序説-」石村修(専修大学法科大学院 第6回東アジア法哲学会シンポジウム)“アーカイブされたコピー”. 2011年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年5月17日閲覧。 ^ “Japan”. ザ・ワールド・ファクトブック. 中央情報局(CIA) (2024年6月3日). 2024年7月9日閲覧。 ^ 国土交通省水管理・国土保全局(編)『海岸統計 (PDF)』(令和5年度版版)、国土交通省。 ^ “特定海域”. www1.kaiho.mlit.go.jp. 2024年7月9日閲覧。 ^ Yamada, Yoshihiko (2011). “Japan's New National Border Strategy and Maritime Security”. Journal of Borderlands Studies 26 (3): 357–367. doi:10.1080/08865655.2011.686972. ^ 太田陽子、小池一之、鎮西清高、野上道男、町田洋、松田時彦『日本列島の地形学』東京大学出版会、2010年1月、2–4頁。ISBN 978-4-13-062717-7。 ^ “1990年刊行 新版日本国勢地図:地形分類 自然地域の名称”. 国土地理院. 2024年12月10日閲覧。 ^ 「日本アルプス」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%97%E3%82%B9。コトバンクより2024年12月20日閲覧。 ^ 太田ほか 2010, pp. 12, 17. ^ 「富士山」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1。コトバンクより2024年12月20日閲覧。 ^ 太田ほか 2010, p. 91. ^ 太田ほか 2010, p. 34. ^ Israel, Brett (2011年3月14日). “Japan's Explosive Geology Explained”. Live Science. 2019年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年9月28日閲覧。 ^ “World Risk Report 2016”. UNU-EHS. 2020年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月8日閲覧。 ^ Fujita, Eisuke; Ueda, Hideki; Nakada, Setsuya (July 2020). “A New Japan Volcanological Database”. Frontiers in Earth Science 8: 205. doi:10.3389/feart.2020.00205. ^ “Tectonics and Volcanoes of Japan”. Oregon State University. 2007年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年3月27日閲覧。 ^ Hammer, Joshua (2011年5月). “The Great Japan Earthquake of 1923”. Smithsonian Magazine. 2021年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年9月28日閲覧。 ^ “3 これまでの大災害との比較 : 防災情報のページ - 内閣府”. www.bousai.go.jp. 2024年9月28日閲覧。 ^ Beck, H.E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., & Wood, E. F. (2018). “Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution”. Nature Scientific Data. doi:10.1038/sdata.2018.214. ^ 主婦の友社 2009, p. 68. ^ 新星出版社編集部 2007, p. 29. ^ 宮本昌幸「東北地方北部から北海道地方におけるケッペンの気候区分の再検討」『地理学論集』第84巻第1号、2009年、111-117頁、doi:10.7886/hgs.84.111、2017年9月22日閲覧。 ^ 清野編集工房 2015, p. 75. ^ 葛西光希、木村圭司「1kmメッシュデータによる北海道の気候変動解析」『地理学論集』第88巻第2号、2014年、37-48頁、doi:10.7886/hgs.88.37、2017年9月22日閲覧。 ^ “琉球島弧(南西諸島)”. 駒澤大学. 2025年1月4日閲覧。 ^ “南鳥島 | 小笠原村公式サイト”. 2025年1月4日閲覧。 ^ 主婦の友社 2009, p. 67. ^ 松山 2014, p. 95. ^ 特に大陸性気候の地域. ^ 雨や雪の多い国土 国土技術研究センター、2017年9月22日閲覧。 ^ 松山 2014, p. 98. ^ 松本 2005, p. 120. ^ 新星出版社編集部, p. 44. ^ 季節風って何?どうしてふくの? 気象庁、2019年8月2日閲覧 ^ 主婦の友社 2009, pp. 68–69. ^ “Natural environment of Japan: Japanese archipelago”. Ministry of the Environment. 2022年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年8月4日閲覧。 ^ Sakurai, Ryo (2019年). Human Dimensions of Wildlife Management in Japan: From Asia to the World. Springer. pp. 12–13. ISBN 978-981-13-6332-0。 ^ “総合研究「日本の生物多様性ホットスポットの構造に関する研究」 :: 国立科学博物館 National Museum of Nature and Science,Tokyo”. www.kahaku.go.jp. 2024年9月28日閲覧。 ^ “生物多様性ホットスポット”. www.conservation.org. コンサベーション・インターナショナル. 2024年9月28日閲覧。 ^ “環境省_ラムサール条約と条約湿地_日本の条約湿地”. www.env.go.jp. 2024年9月29日閲覧。 ^ “環境省_日本の世界自然遺産 [知床・白神山地・小笠原諸島・屋久島・奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島]”. www.env.go.jp. 2024年9月28日閲覧。 ^ “第3章 日本の自然の概要”. www.biodic.go.jp. 環境省自然環境局 生物多様性センター. 2025年1月5日閲覧。 ^ “ブレーキストン線(ブレーキストンセン)とは? 意味や使い方”. コトバンク. DIGITALIO. 2025年1月4日閲覧。 ^ 生物多様性国家戦略2023-2030 https://www.env.go.jp/content/000124381.pdf ^ “History 環境省の歩み”. 環境省. 2025年1月5日閲覧。 ^ “公害国会の召集(1970年)| 高度経済成長と公害の激化(1965~1974年:昭和40年代)|日本の大気汚染の歴史|大気環境の情報館|大気環境・ぜん息などの情報館|独立行政法人環境再生保全機構”. www.erca.go.jp. 2025年1月5日閲覧。 “公害関係法制の抜本的整備を目的として、これに関する集中的な討議が行われた「公害国会」が召集され、広範かつ画期的な内容の公害関連14法案が可決されました。 この国会で可決された公害関係法案は1「公害対策基本法の一部を改正する法律案」、2「道路交通 法の一部を改正する法律案」、3「騒音規制法の一部を改正する法律案」、4「廃棄物処理法案」(修正により「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に改められた。)、5「下水道法の一部を改正する法律案」、6「公害防止事業費事業者負担法案」、7「海洋汚染防止法案」、8「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案」、9「農薬取締法の一部を改正する法律案」、10「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案」、11「水質汚濁防止法案」、12「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」、13「自然公園法の一部を改正する法律案」、14「毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案」です。” ^ “環境省五十年史(令和3年12月、補遺版 令和5年7月)”. 環境省. 2025年1月5日閲覧。 ^ “環境問題の歴史|日本の大気汚染の歴史|大気環境の情報館|大気環境・ぜん息などの情報館|独立行政法人環境再生保全機構”. www.erca.go.jp. 2024年9月28日閲覧。 ^ “Environmental Performance Index: Japan”. Yale University. 2018年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月26日閲覧。 ^ Ito, Masami. “Japan 2030: Tackling climate issues is key to the next decade”. The Japan Times. 2021年3月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月24日閲覧。 ^ “Japan sees extra emission cuts to 2020 goal – minister”. Reuters. (2009年6月24日). オリジナルの2017年10月12日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20171012011542/https://www.reuters.com/article/idUST191967 ^ “2050年カーボンニュートラルの実現に向けて”. 環境省. 2024年9月28日閲覧。 ^ 「日本国憲法」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』。https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95。コトバンクより2024年12月24日閲覧。 ^ “天皇 - 宮内庁”. www.kunaicho.go.jp. 2024年12月24日閲覧。 ^ “天皇皇后両陛下 - 宮内庁”. www.kunaicho.go.jp. 2024年12月24日閲覧。 ^ 村上弘『日本政治ガイドブック〔全訂第3版〕』法律文化社、2024年5月、52–53頁。ISBN 978-4-589-04337-5。 ^ 新藤宗幸、阿部齊『現代日本政治入門』東京大学出版会、2016年2月26日、108–109頁。ISBN 978-4-13-032223-2。 ^ 「自由民主党」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A。コトバンクより2024年12月25日閲覧。 ^ 村上 2024, pp. 87–89. ^ “最高裁判所 | 裁判所”. www.courts.go.jp. 2025年1月5日閲覧。 ^ 伊藤正己・木下毅『アメリカ法入門(4版)』2頁 日本評論社 ^ Dean, Meryll (2002年). Meryll Dean (ed.). Japanese Legal System (2 ed.). Cavendish. pp. 129–132. ISBN 9781859416730。 ^ 水林彪(著)「日本法の成り立ち――法の継受・法の体系」。緒方桂子、豊島明子、長谷河亜希子(編)『日本の法』(2版)、日本評論社、2020年3月、241頁。ISBN 978-4-535-52495-8。 ^ 「警察」『改訂新版 世界大百科事典』。https://kotobank.jp/word/%E8%AD%A6%E5%AF%9F。コトバンクより2024年12月25日閲覧。 ^ “会議録情報 第153回国会 衆議院 内閣委員会 第3号 平成13年11月28日”. kokkai.ndl.go.jp. 2010年8月24日閲覧。 ^ “会議録情報 第166回国会 衆議院 内閣委員会 第29号 平成19年6月15日”. www.shugiin.go.jp. 2010年8月24日閲覧。 ^ “トクシュブタイ”. テレビ朝日SmaSTATION!!. (2004年1月10日). https://www.tv-asahi.co.jp/ss/102/tokushu/top.html ^ UNODC. “Data and Analysis>Crime surveys>The periodic United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems>Fifth Survey (1990 - 1994)”. 2009年7月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年8月26日閲覧。 ^ UNODC. “Data and Analysis>Crime surveys>The periodic United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems>Sixth Survey (1995 - 1997)>Sorted by variable”. 2008年8月26日閲覧。 ^ UNODC. “Data and Analysis>Crime surveys>The periodic United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems>Seventh Survey (1998 - 2000)>Sorted by variable”. 2008年8月26日閲覧。 ^ UNODC. “Data and Analysis>Crime surveys>The periodic United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems>Eighth Survey (2001 - 2002)>Sorted by variable”. 2008年8月26日閲覧。 ^ UNODC. “Data and Analysis>Crime surveys>The periodic United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems>Ninth Survey (2003 - 2004)>Values and Rates per 100,000 Total Population Listed by Country”. 2008年8月26日閲覧。 ^ デジタル大辞泉,世界大百科事典内言及. “特別司法警察職員(トクベツシホウケイサツショクイン)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2025年1月5日閲覧。 ^ 日本大百科全書(ニッポニカ)『都道府県制』 - コトバンク ^ “総務省|地方自治制度|広域行政・市町村合併”. 総務省. 2024年12月25日閲覧。 ^ 村上 2024, p. 168. ^ 塩野宏『行政法Ⅲ第3版』137頁 有斐閣 2006年 ^ “三重県議会 二元代表制”. www.pref.mie.lg.jp. 2025年1月5日閲覧。 ^ “人口が一番多い市と人口が少ない市の差は1406倍!?: 人口最少の村は東京都にある!”. nippon.com (2024年7月26日). 2024年12月25日閲覧。 ^ “東京都の都庁所在地が「新宿」ではなく「東京」なのはなぜですか。|株式会社帝国書院”. 株式会社帝国書院. 2024年12月25日閲覧。 ^ Inc, NetAdvance. “日本列島「地名」をゆく!:ジャパンナレッジ 第101回 地域区分のいろいろ(3)”. JapanKnowledge. 2024年7月10日閲覧。 ^ “日本と国連”. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2024年12月25日閲覧。 ^ “日本の分担金・拠出金”. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2024年12月25日閲覧。 ^ “Japan's Efforts at the United Nations (UN)”. Diplomatic Bluebook 2017. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2021年2月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年12月11日閲覧。 ^ Terada, Takashi (2011年). "The United States and East Asian Regionalism". In Borthwick, Mark; Yamamoto, Tadashi (eds.). A Pacific Nation (PDF). Japan Center for International Exchange. ISBN 978-4-88907-133-7. 2020年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ (PDF)。 ^ “OECD、2023年ODA実績を公表、対ウクライナODAがアフリカ全体へのODAを超える(世界、ルクセンブルク、日本、米国、英国、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フランス、アフリカ) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース”. ジェトロ. 2024年12月25日閲覧。 ^ “Lowy Institute Global Diplomacy Index 2024” (英語). Lowy Institute. 2024年12月25日閲覧。 ^ “世界と日本のデータを見る”. 外務省. 2023年9月9日閲覧。 ^ 「最強パスポートランキング最新版、日本は3位に後退」『CNN.co.jp』2023年7月19日。2023年8月12日閲覧。 ^ “US Relations with Japan”. US Department of State (2020年1月21日). 2019年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月27日閲覧。 ^ 北岡伸一「日本外交の座標軸 : 外交三原則再考」『外交専門誌「外交」』第6巻、2011年2月28日。 ^ “Working Toward a Free and Open Indo-Pacific” (英語). Carnegie Endowment for International Peace. 2020年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年5月8日閲覧。 ^ “Achieving the 'Free and Open Indo-Pacific (FOIP)' Vision: Japan Ministry of Defense's Approach”. Japan Ministry of Defence. 2024年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年5月8日閲覧。 ^ Chanlett-Avery, Emma (2018). Japan, the Indo-Pacific, and the "Quad" (Report). Chicago Council on Global Affairs. ^ Smith, Sheila A. (2021年5月27日). “The Quad in the Indo-Pacific: What to Know”. Council on Foreign Relations. 2023年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月26日閲覧。 ^ 宮脇昇、樋口恵佳、浦部浩之(編)、2022年5月『国境の時代』〈ASシリーズ no. 18〉、大学教育出版、135頁。ISBN 9784866922027。 ^ 宮脇ほか 2022, p. 140. ^ “Profile: Dokdo/Takeshima islands” (英語). BBC News. (2012年8月10日). https://www.bbc.com/news/world-asia-19207086 2024年10月11日閲覧。 ^ 宮脇ほか 2022, p. 147. ^ “2024 Global Peace Index”. Institute for Economics & Peace (2024年6月). 2024年12月26日閲覧。 ^ “防衛関連予算のGDP比、1.6%に上昇 2024年度”. 日本経済新聞 (2024年4月26日). 2024年12月25日閲覧。 ^ “世界の軍事費約378兆円、過去最高に ウクライナは前年比51%増:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル (2024年4月22日). 2024年12月25日閲覧。 ^ 「自衛隊」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A。コトバンクより2024年12月5日閲覧。 ^ “領海警備等の強化”. 海上保安庁. 2022年12月16日閲覧。 ^ “防衛省・自衛隊の人員構成”. 2019年1月15日閲覧。 ^ “資料52 自衛官の定員及び現員並びに自衛官の定数と現員数の推移”. 防衛省. 2021年2月16日閲覧。 ^ “防衛省・自衛隊の人員構成”. 防衛省. 2021年2月16日閲覧。 ^ 「自衛隊」『改訂新版 世界大百科事典』。https://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A。コトバンクより2024年12月26日閲覧。 ^ “憲法解釈変更を閣議決定 集団的自衛権の行使容認”. 日本経済新聞 (2014年7月1日). 2024年12月25日閲覧。 ^ 「在日米軍」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E7%B1%B3%E8%BB%8D。コトバンクより2024年12月26日閲覧。 ^ “【図解・行政】在日米軍関係者の施設・区域内外における都道府県別居住者数(2016年6月):時事ドットコム”. 時事ドットコム. 2024年12月25日閲覧。 ^ Matsui, Shigenori (February 22, 2018). “Fundamental Human Rights and 'Traditional Japanese Values': Constitutional Amendment and Vision of the Japanese Society”. Asian Journal of Comparative Law 13 (1): 59–86. doi:10.1017/asjcl.2017.25. ^ 大河内美紀(著)「憲法」。緒方桂子、豊島明子、長谷河亜希子(編)『日本の法』(2版)、日本評論社、2020年3月、26頁。ISBN 978-4-535-52495-8。 ^ “Japan Strengthening Its Presence in the International Community”. Diplomatic Bluebook. Ministry of Foreign Affairs of Japan (2021年). 2024年12月26日閲覧。 ^ “日本 | Country Page | World | Human Rights Watch”. www.hrw.org. 2024年12月25日閲覧。 ^ “日本弁護士連合会:政府から独立した人権機関の設立に向けた取組(政府から独立した人権機関実現委員会)”. 日本弁護士連合会. 2024年12月25日閲覧。 ^ Iida, Aki (2018). “Gender inequality in Japan: The status of women, and their promotion in the workplace”. Corvinus Journal of International Affairs 3 (3): 43–52. doi:10.14267/cojourn.2018v3n3a5. ^ Shiraishi (2024年3月14日). “Japan same-sex marriage ban ruled unconstitutional again by courts”. BBC. 2024年12月26日閲覧。 ^ “Racial profiling, discrimination in Japan far more serious than stats reported by police”. Mainichi Daily News. (2022年12月17日). オリジナルの2024年5月8日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20240508101627/https://mainichi.jp/english/articles/20221217/p2a/00m/0na/010000c ^ “2020 Country Reports on Human Rights Practices: Japan”. U.S. Department of State. 2023年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年5月8日閲覧。 ^ “Japan: 'Will this day be my last?' The death penalty in Japan”. Amnesty International (2006年7月6日). 2024年12月26日閲覧。 ^ “Japan: Long-standing discrimination unchanged”. Amnesty International (2023年). 2024年12月26日閲覧。 ^ “Japan's new deportation rule for asylum seekers raises rights concerns”. Nikkei Asia (2024年6月10日). 2024年12月26日閲覧。 ^ “World Economic Outlook Database, October 2023”. International Monetary Fund (2023年10月10日). 2023年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月19日閲覧。 ^ “World Factbook: Japan”. CIA. 2021年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年9月24日閲覧。 ^ “Unemployment, total (% of the total labor force) (modeled ILO estimate): Japan”. World Bank. 2022年7月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月31日閲覧。 ^ Huang, Eustance (2020年7月2日). “Japan's middle class is 'disappearing' as poverty rises, warns economist”. CNBC. オリジナルの2022年7月31日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20220731125917/https://www.cnbc.com/2020/07/03/japans-middle-class-is-disappearing-as-poverty-rises-warns-economist.html ^ “Japan confronts rising inequality after Abenomics” (2021年10月31日). 2022年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月19日閲覧。 ^ “Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserve”. IMF. 2016年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月10日閲覧。 ^ “IMD調査の世界競争力、首位はシンガポール 日本は過去最低38位”. 日本経済新聞 (2024年6月18日). 2024年12月19日閲覧。 ^ “令和5年末現在本邦対外資産負債残高の概要”. 財務省. 2025年1月5日閲覧。 ^ “日本の対外純資産、33年連続で世界最大 23年末471兆円”. 日本経済新聞 (2024年5月28日). 2025年1月5日閲覧。 ^ “中国の2020年経常黒字は3100億ドル、ドイツ抜き世界最大に=IFO”. ロイター通信. 2023年1月28日閲覧。 ^ “財政はどのくらい借金に依存しているのか”. 財務省. 2023年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年1月28日閲覧。 ^ “日本国債がそれでも持ちこたえているカラクリ”. 東洋経済. 2023年1月28日閲覧。 ^ “国債等の保有者別内訳(令和元年9月末(速報))” (PDF). 財務省. 2020年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月16日閲覧。 ^ “Monetary Tightening Poses Medium-Term Risks to Japan's Debt Dynamics”. Fitch Ratings (2022年5月6日). 2022年5月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月19日閲覧。 ^ Ímrohoroğlu, Selahattin; Kitao, Sagiri; Yamada, Tomoaki (February 2016). “Achieving fiscal balance in Japan”. International Economic Review(英語版) 57 (1): 117–154. doi:10.1111/iere.12150. JSTOR 44075341. ^ “List of importing markets for the product exported by Japan in 2022”. International Trade Centre(英語版). 2023年4月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年8月11日閲覧。 ^ “List of supplying markets for the product imported by Japan in 2022”. International Trade Centre(英語版). 2023年4月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年8月11日閲覧。 ^ “Exports of goods and services (% of GDP): Japan”. World Bank. 2017年11月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月11日閲覧。 ^ “Japanese Trade and Investment Statistics”. Japan External Trade Organization. 2021年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月3日閲覧。 ^ “Economic survey of Japan 2008”. OECD. 2010年11月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年8月25日閲覧。 ^ “Japan's Economy: Free at last”. The Economist. (2006年7月20日). オリジナルの2011年4月30日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20110430001614/http://www.economist.com/node/7193984?story_id=7193984 ^ 「労使協調」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』。https://kotobank.jp/word/%E5%8A%B4%E4%BD%BF%E5%8D%94%E8%AA%BF。コトバンクより2024年12月19日閲覧。 ^ “The 2018 World Cooperative Monitor: Exploring the Cooperative Economy”. International Co-operative Alliance (2018年10月). 2019年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月19日閲覧。 ^ Goverrnment at a glance 2019, OECD, 2009年, doi:10.1787/8ccf5c38-en。 ^ Revenue Statistics 2014 (Report). OECD. 2014年. doi:10.1787/rev_stats-2014-en-fr。 ^ “ECI Rankings”. oec.world. 2025年1月24日閲覧。 ^ “GDP(国内総生産)に関する統計:農林水産省”. www.maff.go.jp. 2024年12月19日閲覧。 ^ “第1節 食料自給率と食料自給力指標:農林水産省”. www.maff.go.jp. 2024年12月19日閲覧。 ^ “Arable land (% of land area)”. World Bank. 2023年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月11日閲覧。 ^ Chen, Hungyen (2018). “The spatial patterns in long-term temporal trends of three major crops' yields in Japan”. Plant Production Science 21 (3): 177–185. doi:10.1080/1343943X.2018.1459752. ^ “Japan: Support to agriculture”. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation. OECD (2020年). 2021年6月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月11日閲覧。 ^ Nishimura, Karyn (2020年1月1日). “Grown from necessity: Vertical farming takes off in aging Japan”. The Jakarta Post. 2021年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月19日閲覧。 ^ “The state of world fisheries and aquaculture”. Food and Agriculture Organization (2018年). 2021年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月25日閲覧。 ^ McCurry, Justin (2017年4月24日). “Japan to exceed bluefin tuna quota amid warnings of commercial extinction”. 2020年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月19日閲覧。 ^ “Japan resumes commercial whaling after 30 years”. BBC News (2019年7月1日). 2020年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月19日閲覧。 ^ “第1部 第1章 第1節 森林の適正な整備・保全の推進(1):林野庁”. www.rinya.maff.go.jp. 2024年12月19日閲覧。 ^ “第1部 第2章 第1節 林業の動向(1):林野庁”. www.rinya.maff.go.jp. 2024年12月19日閲覧。 ^ “3. 資料編”. 資源エネルギー庁. 2024年12月19日閲覧。 ^ 「石灰岩」『改訂新版 世界大百科事典』。https://kotobank.jp/word/%E7%9F%B3%E7%81%B0%E5%B2%A9。コトバンクより2024年12月19日閲覧。 ^ “1. 私たちの生活や産業に不可欠な「鉱物資源」”. 資源エネルギー庁. 2024年12月19日閲覧。 ^ “「令和3年経済センサス‐活動調査」の製造業に関する結果(概要版)を取りまとめました”. 経済産業省. 2024年12月18日閲覧。 ^ “Manufacturing, value added (current US$)”. World Bank. 2020年1月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年3月17日閲覧。 ^ “基幹産業としての自動車製造業”. JAMA 一般社団法人 日本自動車工業会. 2024年12月19日閲覧。 ^ “2022 Production Statistics”. OICA. 2023年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年5月22日閲覧。 ^ “Is China now the world's top car exporter? It's complicated”. CNN (2024年2月2日). 2024年12月19日閲覧。 ^ “Cars”. The Observatory of Economic Complexity(英語版). 2024年7月27日閲覧。 ^ 山下, 充、小川, 慎一「産業構造の変化と働き方」『日本労働研究雑誌』第64巻第6号、2022年6月、4–16頁、ISSN 0916-3808。 ^ “Services, value added (% of GDP)”. World Bank. 2022年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月11日閲覧。 ^ “非製造業”. 新着!きょうのことば. 日経をヨクヨムためのナビサイト nikkei4946.com (2024年11月24日). 2025年4月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月19日閲覧。 ^ “Trends in the Visitor Arrivals to Japan by Year”. Japan National Tourism Organization. 2020年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年12月11日閲覧。 ^ “Statistical Annex”. UNWTO World Tourism Barometer 18 (5): 18. (August–September 2020). doi:10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.5. ^ “The Travel & Tourism Development Index 2021”. World Economic Forum (2022年5月). 2022年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月31日閲覧。 ^ “Japan's Science and Technology Research Spending at New High”. Nippon.com (2019年2月19日). 2021年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月20日閲覧。 ^ “All Nobel Prizes”. Nobel Foundation. 2018年8月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月11日閲覧。 ^ “Fields Medal”. International Mathematical Union. 2018年12月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月11日閲覧。 ^ “Science, technology, and innovation: Researchers by sex, per million inhabitants, per thousand labour force, per thousand total employment (FTE and HC)”. UNESCO. 2020年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月11日閲覧。 ^ “科学技術指標2019 第1章 研究開発費”. 科学技術・学術政策研究所 (NISTEP). 2022年4月26日閲覧。 ^ “主要国の特許出願件数の推移(1995-2015年)”. SciencePortal China. 2022年4月26日閲覧。 ^ “科学技術指標2019 4.1.2研究活動の国別比較”. 科学技術・学術政策研究所 (NISTEP). 2022年4月26日閲覧。 ^ “日本の科学技術は昔の栄光頼み 若手鍛え、複合的な課題解決目指せ”. 日経ビジネス電子版. 2022年4月26日閲覧。 ^ “中国、論文の数・質ともに世界一に 日本はインドにも抜かれ過去最下位に没落”. THE OWNER. 2022年4月26日閲覧。 ^ “論文数は世界4位だが注目論文数は10位に後退 今年の「科学技術指標」”. Science Portal. 2022年4月26日閲覧。 ^ “世界の特許出願317万件 中国が7年連続で首位”. 2018年12月6日閲覧。 ^ “Record Year for International Patent Applications in 2016; Strong Demand Also for Trademark and Industrial Design Protection” (英語). www.wipo.int. 2022年3月30日閲覧。 ^ Wessling, Brianna (2021年12月15日). “10 most automated countries worldwide”. The Robot Report. 2023年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月20日閲覧。 ^ Fujiwara, Hiroshi (2018年12月17日). “Why Japan leads industrial robot production”. International Federation of Robotics. 2020年11月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月20日閲覧。 ^ Pham, Sherisse (2017年5月4日). “How things got ugly for some of Japan's biggest brands”. CNN Money. 2020年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月20日閲覧。 ^ “旅客輸送人キロ”. 国土交通省. 2024年12月20日閲覧。 ^ “貨物輸送トンキロ”. 国土交通省. 2024年12月20日閲覧。 ^ “道路:道の相談室:道に関する各種データ集 - 国土交通省”. www.mlit.go.jp. 2024年12月19日閲覧。 ^ (英語) Japan, Central Intelligence Agency, (2024-12-16), https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/japan/ 2024年12月19日閲覧。 ^ 天野, 光三「日本の総合交通体系における鉄道の役割と課題」『ノモス = Nomos』第18巻、2006年6月30日、1–11頁。 ^ “Busiest station” (日本語). ギネス世界記録. https://www.guinnessworldrecords.jp/world-records/busiest-station 2024年12月19日閲覧。 ^ 「モータリゼーション」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3。コトバンクより2024年12月20日閲覧。 ^ “Japan’s Bullet Trains Are Hitting a Speed Bump” (英語). Bloomberg.com. (2020年10月7日). https://www.bloomberg.com/news/features/2020-10-07/can-japan-s-bullet-trains-get-back-up-to-speed 2024年12月19日閲覧。 ^ 「地方交通問題」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%95%8F%E9%A1%8C。コトバンクより2024年12月20日閲覧。 ^ “1 鉄道関連産業の動向と施策”. www.mlit.go.jp. 2024年12月19日閲覧。 ^ “1 幹線道路ネットワークの整備”. www.mlit.go.jp. 2024年12月19日閲覧。 ^ “道路:道路統計年報2023 道路の現況 - 国土交通省”. www.mlit.go.jp. 2024年12月19日閲覧。 ^ “World Factbook: Japan”. CIA. 2021年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年9月24日閲覧。 ^ Falcus, Matt (2019年4月22日). “Asia's 9 busiest airports in 2019”. CNN. 2019年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月20日閲覧。 ^ “日本の航空会社、なぜここまで激増? 一強→三強 そして群雄割拠になった歴史”. 乗りものニュース (2021年4月19日). 2024年12月19日閲覧。 ^ ランキング 日本港湾協会 2022年5月25日閲覧。 ^ 漁港一覧 水産庁 2022年5月25日閲覧。 ^ “Top 50 World Container Ports”. World Shipping Council. 2020年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月16日閲覧。 ^ “2023年度簡易表 (xlsx形式)Excelファイル”. 資源エネルギー庁. 2024年12月20日閲覧。 ^ “令和5年度(2023年度)エネルギー需給実績を取りまとめました(速報)”. 資源エネルギー庁. 2024年12月20日閲覧。 ^ "Chapter 7: Energy – 1. Supply and Demand" (PDF). Statistical Handbook of Japan 2021 (Report). Statistics Bureau of Japan. pp. 77, 79. 2021年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年1月8日閲覧。 ^ Tsukimori, Osamu (2012年5月5日). “Japan nuclear power-free as last reactor shuts”. Reuters. オリジナルの2015年9月24日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20150924163821/http://www.reuters.com/article/2012/05/05/us-nuclear-japan-idUSBRE84405820120505 ^ “Nuclear power back in Japan for the first time since Fukushima”. BBC News. (2015年8月11日). オリジナルの2020年8月1日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20200801113235/https://www.bbc.co.uk/news/av/world-asia-33858628/nuclear-power-back-in-japan-for-first-time-since-fukushima ^ “Mixed progress for Japan's nuclear plant restarts”. Nuclear Engineering International (2020年4月23日). 2020年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月20日閲覧。 ^ 「電気事業」『改訂新版 世界大百科事典』。https://kotobank.jp/word/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BA%8B%E6%A5%AD。コトバンクより2024年12月20日閲覧。 ^ “電力小売り自由化の評価|コラム|自然エネルギー財団”. www.renewable-ei.org. 2024年12月19日閲覧。 ^ Thorarinsson, Loftur (2018年4月). “A Review of the Evolution of the Japanese Oil Industry, Oil Policy and its Relationship with the Middle East”. Oxford Institute for Energy Studies. pp. 5–12. 2018年4月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月20日閲覧。 ^ Kucharski, Jeffrey; Unesaki, Hironobu (2017). “Japan's 2014 Strategic Energy Plan: A Planned Energy System Transition”. Journal of Energy 2017: 1–13. doi:10.1155/2017/4107614. ^ “水道資料室:日本の水道の現状:公益社団法人 日本水道協会【JWWA】”. www.jwwa.or.jp. 2024年12月19日閲覧。 ^ 小池治(著)「都市と水道」。横浜国立大学都市科学部(編)『都市科学事典』春風社、2021年、356–357頁。ISBN 9784861107344。 ^ “国土交通省|報道資料|令和5年度末の汚水処理人口普及状況について”. 国土交通省. 2024年12月19日閲覧。 ^ 小池治(著)「都市と下水道」。横浜国立大学都市科学部(編)『都市科学事典』春風社、2021年、358–359頁。ISBN 9784861107344。 ^ “令和2年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約”. 総務省. 2024年12月20日閲覧。 ^ “世界人口白書2024”. UNFPA Tokyo. 2025年1月21日閲覧。 ^ Fujimoto, Shouji; Mizuno, Takayuki; Ohnishi, Takaaki; Shimizu, Chihiro; Watanabe, Tsutomu (2017). “Relationship between population density and population movement in inhabitable lands”. Evolutionary and Institutional Economics Review 14: 117–130. doi:10.1007/s40844-016-0064-z. ^ “List of countries by population density”. Statistics Times. 2020年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月12日閲覧。 ^ Fujimoto, Shouji; Mizuno, Takayuki; Ohnishi, Takaaki; Shimizu, Chihiro; Watanabe, Tsutomu (2015). Geographic Dependency of Population Distribution. International Conference on Social Modeling and Simulation, plus Econophysics Colloquium 2014. Springer Proceedings in Complexity. pp. 151–162. doi:10.1007/978-3-319-20591-5_14. ISBN 978-3-319-20590-8。 ^ “Urban population (% of total population)”. World Bank. 2019年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月19日閲覧。 ^ “首都を定める法律|参議院法制局”. houseikyoku.sangiin.go.jp. 2024年12月20日閲覧。 ^ “東京都の人口(推計):毎月”. Tokyo Metropolitan Government Bureau of Statistics Department. 2018年10月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月22日閲覧。 ^ “人口推計 2023年(令和5年)10月1日現在(結果の概要)”. 総務省統計局. 2025年1月5日閲覧。 ^ “The World's Cities in 2016”. United Nations (2017年3月12日). 2017年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月10日閲覧。 ^ “我が国の人口について”. www.mhlw.go.jp. 2024年12月20日閲覧。 ^ Noriko, Tsuya (June 2017). Low fertility in Japan—no end in sight (PDF) (Report). Vol. 131. East–West Center. pp. 1–4. 2022年7月2日時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。 ^ “Japan: Demographic Shift Opens Door to Reforms”. International Monetary Fund (2020年2月10日). 2020年2月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月10日閲覧。 ^ “-人口統計資料集(2022)-”. www.ipss.go.jp. 国立社会保障・人口問題研究所. 2024年12月20日閲覧。 ^ Walia, Simran (2019年11月19日). “The economic challenge of Japan's aging crisis”. オリジナルの2019年11月19日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20191119155159/https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/11/19/commentary/japan-commentary/economic-challenge-japans-aging-crisis/ ^ Semuels, Alana (2017年7月20日). “The Mystery of Why Japanese People Are Having So Few Babies”. オリジナルの2017年7月20日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20170720214203/https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/07/japan-mystery-low-birth-rate/534291/ ^ D'Ambrogio, Enrico (2020年12月). “Japan's ageing society”. European Parliament. 2020年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月20日閲覧。 ^ Burgess, Chris (2007年3月1日). “Multicultural Japan? Discourse and the 'Myth' of Homogeneity”. The Asia-Pacific Journal: Japan Focus 5 (3). オリジナルの2016年11月24日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20161124154805/https://apjjf.org/-Chris-Burgess/2389/article.html ^ “令和5年末現在における在留外国人数について | 出入国在留管理庁”. www.moj.go.jp. 2024年9月29日閲覧。 ^ “お問合せ・よくある質問”. 国立アイヌ民族博物館 (2024年12月20日). 2024年12月20日閲覧。 ^ “法律と国語・日本語|参議院法制局”. houseikyoku.sangiin.go.jp. 2024年12月20日閲覧。 ^ Fujita-Round, Sachiyo; Maher, John C. (2017年). "Language Policy and Education in Japan". In McCarty, Teresa L.; May, Stephen (eds.). Language Policy and Political Issues in Education. Encyclopedia of Language and Education (3rd ed.). Springer International Publishing. pp. 491–505. doi:10.1007/978-3-319-02344-1_36. ISBN 978-3-319-02343-4。 ^ 三井はるみ「我が国における言語・方言の現状」『文化庁委託事業 危機的な状況にある言語・方言の実態に関する調査研究事業 報告書』(レポート)、17-36頁。 ^ 木部暢子「言語・方言の定義について」『文化庁委託事業 危機的な状況にある言語・方言の実態に関する調査研究事業 報告書』(レポート)、5-8頁。 ^ Thomas Pellard(著)「日本列島の言語の多様性 ―琉球諸語を中心に―」。田窪行則(編)『琉球列島の言語と文化:その記録と継承』くろしお出版、2013年。ISBN 978-4-87424-596-5。 ^ “消滅の危機にある言語・方言 | 文化庁”. www.bunka.go.jp. 2024年12月20日閲覧。 ^ “変わる英語の学習環境 学校によって大きな差 親ができることは?|英語学習、いつからでも どこからでも|朝日新聞EduA”. www.asahi.com. 2024年12月20日閲覧。 ^ “令和5年末現在における在留外国人数について | 出入国在留管理庁”. www.moj.go.jp. 2024年9月29日閲覧。 ^ “令和2年国勢調査 -⼈⼝等基本集計結果からみる我が国の外国⼈⼈⼝の状況-”. 総務省統計局. 2024年9月29日閲覧。 ^ 「朝鮮戦争と日本の対応」庄司潤一郎(防衛研究所紀要第8巻第3号2006.3)[1] アーカイブ 2010年12月6日 - ウェイバックマシン 2章P.44以降に詳しい ^ ここからの記述について『書評:安井三吉著:帝国日本と華僑-日本・台湾・朝鮮』陳来幸(現代中国研究第19号2006.10.7)[2][3] から起筆した。 ^ 明治32年勅令第352号「条約若ハ慣行ニ依リ居住ノ自由ヲ有セサル外国人ノ居住及営業等ニ関スル件」 ^ 陳来幸2006.10.7によれば「韓国人には慣行により内地雑居が容認されてい(た)」(P.75、PDF-P.3) ^ 山脇啓造、『近代日本と外国人労働者』(1994年、明石書店)P.11 ^ 黄嘉琪、「第二次世界大戦前後の日本における台湾出身者の定住の一過程」『海港都市研究』 2008年 3号 p.129-141, 神戸大学文学部海港都市研究センター, doi:10.24546/81000036 ^ 1920年代の東京在住中国人労働者については 阿部康久、「1920年代の東京府における中国人労働者の就業構造と居住分化」 『人文地理』 1999年 51巻 1号 p.23-48, doi:10.4200/jjhg1948.51.23, 人文地理学会 が詳しい。 ^ 帰化統計 日本国 総務省 統計局 ^ Japan, U. S. Mission (2023年6月14日). “信仰の自由に関する国際報告書(2022年版)-日本に関する部分”. 在日米国大使館と領事館. 2024年12月23日閲覧。 ^ 『宗教年鑑 令和5年版 (PDF)』文化庁、2023年、1頁。 ^ 文化庁 2023, p. 37. ^ 渡辺, 浩希 (2011-03). “日本の宗教人口 : 2億と2-3割の怪の解”. 武蔵野大学仏教文化研究所紀要 (27): 25–37. ISSN 1882-0107. https://cir.nii.ac.jp/crid/1050009062401435136. ^ 小林, 利行「日本人の宗教的意識や行動はどう変わったか」『放送研究と調査』第69巻第4号、2019年、52–72頁、doi:10.24634/bunken.69.4_52。 ^ 岡本亮輔『宗教と日本人: 葬式仏教からスピリチュアル文化まで』〈中公新書〉、中央公論新社、2021年、183頁。 ^ 岡本 2021, pp. 4–6. ^ "The Modernization and Development of Education in Japan". The History of Japan's Educational Development (PDF). Japan International Cooperation Agency Research Institute. 2004年3月. p. 23. 2020年11月5日時点のオリジナルよりアーカイブ (PDF)。 ^ 「義務教育」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E7%BE%A9%E5%8B%99%E6%95%99%E8%82%B2。コトバンクより2024年12月21日閲覧。 ^ “OECD生徒の学習到達度調査 PISA2022のポイント”. 国立教育政策研究所. 2024年12月21日閲覧。 ^ “Japan: Learning Systems”. Center on International Education Benchmarking. 2020年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月22日閲覧。 ^ “Education at a Glance 2024 - Country notes: 日本”. OECD (2024年9月10日). 2024年12月20日閲覧。 ^ “Japan”. OECD. 2022年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年1月29日閲覧。 ^ 社会保障費用統計, 厚生労働省 ^ 平成27年簡易生命表の概況 厚生労働省 ^ 主な年齢の平均余命 厚生労働省 2022年5月25日閲覧。 ^ “平均寿命、男女とも過去最高 2017年厚労省”. 2019年3月10日閲覧。 ^ “健康寿命、男女とも延びる 男性72歳・女性74歳”. 2019年3月10日閲覧。 ^ “(2)死因 ① 死因順位”. 厚生労働省. 2019年7月29日閲覧。 ^ “Suicide rates”. OECD. 2020年12月30日閲覧。 ^ “韓国、OECD自殺率1位…堅調な減少にも10万人あたり25.8人”. 2019年4月15日閲覧。 ^ Making Mental Health Count - The Social and Economic Costs of Neglecting Mental Health Care (Report). Country press releases - Japan.: OECD. 2014年7月. doi:10.1787/9789264208445-en。 ^ WHO. “Data and Statistics>World Health Statistics 2007 - Health systems expenditures in health”. 2008年5月4日閲覧。 ^ Health at a Glance 2013 (Report). OECD. 2013年11月21日. doi:10.1787/health_glance-2013-en。 ^ “Total, Per 1 000 inhabitants, 2019 or latest available”. OECD. 2021年2月28日閲覧。 ^ Company, The Asahi Shimbun. “社会保障とは 社会保障制度を構成する四つの柱や問題点について解説”. SDGs ACTION. 2024年12月20日閲覧。 ^ “日本の医療保険制度の仕組み|世界に誇れる日本の医療保険制度|日本医師会”. www.med.or.jp. 2024年12月20日閲覧。 ^ 佐々木, 利和「ひとつの列島, ふたつの国家, みっつの文化」『学術の動向』第16巻第9号、2011年、9_70–9_78、doi:10.5363/tits.16.9_70。 ^ 和の服装文化 浴衣の歴史 ^ 着物の伝統文化・歴史について|にほんご日和 -ヒューマンアカデミー ^ 「日本美術」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%BE%8E%E8%A1%93。コトバンクより2024年9月29日閲覧。 ^ 「日本美術」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』。https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%BE%8E%E8%A1%93。コトバンクより2024年9月29日閲覧。 ^ 「日本工芸」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』。https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B7%A5%E8%8A%B8。コトバンクより2024年9月29日閲覧。 ^ 「日本建築」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%BB%BA%E7%AF%89。コトバンクより2024年12月1日閲覧。 ^ 「明治大正時代美術」『改訂新版 世界大百科事典』。https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E6%99%82%E4%BB%A3%E7%BE%8E%E8%A1%93。コトバンクより2024年9月29日閲覧。 ^ 林屋辰三郎「古代:芸能」『国史大辞典』吉川弘文館。 ^ 「芸能」『改訂新版 世界大百科事典』。https://kotobank.jp/word/%E8%8A%B8%E8%83%BD。コトバンクより2024年12月26日閲覧。 ^ 「落語」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E8%90%BD%E8%AA%9E。コトバンクより2024年12月26日閲覧。 ^ 石毛直道『日本の食文化史』岩波書店 ISBN 978-4-00-061088-9 ^ 『講座 食の文化 日本の食事文化』味の素食の文化センター ISBN 4540980882 ^ 『講座 食の文化 食の情報化』味の素食の文化センター ISBN 4540982192 ^ 日本の伝統的食文化としての和食 農林水産省 ^ 「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されました! 農林水産省 ^ 『講座 食の文化 調理とたべもの』味の素食の文化センター ISBN 4-540-98218-4 ^ 『講座 食の文化 家庭の食事空間』味の素食の文化センター ISBN 4540990233 ^ 『講座 食の文化 食の思想と行動』味の素食の文化センター ISBN 4540990241 ^ “厚生労働省 栄養・食生活”. 2017年8月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月14日閲覧。 ^ 「日本文学」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%96%87%E5%AD%A6。コトバンクより2024年12月26日閲覧。 ^ 「日本思想」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%80%9D%E6%83%B3。コトバンクより2024年12月26日閲覧。 ^ 「仏教」『改訂新版 世界大百科事典』。https://kotobank.jp/word/%E4%BB%8F%E6%95%99。コトバンクより2024年12月26日閲覧。 ^ 「神道」『改訂新版 世界大百科事典』。https://kotobank.jp/word/%E7%A5%9E%E9%81%93。コトバンクより2024年12月26日閲覧。 ^ 「儒教」『改訂新版 世界大百科事典』。https://kotobank.jp/word/%E5%84%92%E6%95%99。コトバンクより2024年12月26日閲覧。 ^ 「国学」『改訂新版 世界大百科事典』。https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E5%AD%A6。コトバンクより2024年12月26日閲覧。 ^ 新藤 & 阿部 2016, pp. 117–118. ^ “全国紙・地方紙の新聞社サイト集 | リサーチ・ナビ | 国立国会図書館”. 国立国会図書館サーチ(NDLサーチ) (2023年7月13日). 2024年12月26日閲覧。 ^ “著作物再販制度に関する公取委決定についての渡邉恒雄・日本新聞協会会長の談話”. www.pressnet.or.jp. 日本新聞協会. 2021年3月4日閲覧。 ^ “何が対象なの? 特集-消費税の軽減税率制度”. 政府広報オンライン. 2016年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月5日閲覧。 ^ 新藤 & 阿部 2016, p. 121. ^ “若年層のテレビ離れが深刻に・・・10~20代の約半数が視聴せず NHK「国民生活時間調査」”. Media Innovation / デジタルメディアのイノベーションを加速させる (2021年6月3日). 2024年12月26日閲覧。 ^ “放送法の「政治的公平」撤廃を検討 政府、新規参入促す”. 2023年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月15日閲覧。 ^ “なぜ、国会でNHKの予算を審議するのか”. www.nhk.or.jp. 日本放送協会. 2021年3月4日閲覧。 ^ “記者クラブ制度「やっぱり廃止した方がいい」 「NEWS23」岸井氏らが「電波停止」発言で会見”. J-CAST ニュース (2016年3月24日). 2022年3月19日閲覧。 ^ “報道自由度、日本66位 国境なき記者団、1つ上昇”. 日本経済新聞 (2020年4月22日). 2021年3月4日閲覧。 ^ “Japan : Tradition and business interests | Reporters without borders” (英語). RSF. 2021年3月4日閲覧。 ^ “Press Freedom's Dark Horizon” (英語). Freedom House. 2021年3月2日閲覧。 ^ 不破雷蔵. “日本は第11位、自由判定…インターネット上の自由度ランキング最新版(2019年版)”. Yahoo!ニュース 個人. 2021年3月2日閲覧。 ^ “The Crisis of Social Media” (英語). Freedom House. 2021年3月2日閲覧。 ^ “Japan: Freedom in the World 2020 Country Report” (英語). Freedom House. 2021年3月2日閲覧。 ^ 「日本映画」『改訂新版 世界大百科事典』。https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%98%A0%E7%94%BB。コトバンクより2024年12月18日閲覧。 ^ “過去興行収入上位作品 一般社団法人日本映画製作者連盟”. www.eiren.org. 2024年12月28日閲覧。 ^ Rosser, Michael (2024年1月30日). “Japan box office and cinema admissions hit post-pandemic high in 2023” (英語). Screen. 2024年12月28日閲覧。 ^ 琉球新報社 (2022年3月28日). “「ドライブ・マイ・カー」米アカデミー国際長編映画賞に 「おくりびと」以来”. 琉球新報デジタル. 2024年12月28日閲覧。 ^ Brzeski, Patrick (2022年3月28日). “Oscars: ‘Drive My Car’ Director Ryusuke Hamaguchi Thanks His Actors for Best International Film Win” (英語). The Hollywood Reporter. 2024年12月28日閲覧。 ^ 澤村修治『日本マンガ全史 : 「鳥獣戯画」から「鬼滅の刃」まで』〈平凡社新書 944〉、平凡社、2020年6月、16–21頁。ISBN 9784582859447。 ^ 津堅信之『日本アニメ史 : 手塚治虫、宮崎駿、庵野秀明、新海誠らの100年』中央公論新社、2022年4月19日、24–25頁。ISBN 978-4-12-102694-1。 ^ “第1章 日本のアニメ・マンガを取り巻く状況”. アニメ等を活かした国際観光ビジネスモデルの検討. 国土交通省. 2024年12月28日閲覧。 ^ 小山友介『日本デジタルゲーム産業史 増補改訂版 : ファミコン以前からスマホゲームまで』(kindle版)、人文書院、2020年4月30日、No. 1175/7365頁。ISBN 9784409241332。 ^ 小山 2020, No. 1736/7365. ^ “メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査 報告書<概要>”. 総務省. 2024年12月28日閲覧。 ^ “新たなクールジャパン戦略”. 首相官邸. 2024年12月28日閲覧。 ^ “IFPI GLOBAL MUSIC REPORT 2024”. globalmusicreport.ifpi.org. 2024年12月28日閲覧。 ^ 東谷護「戦後日本のポピュラー音楽をどう捉えるか : 本物志向と「記憶」を手がかりとして」『ミクスト・ミューズ : 愛知県立芸術大学音楽学部音楽学コース紀要 = Mixed muses』第15巻、2020年3月、51–61頁、ISSN 2432-7816。 ^ “一般社団法人 日本レコード協会”. www.riaj.or.jp. 2024年12月28日閲覧。 ^ “日本相撲協会公式サイト”. 日本相撲協会公式サイト. 2024年12月28日閲覧。 ^ Aoki, Mizuho (2017年4月24日). “Prewar bayonetting martial art makes a return to schools”. The Japan Times. 2024年12月27日閲覧。 ^ Adler, David (2023年2月21日). “History of baseball in Japan”. Major League Baseball. 2024年12月27日閲覧。 ^ “【スポーツ観戦率】直接・テレビ観戦ともに1位は「プロ野球」。インターネット観戦は「格闘技」が人気。 - 調査・研究”. 笹川スポーツ財団. 2024年12月26日閲覧。 ^ Nagata, Yoichi; Holway, John B. (1995年). "Japanese Baseball". In Palmer, Pete (ed.). Total Baseball (4th ed.). Viking Press. p. 547. ^ “Soccer as a Popular Sport: Putting Down Roots in Japan”. The Japan Forum. 2007年4月1日閲覧。 ^ Reineking, Jim (2018年5月25日). “Every FIFA World Cup champion: Brazil, Germany, Italy historically dominate tournament”. USA Today. 2024年12月27日閲覧。 ^ “Team Japan”. Asian Football Confederation. 2016年1月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月2日閲覧。 ^ “Japan edge USA for maiden title”. FIFA (2011年7月17日). 2011年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年12月27日閲覧。 ^ “History”. Asia Rugby. 2020年12月5日閲覧。 ^ “ラグビーW杯開幕まで3カ月切る、日本開催の理由-QuickTake”. Bloomberg.com (2019年6月20日). 2024年12月26日閲覧。 ^ “国内で過去に行われた主な大規模国際競技大会:スポーツ庁”. スポーツ庁ホームページ. 2024年12月26日閲覧。 ^ “2006 FIBA World Championship”. FIBA. 2006年9月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月10日閲覧。 ^ “FIBA Basketball World Cup 2023”. FIBA. 2020年9月24日閲覧。 ^ “The Game – World Championships – FIVB Women's World Championships Finals”. FIVB. 2017年6月13日閲覧。 ^ キックボクシングの歴史 ^ K-1とは ^ JTB総合研究所 ^ 忍者になりきれる!?日本で体験できるスポット7選 ^ “文化芸術立国の実現”. 文部科学省. 2024年12月28日閲覧。 ^ “日本の世界遺産一覧 | 文化庁”. www.bunka.go.jp. 2024年12月28日閲覧。
日本を意味する和の一覧 日本カテゴリのカテゴリツリー |
※文章がおかしな場合がありますがご了承ください。
もしもしロボ「日本に関する情報が見つかるかもしれないよ!」
最新情報を確認する
nipponkoku
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター