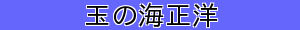玉の海正洋の情報(たまのうみまさひろ) 相撲 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

玉の海 正洋さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
玉の海正洋と関係のある人
大鵬幸喜: 現役晩年に至っても、北の富士と玉の海正洋の両横綱に対しては最後まで壁として君臨し続けた。 出羽錦忠雄: 日本相撲協会の巡業部に在職していた1971年の夏のある日、巡業の一日が終わって親方や力士が夜の街へ出かけるために世話をしていたが、ある日、玉の海正洋だけが外出せずに宿舎に一人で残っていることに気付き、「横綱はなぜ遊びに行かないのか」と尋ねたところ、玉の海は「自分は皆と一緒に遊んでたら身体が持ちません」と返答した。 安芸乃島勝巳: 貴闘力の証言によると、四股名「安芸乃島」は当時の郷土の名前「安芸津町」と師匠が尊敬していた横綱・玉の海正洋の若名乗り「玉乃島」から。 玉ノ海梅吉: 玉乃島正夫が横綱に昇進して「玉の海正洋」と改名した際は、玉ノ海本人も自身の師匠である玉乃海太三郎も自分の名を継いだということもあって特に注目した。 玉錦三右衛門: 第二次世界大戦後の第51代横綱・玉の海正洋は皮肉にも玉錦の孫弟子にあたり、さらに奇しくも虫垂炎の悪化(手術後の血栓症)により27歳で現役死した。 玉錦三右衛門: 大関時代にすでに第一人者でありながら昇進を見送られ続けたことや、まだ余力を残しての現役死だったせいもあるが、「一場所平均の金星配給数」を見た場合、昭和の横綱で玉錦より少ないのは現役のまま亡くなった玉の海正洋(在位10場所、金星3個)だけである。 |
玉の海正洋の情報まとめ

玉の海 正洋(たまのうみ まさひろ)さんの誕生日は1944年2月5日です。愛知出身の相撲のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 03:15更新
|
tamanoumi masahiro
玉の海正洋と同じ誕生日2月5日生まれ、同じ愛知出身の人
TOPニュース
玉の海正洋と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター