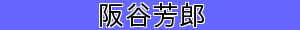阪谷芳郎の情報(さかたによしろう) 官僚、政治家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

阪谷 芳郎さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
阪谷芳郎と関係のある人
田尻稲次郎: 1879年(明治12年)夏に帰国し東京大学で経済学を講じ、のちに大蔵省での部下となる阪谷芳郎・添田寿一らを教える。 渋沢元治: ただ、尋常中学は当時の埼玉にはなかったために上京、栄一の娘婿である大蔵省の阪谷芳郎邸で書生をしながら、一旦成立学舎に入学、12月に東京府尋常中学合格が決まり、同校2年次に編入学した。 伊沢多喜男: 1923年(大正12年) 10月、帝都復興院評議会議員(会長は阪谷芳郎)となる。 松尾臣善: 1903年(明治36年)10月、山本達雄第5代日銀総裁の任期が満了となり、大勢は山本の再任と認識していたが、松尾が大蔵省局長に通算17年も在任し、当時の大蔵総務長官(大蔵次官)阪谷芳郎よりも先輩でありその処遇に苦慮していたことと、日露戦争開戦となると日銀総裁は戦費調達のため政府の方針に従ってくれる人物が望ましく、山本は政府に従順な人物ではなかったため、曾禰荒助大蔵大臣の意向により松尾が第6代日銀総裁に就任した。 明治天皇: まず、天皇の陵墓について、崩御当日に阪谷芳郎東京市長が宮内省に天皇陵の造営地として、東京が選定されることの希望を申し入れた。 三好学: 三好は、阪谷芳郎、山本直良、林愛作、井下清らとともにその中心人物の一人で、会の顧問、副会頭など、ほぼ全期にわたって役員を務め、会誌への執筆記事も最多を数えた。 若槻礼次郎: 1906年1月 - 第一次西園寺内閣の阪谷芳郎大蔵大臣の下の大蔵次官となる。 徳川家達: しかし日本国内では7割案だったのを米国に屈従して6割案に譲ったとする全権の弱腰を批判する論調が日増しに高まり、それは渋沢栄一と彼の娘婿で貴族院議員の阪谷芳郎を通じて家達の耳にも入っていた。 内野謙太: 青天を衝け(2021年) - 阪谷芳郎 役 西園寺公望: 明治41年(1908年)1月には、山縣伊三郎逓信大臣と阪谷芳郎大蔵大臣を更迭するよう元老からの圧力が強まり、西園寺は両名とともに辞表を提出したが、西園寺のもののみ却下されている。 |
阪谷芳郎の情報まとめ

阪谷 芳郎(さかたに よしろう)さんの誕生日は1863年3月5日です。岡山出身の官僚、政治家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/06 20:49更新
|
sakatani yoshirou
阪谷芳郎と同じ誕生日3月5日生まれ、同じ岡山出身の人
TOPニュース
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター