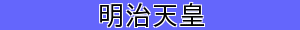明治天皇の情報(めいじてんのう) 皇族 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

明治天皇さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
明治天皇と関係のある人
児玉源太郎: 奉天会戦勝利後の明治38年(1905年)3月、児玉は、明治天皇へ奉天会戦の戦況報告を上奏することを名目に東京へ戻り、政府首脳の意見を早期戦争終結の方向にまとめる活動に着手した。 大隈重信: 6月24日、伊藤首相は大隈と板垣に政権を委ねるよう上奏するが、明治天皇は伊藤内閣が存続し、大隈と板垣が入閣するものと勘違いして裁可を行った。明治天皇は勘違いに気がついたが、6月27日に大隈と板垣二人に対して組閣の大命が降下した。しかし、明治天皇も過去の経緯から大隈に対して不信感を持っていたほか、外務大臣職をはじめとするポストの配分を巡って旧自由党と旧進歩党の間に対立が生じているなど前途は多難であった。 桂太郎: 山縣は、明治天皇の崩御(死去)により急きょ海外視察から帰国した桂に「新帝輔翼」の重要性を説き、内大臣兼侍従長として宮中に押し込めることで桂の政治的引退を図った。 西園寺公望: 孝明天皇が設置した学習院で学び、11歳の時からは御所に出仕し、祐宮(後の明治天皇)の近習となった。 岩倉具視: これを聞いた明治天皇は、勅命により東京大学医学部教授をしていたエルヴィン・フォン・ベルツを京都に派遣して診察させた。その後船で東京へ戻され、明治天皇から数度の見舞いを受けたが回復することはなく、最後の天皇の見舞いの翌日の7月20日死去。 新渡戸稲造: 稲之助は巡幸中に新渡戸家で休息していた明治天皇から「父祖伝来の生業を継ぎ農業に勤しむべし」という主旨の言葉をかけられたことから、農学を志すようになったという。 大正天皇: とは言え明治天皇とは異なり、大正天皇を偲び記念する運動はほとんどなく、誕生日は祝日とならず、大正神宮も造られなかった。 末松謙澄: 第1次伊藤内閣・鹿鳴館時代の明治19年(1886年)に日本へ帰国、伊藤の意向を受けて歌舞伎の近代化のため福地源一郎・外山正一と共に演劇改良運動を興し、明治天皇の歌舞伎見物(天覧歌舞伎)を実現させた。 建部遯吾: 遯吾も同僚の博士らと「日露条約批准拒否」の意見書を明治天皇に奉呈した。 金子堅太郎: また、後の維新史編纂会の発足に関わり、臨時帝室編修局総裁、『明治天皇紀』編纂局総裁、維新史料編纂会総裁、帝室編纂局総裁などを歴任し、『明治天皇紀』完成の功により伯爵に昇爵、さらに『維新史』を奉呈する。 伊藤博文: 明治15年(1882年)3月3日、明治天皇に憲法調査のための渡欧を命じられ、3月14日、河島醇・平田東助・吉田正春・山崎直胤・三好退蔵・岩倉具定・広橋賢光・西園寺公望・伊東巳代治ら随員を伴いヨーロッパに向けて出発した。 和宮: 慶応3年(1867年)1月9日に甥にあたる明治天皇が践祚すると、橋本実麗・実梁父子ら、孝明天皇の勅勘を蒙って参内を止められていた公卿たちが復帰し、佐幕派で占められていた朝廷の顔ぶれは大きく様変わりする。 渡辺邦男: 対する大蔵社長も『明治天皇と日露大戦争』以降、柳の下の泥鰌を狙って天皇映画に熱中する一方だった。『明治天皇と日露大戦争』であてて、もうひとつおまけに『雪之丞変化』、美空ひばりでしこたま会社に金を儲けさせて、新東宝から去っていかはりました」と語っている。 山県有朋: 辞表を受け取った明治天皇は西郷隆盛・従道兄弟に調停に入るよう命じた。 大正天皇: そこで威仁親王は自分の役割は終わったとして、1903年(明治36年)2月、明治天皇に東宮輔導廃止を進言した。明治天皇は即答を避けたが、威仁親王の体調が悪化したこともあり、同年6月に東宮輔導を免じられた。 渡辺節: 明治天皇の誕生日)に生まれたことから「節」と名づけられた。 乃木希典: 明治40年(1907年)1月31日、軍事参議官の乃木は学習院長を兼任することとなったが、この人事には明治天皇が大きく関与した。しかし、明治天皇の勅命により、乃木は予備役に編入されなかった。 幸徳秋水: これは当時では国際的に見ても先進的なもので、同年12月10日に田中正造が足尾銅山鉱毒事件について明治天皇に直訴した際の直訴状はまず秋水が書き、田中が手を加えたものである。 山県有朋: やむなく明治天皇は内大臣三条実美に内閣総理大臣を兼任させた。特に功労が大きいという明治天皇の特旨により、山縣は現役軍人であり続けることを許された。 西園寺公望: ある時、西園寺が三条実万の伝記である絵巻物を執筆して明治天皇に献上した。 西郷隆盛: 晩餐会の席で「作法を知らない」と言って、スープ皿を手に持ってスープを飲み干すなど、飾らない西郷の人柄を、明治天皇はとても気に入っていたと言われる。 三浦謹之助: 明治天皇、大正天皇、貞明皇后、昭和天皇、山縣有朋、西園寺公望、松方正義、大隈重信、桂太郎、寺内正毅、原敬、加藤高明、浜口雄幸、犬養毅、井上馨、平沼騏一郎、牧野伸顕、福沢諭吉、中村福助、三浦環、小唄勝太郎、大倉喜八郎、安田善次郎、福沢桃介 尾崎行雄: 相談した結果、後藤を正装させて、宮内省に向かわせたが明治天皇と会うことは許されず、クーデターを計画し始めた尾崎は、明治20年(1887年)、保安条例により東京からの退去処分を受けた。 板垣退助: 朕(明治天皇)今、人民の父母となってこの賊臣を排斥しなければ、いかにして、上に向かっては先帝の霊に謝罪し、下に向かっては人民の深いうらみに報いることが出来るだろうか。 徳富蘇峰: 本論…明治天皇時代の初期10年間〔39巻〕 板垣退助: しかし、自由民権運動の逮捕者が国事犯として恩赦の対象となり、また、板垣が相原に刺された際、明治天皇自らが「板垣は国家の元勲なり」と、勅使を見舞いとして差向けられた事や、事件の要因が私怨にあらず「国会を開設すべきか否か」と言う問題にある点などを挙げ、「民間人に対する殺害未遂」ではあるが「国事犯」としての要素を勘案すべきと板垣は主張して3月13日、恩赦歎願書を明治天皇へ奉呈した。 乃木希典: 明治45年(1912年)7月に明治天皇が崩御してから、乃木が殉死するまで3か月ほどの間、裕仁親王は乃木を「院長閣下」と呼んだ。これは、明治天皇の遺言によるものである。 西郷隆盛: この頃西郷は中性脂肪やコレステロールの増加による脂質異常症が悪化し、明治天皇が派遣した医師テオドール・ホフマンの指示で下剤を服用していた。 東郷平八郎: 明治天皇に理由を聞かれた山本は「東郷は運のいい男ですから」と奏したと言われているが、内田一臣によれば「この人が、ちょっといいんです」だったという。 石川啄木: これらの報道では秋水らの検挙容疑が明治天皇暗殺計画(旧刑法73条の「大逆罪」)であることは伏せられていたが、検挙者に対する各種令状(勾引状・勾留状など)には「刑法七十三条ノ罪被告事件」とあり、新聞社ではこの事実をつかんでいたとされることから、啄木は事件が大逆罪による検挙であるという認識を6月時点で持っていたと推測されている。 |
明治天皇の情報まとめ

明治天皇(めいじてんのう)さんの誕生日は1852年11月3日です。京都出身の皇族のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/06 03:21更新
|
meijitennou
明治天皇と同じ誕生日11月3日生まれ、同じ京都出身の人
TOPニュース
明治天皇と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】話題のアホネイター