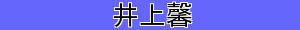井上馨の情報(いのうえかおる) 政治家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

井上 馨さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
井上馨と関係のある人
山尾庸三: 1888年2月7日法制局長官を辞任し、宮中顧問官・有栖川宮別当・北白川宮別当兼任のまま、2月15日に官庁集中計画を担う臨時建築局のの第二代総裁に就任した(初代は井上馨)。 板垣退助: 尾佐竹猛は費用の出所は三井であり、政府が板垣を懐柔するために井上馨が出させたものであると見ている。 三浦謹之助: 明治天皇、大正天皇、貞明皇后、昭和天皇、山縣有朋、西園寺公望、松方正義、大隈重信、桂太郎、寺内正毅、原敬、加藤高明、浜口雄幸、犬養毅、井上馨、平沼騏一郎、牧野伸顕、福沢諭吉、中村福助、三浦環、小唄勝太郎、大倉喜八郎、安田善次郎、福沢桃介 小林且弥: ドリームジャンボ宝ぶね 〜けっしてお咎め下さいますな〜(2013年1月6日 - 13日、青山劇場 / 26日、梅田芸術劇場) - 井上馨 役 山尾庸三: 文久3年(1863年)、藩命により陪臣から藩の士籍に列し、密航で伊藤博文・井上馨・井上勝・遠藤謹助と共にイギリスへ留学し、後に長州五傑(長州ファイブ)と呼ばれる。 西郷隆盛: しかしこれは財政に大きな負担を強いるものであり、大蔵省を掌握していた井上馨と、改革を進めようとする他の省庁の対立も激化していった。 藤巻潤: 巨人 大隈重信(1963年、大映) - 井上馨 西郷隆盛: 大蔵大輔(井上馨) チャニング=ウィリアムズ: 当時外務大臣であった井上馨は、ウィリアムズを指して、「あの人は聖人です」と常に評していたと言われる。 小村寿太郎: 1879年から外務卿、1885年から外務大臣を務めた井上馨は領事裁判権撤廃と関税自主権の一部回復のため、「鹿鳴館外交」の名で知られる欧化政策を積極的に進めており、欧米にならった法典を整備すること、裁判所に外国人判事を採用すること、および内地開放を条件に交渉を進めようとしていたが、これには政府内外からの批判や反対があった。 大隈重信: 元老山縣有朋が最初に推した徳川家達が辞退すると、元老井上馨の秘書望月小太郎は大隈と接触し、立憲同志会の加藤高明を協力させたうえで、大隈に組閣する気がないかと打診した。 明治天皇: 明治20年(1887年)4月の条約改正会議において外務大臣井上馨は、治外法権撤廃のための大幅譲歩案を提出することで、欧米列強諸国の支持を取り付けることに成功した。 鮎川義介: 明治13年(1880年)、旧長州藩士・鮎川弥八(第10代当主)を父とし、明治の元勲・井上馨の姪を母として山口県吉敷郡大内村(現在の山口市大内地区)に生まれた。 井上勝: 山尾・野村、および2人とは別に井上馨からの留学願を受けた周布政之助は、文久3年(1863年)4月3日、貿易商会伊豆倉商店の番頭・佐藤貞次郎(加賀藩との商用のため、山尾・野村の癸亥丸に乗船しており、3月20日頃兵庫で下船し、3月26日には上洛していた)を祇園の一力茶屋に招いて、この計画実現への助力を請い、承諾された。 大隈重信: 明治20年(1887年)8月、条約改正交渉で行き詰まった井上馨外務大臣は辞意を示し、後任として大隈を推薦した。山田顕義法務大臣は外国人裁判官に日本国籍を取らせる帰化法を提案し、伊藤枢密院議長、井上馨農商務大臣もこれに同意して条約改正交渉の施行を遅らせるよう求めた。 原敬: 徳川家達・清浦奎吾といった候補者の内閣は成立せず、山縣と井上馨は大隈重信を奏薦した。 明治天皇: 竹添公使は、11月12日に甲乙案を作成して本国の外務卿井上馨に送付して訓令を仰いだ。 井上勝: 1863年(文久3年):井上馨・遠藤謹助・山尾庸三・伊藤博文と共に5人でイギリス留学(長州五傑)。 豊田佐吉: 1899年(明治32年) - 大隈重信、井上馨ら明治の顕官が武平町工場を訪れる。 山本権兵衛: 当時の山本は軍務局長であったが、新聞各紙で「権兵衛大臣の独断専行」という表現で批判され、海軍の弱体化を懸念する山縣有朋や井上馨からも説明を求められたが、海軍大臣の西郷従道は、すべて山本に任せて自分が責任を取るとして改革を進めさせた。 西郷従道: 井上馨から海軍拡張案のことで尋ねられた際、「実はわしもわからん。 原敬: 退社後の原に目をつけたのは井上馨であった。 伊藤博文: このあと木戸とは疎遠になる代わりに、政権の重鎮となった大久保・岩倉と連携する道を選ぶ一方、盟友の井上馨とともに木戸と大久保の間を取り結び、板垣退助とも繋ぎを取り明治8年(1875年)1月の大阪会議を斡旋する。 石井正則: 大河ドラマ 花燃ゆ(2015年、NHK) - 井上馨 役 明治天皇: 明治12年(1879年)から外務卿に就任し、欧米諸国との条約改正に努力していた井上馨は、欧州では王室が外交の中心となっていることから、日本でも皇室外交を盛んにさせたいと考え、春と秋に2回園遊会を開いて諸外国の外交官を招待することを建言した。 清浦奎吾: これは井上馨が清浦を警保局長に任命しようと交渉しており、これを円満に断るために時間がかかったためであるとという。 木戸孝允: 大村益次郎、伊藤博文、井上馨、大隈重信ら開化派の官僚を登用して、兵制改革や官制改革など封建制の解体を目指す木戸に対し、大久保は副島種臣らと共に保守的な慎重論を唱えた。 木戸孝允: 後に井上馨らが担当して購入し、壬戌丸と名付けられた。 渋沢栄一: 大蔵省を辞職した栄一は、井上馨やアレクサンダー・フォン・シーボルト、その弟のハインリヒ・フォン・シーボルトの協力も得ながら明治6年(1873年)自ら設立を指導した第一国立銀行(後の第一銀行、第一勧業銀行、現:みずほ銀行)の総監役に就任する。 林董: この頃には伊藤との関係が修復されたらしく、外相就任には彼と井上馨・山縣有朋ら元老の意向を受けた西園寺の任命があってのことだった。 |
井上馨の情報まとめ

井上 馨(いのうえ かおる)さんの誕生日は1836年1月16日です。山口出身の政治家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 04:32更新
|
inoue kaoru
井上馨と同じ誕生日1月16日生まれ、同じ山口出身の人
TOPニュース
井上馨と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター