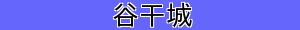谷干城の情報(たにたてき) 政治家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

谷 干城さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
谷干城と関係のある人
佐々友房: 大隈条約改正に反対する谷干城・浅野長勲らの日本倶楽部に与し、第一回帝国議会が開設されると、衆議院議員に立候補し当選を果たした。 井上馨: 明治20年(1887年)に改正案が広まると、裁判に外国人判事を任用するなどの内容に反対運動が巻き起こり、井上毅・谷干城などの閣僚も反対に回り分裂の危機を招いたため、7月に改正交渉延期を発表、9月に外務大臣を辞任。 西郷隆盛: 西郷隆盛が士族兵制論者か徴兵制支持者なのか、当時の政府関係者ですら意見が分かれており、谷干城や鳥尾小弥太は前者を、平田東助は後者であったとする見解を採っている。 明治天皇: 一方2月19日に鹿児島県令大山綱良は熊本鎮台司令長官谷干城陸軍少将に使者を送り、上京の趣旨を記した西郷の紹介状、大山の届書、中原尚雄に署名させた西郷暗殺供述書を渡したが、谷は受け取りを拒否し、もし西郷軍が熊本鎮台城下を強いて通過しようとするのならば、守備兵は抵抗せざるを得ないと告げた。 羊宮妃那: 幕末動乱美少女伝(2024年、谷干城) 大鳥圭介: 続いて大書記官兼参事院員外議官補工部技監に任じられ、第1次伊藤内閣の農商務大臣として転出した谷干城の後任として第3代学習院長に就任、華族女学校校長を兼務。 嶋岡晨: 『明治の人 反骨・谷干城』学芸書林 1981 「熊本城を救った男」河出文庫 明治天皇: しかしこの譲歩案は日本国内で朝野問わず激しい反発を巻き起こし、政府内では農商務大臣谷干城、フランス人内閣雇法律顧問ボアソナード、法務官僚井上毅などが反対の論陣を張った。 吉岡平: 『宇宙一の無責任男』シリーズの第2巻「明治一代無責任男」は、主人公のタイラー達がタイムワープの影響で明治時代(日清戦争時)の日本にタイムスリップするストーリーであるが、この作品にはマコト・ヤマモトの直接の先祖として山本権兵衛が、他に東郷平八郎、森鴎外、谷干城等が登場する。 山県有朋: 薩軍挙兵前の1月28日に、不穏な鹿児島情勢を警戒し、山縣は陸軍少輔大山巌や熊本鎮台司令長官谷干城に厳戒態勢を滞在中の京都から命じて、小倉の歩兵第14連隊から一個中隊を派遣して長崎港の防備を固めた。 郡司成忠: また、谷干城らの尽力によって「報效義会保護案」が議会で成立し、3年間補助金が政府から出ることも決まった。 坂本龍馬: 慶応3年6月(1867年7月)、龍馬の提示を受けた後藤はただちに京都へ出向し、建白書の形式で山内容堂へ上書しようとしたが、これより1ヶ月前の5月21日の時点で既に中岡慎太郎の仲介によって乾退助、毛利恭助、谷干城らが薩摩藩の西郷隆盛、吉井友実、小松帯刀らと薩土討幕の密約を結び、翌日容堂はこれを承認したうえで、乾らとともに大坂で武器300挺の買い付けを指示して土佐に帰藩していた。 板垣退助: 同日、土佐藩迅衝隊大軍監・谷干城が東京に凱旋。 近衛篤麿: 月曜会はしばらくして自然消滅に向かったが、篤麿は同じく五摂家出身の二条基弘らと共に三曜会に属し、谷干城らが結成した懇話会と共同歩調を取り貴族院で政治活動を行った。 樺山資紀: 西南戦争では熊本鎮台司令長官・谷干城少将の下、同鎮台参謀長として熊本城を負傷しつつも死守する。 板垣退助: 勿堂の山鹿流は、赤穂山鹿流の正統な伝系を継いでおり、ほかにも勝海舟、土方久元、佐々木高行、谷干城が勿堂から山鹿流を習得している。 板垣退助: 薩州屋敷焼打事件の一報に接し、西郷は「これで討幕の名分は立ち申した」と喜び、急ぎ土佐藩の谷干城を呼んで「遂に戦端は開かれましたぞ。 西郷隆盛: 5月21日、中岡慎太郎の仲介によって、京都の小松帯刀邸にて、土佐藩の乾退助、谷干城らと、薩摩藩の西郷、吉井幸輔らが武力討幕を議して、薩土討幕の密約(薩土密約)を結ぶ。 板垣退助: 慶応3年5月21日(1867年6月23日) 夕方、京都室町通り鞍馬口下る西入森之木町の近衛家別邸(薩摩藩家老・小松帯刀の寓居「御花畑屋敷」)において土佐藩の乾退助、中岡慎太郎、谷干城、毛利恭助は、薩摩藩の小松清廉、西郷吉之助(のちの隆盛)、吉井幸輔らと武力討幕を議し、 榎本武揚: 3月23日、榎本は谷干城や津田仙の助言を受け入れ、津田の案内で現地を視察。 板垣退助: 同日、土佐藩側は、福岡孝弟、乾退助、毛利吉盛、谷干城、中岡慎太郎が喰々堂に集まり討幕の具体策を協議。5月26日(太陽暦6月28日)、中岡慎太郎は再度、西郷隆盛に会い、薩摩藩側の情勢を確認すると同時に、乾退助、毛利吉盛、谷干城ら土佐藩側の討幕の具体策を報告した。 坂本龍馬: 慶応4年(1868年)4月に下総国流山で出頭して捕縛された新選組局長の近藤勇は、部隊の小監察であった土佐藩士谷干城の強い主張によって斬首に処された。 西郷隆盛: 12月28日、土佐藩・山田平左衛門、吉松速之助らが伏見の警固につくと、西郷は土佐藩士・谷干城へ薩長芸の三藩には既に討幕の勅命が下ったことを示し、薩土密約に基づき、乾退助を大将として国元の土佐藩兵を上洛させ参戦することを促した。 神山繁: 鹿鳴館(1986年、東宝)- 谷干城 役 大槻文彦: 1891年6月23日、文彦の仙台藩時代の先輩にあたる富田鉄之助が、芝公園の紅葉館で主催した『言海』完成祝賀会には、時の内閣総理大臣・伊藤博文をはじめとし、山田顕義、大木喬任、榎本武揚、谷干城、勝海舟、土方久元、加藤弘之、津田真道、陸羯南、矢野龍渓ら、錚錚たるメンバーが出席した。 板垣退助: 12月28日(太陽暦1868年1月22日)、土佐藩・山田喜久馬、吉松速之助らが伏見の警固につくと、薩摩藩・西郷隆盛は土佐藩士・谷干城を陣中に招き薩摩・長州・安芸の三藩には既に討幕の勅命が下ったことを示し、薩土密約に基づき、乾退助を大将として国許の土佐藩兵を上洛させ参戦することを促した。 板垣退助: この日、乾退助は在京の同志である谷干城に宛て、左行秀の不穏な行動に注意するよう書簡を託した。 乃木希典: 2月14日、鎮台司令長官谷干城の命を受けて小倉から熊本に到着し作戦会議に参加。 板垣退助: そこで、乾退助はこの事を伝えるため腹心の軍監・谷干城を伝令として土佐へ戻し、第二軍を設えて松山討伐へ向かわせる事を指示。 明石潮: 姿三四郎 第一部(1955年、東映) - 谷干城 |
谷干城の情報まとめ

谷 干城(たに たてき)さんの誕生日は1837年3月18日です。高知出身の政治家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 12:42更新
|
tani tateki
谷干城と同じ誕生日3月18日生まれ、同じ高知出身の人
TOPニュース
谷干城と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター