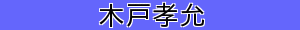木戸孝允の情報(きどたかよし) 政治家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

木戸 孝允さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
木戸孝允と関係のある人
明治天皇: 草案は由利公正と福岡孝弟が作り、木戸孝允がその修正に加わって作成された。 高杉晋作: また木戸孝允・大村益次郎らによって東京招魂社(現在の靖国神社)に吉田松陰・久坂玄瑞・坂本龍馬・中岡慎太郎たちとともに祀られた。 風間杜夫: 田原坂(1987年) - 木戸孝允 桂こごろう: 「桂こごろう」という芸名は、入門当時に明智小五郎が登場する推理小説をべかこが愛読していたことに由来する(同音の別名「桂小五郎」を持つ木戸孝允にも由来しているかどうかは不明)。 加藤高明: 西園寺公望は加藤のことを大久保利通、木戸孝允、伊藤博文とならべて「一角の人物であった」と述べるなど高く評価していた。 明治天皇: 大久保利通と木戸孝允も建白を受理する待詔院学士という立場に追いやられて政府第一線から退かされている。 和田小六: 父は木戸孝正で、木戸孝允は義理の祖父に当たる。 陸奥宗光: その後、廃藩置県を受け、8月神奈川県令として再度出仕、地租改正局長(1872年)、大蔵少輔(1873年6月)などを歴任するが、薩長藩閥政府の現状に不満を抱き、木戸孝允への接近を通して、薩長勢力の一角に楔を打ち込もうとする。 陸奥宗光: 後長州藩の桂小五郎(木戸孝允)・板垣退助・伊藤俊輔(伊藤博文)などの志士と交友を持つようになる。 伊藤博文: 翌安政5年(1858年)7月から10月まで松陰の推薦で長州藩の京都派遣に随行、帰藩後は来原に従い安政6年(1859年)6月まで長崎で勉学に努め、10月からは来原の紹介で来原の義兄の桂小五郎(のちの木戸孝允)の従者となり、長州藩の江戸屋敷に移り住んだ。 武市瑞山: 維新後、木戸孝允が山内容堂との酒席で酔った勢いで「殿はなぜ武市半平太を斬りました?」と詰めたが、彼は「藩令に従ったまでだ」と答えたきりだったと言われる。 五代友厚: 明治8年(1875年)1月 - 2月 - 五代の斡旋により、大久保利通・木戸孝允らによる大阪会議開催。 西郷隆盛: 参議(西郷隆盛、木戸孝允、板垣退助、大隈重信) 榎本武揚: 政府内では榎本らの処置に関して対立があり、木戸孝允ら長州閥が厳罰を求めた一方、榎本の才能を評価していた黒田清隆、福沢諭吉らが助命を主張。 大隈重信: 大隈の回想によれば、井上馨が「天下の名士」を長崎においておくのは良くないと木戸孝允に推薦したためであるという。 大久保利通: 明治維新の元勲であり、西郷隆盛、木戸孝允と並んで「維新の三傑」と称され、「維新の十傑」の1人でもある。 尾崎行雄: 行雄の父・尾崎行正の生家は漢方医を業とし、漢学者・藤森弘庵の私塾に桂小五郎(木戸孝允)の先輩として学んだ。 大久保利通: さらに同じく維新の三傑の一人木戸孝允とともに「維新時代の二大英傑」と評している(大隈は西郷を評価していなかった)。 岩倉具視: 1871年(明治4年)2月、三条邸に岩倉具視・大久保利通・西郷隆盛・木戸孝允・板垣退助ら政府首脳が集まり、廃藩置県に備えて藩の指揮権に属さない天皇直属の御親兵をつくる必要があるということで一致。 山田顕義: 代表的なものに、明治3年(1870年)大木民平の「建国法意見書」や江藤新平の「国法会議案」、明治5年(1872年)木戸孝允の命により青木周蔵が起草した「帝号大日本政典」や民撰議院「仮規則及議事上院略規」、明治10年(1877年)元老院「日本国憲案」、明治13年(1880年)「国憲草案」及び筑前共愛公衆会による「大日本帝国憲法見込書草案」や元田永孚の「国憲大綱」などがある。 三条実美: しかし征韓反対派の岩倉・木戸孝允・大久保利通が辞表を提出し、いずれにしても政府の分裂は避けられなくなった。 五代友厚: 1868年(慶応4年)1月、新政府で遷都機運あるなか、参与大久保利通(39歳)は、因習の京都を離れ、交通の開けた大坂以外に首都はないと大坂遷都を提案し、これに長州の木戸孝允が賛成。 高杉晋作: 長州藩では、晋作の渡航中に俗論派の長井雅楽らが失脚、尊王攘夷(尊攘)派が台頭し、晋作も桂小五郎(木戸孝允)や久坂義助(久坂玄瑞)らとともに尊攘運動に加わり、江戸・京都において勤皇・破約攘夷の宣伝活動を展開し、各藩の志士たちと交流した。 荒木貞夫: 誕生日は木戸孝允の命日でもある。 山県有朋: 慶応3年(1867年)2月、山縣は木戸孝允の支配下として京都と摂津の間で事情探索を行うことを命じられた。 岩倉具視: 使節団には外務卿である岩倉自らが特命全権大使として参加し、参議・木戸孝允や大蔵卿・大久保利通、工部大輔・伊藤博文らを副使として伴い、1871年12月23日(明治4年11月)に横浜港をたち、1年10か月にわたり欧米諸国を巡り、各国元首と面会して国書を手渡したが、条約改正の糸口はつかめなかった。 明治天皇: すでに一年半前に、西郷隆盛と木戸孝允の間で幕府に対抗するための薩長同盟が結ばれており、旧体制のままで徳川幕府が政治を主導することの強い疑問が、西南雄藩の間で強まっていたのである。 和田昭允: 和田小六・春子の長男、木戸孝允の義理の曾孫、山尾庸三の曾孫、吉川重吉の孫、木戸幸一の甥、都留重人の義弟。 新島襄: 明治8年(1875年)1月、新島は大阪で木戸孝允に会い、豪商磯野小右衛門から出資の約束を得て大阪での学校設立を目指したが、府知事渡辺昇のキリスト教反対のため断念し、木戸の勧めにより長州出身の槇村正直が府知事を務める京都を新たな候補地と定めた。 山田浩貴: 明治撃剣-1874-(武市熊吉、木戸孝允) |
木戸孝允の情報まとめ

木戸 孝允(きど たかよし)さんの誕生日は1833年8月11日です。山口出身の政治家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 20:23更新
|
kido takayoshi
木戸孝允と同じ誕生日8月11日生まれ、同じ山口出身の人
TOPニュース
木戸孝允と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター