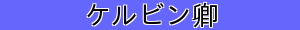ケルビン卿の情報(Kelvin) 物理学者 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

ケルビン卿さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
|
ケルビン卿と同じ出身地の人 |
ケルビン卿と関係のある人
田中舘愛橘: グラスゴー大学ではユーイングの旧師であったケルビン卿に師事した。 ピーター=ガスリー=テイト: をケルビン卿とともに書いたことや結び目理論に関する初期の研究で有名。 ジョージ=ウェスティングハウス: 現代の技術者なら誰でも、ウェスティングハウスは明らかに永久機関を作ろうとしていたと見るであろうし、彼と交際のあったイギリスの物理学者ウィリアム・トムソン(ケルビン卿)は、ウェスティングハウスのやろうとしていることは熱力学の法則に反していると助言をした。 ヘルマン=ヘルムホルツ: マイヤー、ジュール、ウィリアム・トムソン(ケルビン卿)と並ぶエネルギー保存則の確立者の一人とみなされるようになった。 |
ケルビン卿の情報まとめ

ケルビン卿(Kelvin)さんの誕生日は1824年6月26日です。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 07:15更新
|
Kelvin
ケルビン卿と同じ誕生日6月26日生まれの人
TOPニュース
ケルビン卿と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター