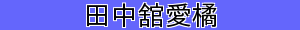田中舘愛橘の情報(たなかだてあいきつ) 地球物理学者 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

田中舘 愛橘さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
田中舘愛橘と関係のある人
トマス=メンデンホール: 田中舘愛橘 福田繁雄: 『ローマ字の宇宙』(2001年) - 田中舘愛橘記念科学館 和田小六: このころ風洞の研究を行ない、田中舘愛橘らと交流があった。 長岡半太郎: 物理学科に進んでからは、教授山川健次郎や助教授田中舘愛橘、イギリス人教師ノットのもとで学んでいる。 土岐善麿: 『NAKIWARAI』はヘボン式を採用したが、すぐに日本式ローマ字に転向し、田中舘愛橘、芳賀矢一、田丸卓郎指導のもとに「ローマ字世界」の編集に当たる。 木村栄: 同年、東京帝国大学理科大学星学科に入学し、寺尾寿に位置天文学を、田中舘愛橘に地球物理学を学んだ。 田中舘秀三: 菅原孝平「今やらねば 田中舘愛橘の生涯 17」(PDF)『広報 にのへ』第239号、二戸市、2015年12月1日、17頁、2018年8月28日閲覧。 木村栄: 1892年(明治25年)に大学院に進み、震災予防調査会の命を受けた田中舘愛橘教授の下で全国地磁気測量を始め、1895年に、嘱託として「緯度変化観測方」となり、緯度観測を行なった。 田中舘秀三: 日本の地球物理学の先駆者である田中舘愛橘の養子。 |
田中舘愛橘の情報まとめ

田中舘 愛橘(たなかだて あいきつ)さんの誕生日は1856年10月16日です。岩手出身の地球物理学者のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/06 04:03更新
|
tanakadate aikitsu
田中舘愛橘と同じ誕生日10月16日生まれ、同じ岩手出身の人
TOPニュース
田中舘愛橘と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター