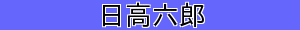日高六郎の情報(ひだかろくろう) 社会学者、評論家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

日高 六郎さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
日高六郎と関係のある人
清水幾太郎: 作田啓一は、清水幾太郎と日高六郎を対比させ、日高の時評は「想像以上に社会学的であり、いくらか誇張すれば、時事的発言がそのまま彼の社会学の仕事となっている」と評しており、対して清水は日高ほどの一貫性がなく清水の時評は「社会学を超えたプラス・アルファの豊かさにある」と評している。 稲葉三千男: 『マス・コミュニケーション入門』(日高六郎、佐藤毅と)有斐閣双書、1967年 清水幾太郎: 60年安保時に丸山真男は、強行採決は議会政治の破壊だとして反安保改定阻止運動を、反安保から民主主義擁護に目標転換するが、清水は1960年5月23日日本ジャーナリスト会議の事務所に翌日の教育会館の会合の打ち合わせに行った際に、「日高六郎etcみんな小生を警戒している。 エーリッヒ=フロム: 1941年『自由からの逃走』日高六郎訳 創元社 1951 宇野重吉: 1968年2月金嬉老事件の際、鈴木道彦や日高六郎、中嶋嶺雄、中野好夫らと共に銀座東急ホテルで「金さんへ」という呼びかけで始まる文書をとりまとめて、後日文化人・弁護士5人がその文書を吹き込んだテープを持って、金嬉老を訪ね会見している。 暉峻淑子: 日高六郎 編『教科書検定 私の体験』アドバンテージサーバー〈ブックレット生きる〉、1994年。 中嶋嶺雄: また金嬉老事件の際、鈴木道彦や中野好夫、日高六郎、宇野重吉らと共に銀座東急ホテルで「金さんへ」という呼びかけで始まる文書をとりまとめて、後日文化人・弁護士5人がその文書を吹き込んだテープを持って、金嬉老を訪ね会見した。 尾崎盛光: 1955年、日高六郎の推薦で東京大学文学部事務室に勤務、1961年に事務長。 清水幾太郎: 日高六郎は『現代随筆全集13 三木清・清水幾太郎集』(1953年)の解説において、清水は偽装転向どころか、戦前・戦後いささかもぶれていなかったと手放しの賛辞を送っている。 中野好夫: 1968年2月金嬉老事件の際、鈴木道彦や日高六郎、中嶋嶺雄、宇野重吉らと共に銀座東急ホテルで「金さんへ」という呼びかけで始まる文書をとりまとめて、後日文化人・弁護士5人がその文書を吹き込んだテープを持って、金嬉老を訪ね会見した。 黒川創: 『日高六郎・95歳のポルトレ 対話を通して』(2012年、新宿書房) |
日高六郎の情報まとめ

日高 六郎(ひだか ろくろう)さんの誕生日は1917年1月11日です。旧 中国出身の社会学者、評論家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 09:49更新
|
hidaka rokurou
TOPニュース
日高六郎と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター