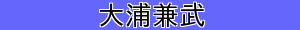大浦兼武の情報(おおうらかねたけ) 政治家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

大浦 兼武さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
大浦兼武と関係のある人
大隈重信: 特に選挙直前に大浦兼武を内務大臣に転任させ、政権の力を利用した激しい選挙干渉は、大隈内閣を支持していた吉野作造をも失望させるほどのものであった。 大隈重信: 7月下旬、大浦兼武内相が二個師団増設問題の決議の際、野党議員を買収したという疑惑が明らかになった(大浦事件)。 伊沢多喜男: ところが内務大臣の大浦兼武が失脚した大浦事件に巻き込まれる形で辞職。 原敬: これに加えて大浦兼武内務大臣による強力な選挙干渉が行われた。 大隈重信: 同志会からは加藤高明が外務大臣、若槻礼次郎が大蔵大臣、大浦兼武が農商務大臣、武富時敏が逓信大臣として入閣し、中正会からはかつての側近尾崎行雄が司法大臣として入閣した。 平田東助: 陸軍および内務系官僚に広範な「山縣閥」を築いた山縣側近の中で、陸軍の側近が桂太郎・児玉源太郎・寺内正毅らとすれば、平田は清浦奎吾・田健治郎・大浦兼武らと並ぶ官僚系の山縣側近として人脈を形成した。 大隈重信: 改革派は児玉源太郎、清浦奎吾、大浦兼武ら外部から党首を迎え、桂太郎首相に接近しようとする動きも見せていた。 大正天皇: 1915年(大正4年)、第2次大隈内閣の大浦兼武内務大臣の汚職事件が発覚すると、7月に大隈重信首相は「事件の責任を取る」として全閣僚の辞表を天皇に提出した。 高野佐三郎: 大正元年(1912年)10月、大日本帝国剣道形が完成し、大日本武徳会会長大浦兼武から感謝状と「剣道統一」の書を贈られた。 |
大浦兼武の情報まとめ

大浦 兼武(おおうら かねたけ)さんの誕生日は1850年6月15日です。鹿児島出身の政治家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2025/06/27 17:13更新
|
ooura kanetake
大浦兼武と同じ誕生日6月15日生まれ、同じ鹿児島出身の人
TOPニュース
大浦兼武と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター