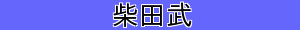柴田武の情報(しばたたけし) 言語学者 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

柴田 武さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
柴田武と関係のある人
祖父江孝男: 現代の日本語 柴田武、徳川宗賢共著 三省堂選書 1977 山本五十六: 1933年(昭和8年)夏、柴田武雄によれば、横須賀海軍航空隊(横空)研究会において、日高実保(大尉、海兵50期)が雷撃訓練に対空砲火や敵戦闘機の妨害の概念を取り入れるよう主張し、遠距離での発射を見越した高々度高速発射砲や魚雷の改善を求め、続いて柴田大尉が戦闘機の機銃の射程延長と照準器や兵器弾薬の発明の必要性を訴えると、山本が立ち上がり2人の意見を言語道断と否定し、「そもそも帝国海軍のこんにちあるは、肉迫必中の伝統的精神にある。 碇義朗: 『鷹が征く 大空の死闘 源田実VS柴田武雄』光人社、2000年4月。 碇義朗: 『激闘海軍航空隊 「零戦」の柴田武雄と「紫電改」の源田実』光人社〈光人社NF文庫〉、2007年12月。 大西瀧治郎: 計画していた小空母を使用した戦闘機隊の効率の低さ、戦闘機と陸上攻撃機の協同の難から柴田武雄が提案した。 岩淵悦太郎: 名づけ 柴田武共著 筑摩書房 1964 樋口夢祈: オサエロ(2013年9月、両国エアースタジオ) - 柴田武夫 役 堀越二郎: 海軍からのあまりに高い性能要求に悩み、会議において堀越は「格闘性能、航続力、速度の内で優先すべきものを1つ挙げてほしい」と要求するが、源田実の「どれも基準を満たしてもらわなければ困るが、あえて挙げるなら格闘性能、そのための他の若干の犠牲は仕方ない」という意見と、柴田武雄の「攻撃機隊掩護のため航続力と敵を逃がさない速力の2つを重視し、格闘性能は搭乗員の腕で補う」という意見が対立し、両方正論で並行したため、堀越は自分が両方の期待に応えようと決めていた。 志賀廣太郎: 大学では演技の他に狂言、日舞、バレエ、体操などを学んだが、なかでも能を観世銕之丞に学んだことは印象に残っており、音声学を学んだ柴田武からは、「君の声はいい声だから大事にしなさい」と言われたという。 |
柴田武の情報まとめ

柴田 武(しばた たけし)さんの誕生日は1918年7月14日です。愛知出身の言語学者のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 07:55更新
|
shibata takeshi
柴田武と同じ誕生日7月14日生まれ、同じ愛知出身の人
TOPニュース
柴田武と近い名前の人
話題のアホネイター