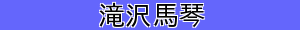滝沢馬琴の情報(たきざわばきん) 作家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

滝沢 馬琴さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
滝沢馬琴と関係のある人
杉本苑子: 『滝沢馬琴』(1977年、文藝春秋)のち文庫、講談社文庫 日下武史: びいどろで候〜長崎屋夢日記(1990年、NHK) - 滝沢馬琴 本山一城: 南総里見八犬伝(1985年 滝沢馬琴作 旺文社/ぽるぷ出版) 角田喜久雄: 小学生の頃から、俳句、短歌、新体詩の投稿をしており、滝沢馬琴、山東京伝、黒岩涙香を愛読、中学時代はトルストイ、ドストエフスキー等を愛読していた。 坪内逍遥: 父から漢学書類を読まされた他に、母の影響を受け、11歳頃から貸本屋に通い、読本、草双紙などの江戸戯作や俳諧、和歌に親しみ、ことに滝沢馬琴に心酔した。 役所広司: 八犬伝(2024年公開予定) - 主演・滝沢馬琴 役 杉本苑子: 1977年 『滝沢馬琴』で第12回吉川英治文学賞 岡村賢二: 八犬士(原作:滝沢馬琴、2005年 - 2006年、『別冊漫画ゴラク』、全2巻) みやぞえ郁雄: マンガ南総里見八犬伝(原作:滝沢馬琴) 睦月ムンク: 里見八犬伝 上巻・下巻(しかたしん、原作:滝沢馬琴/ポプラポケット文庫) 辻本祐樹: HOKUSAI(2020年) - 滝沢馬琴 役 亀井秀雄: そして、逍遥が取り上げた滝沢馬琴の物語作法論や本居宣長の源氏物語論を、実作の細部と照合しながら分析をした。 桂歌丸: その際には「正直二度とやりたくないです」と述べたが、2012年にも『伏 鉄砲娘の捕物帳』において滝沢馬琴役を演じている。 宮田雅之: 1998年に滝沢馬琴没150年を記念して国内6都市で「八犬伝」展を開催 総数360点の挿絵を一挙公開。 増田晶文: 山東京伝、恋川春町、喜多川歌麿、東洲斎写楽、十返舎一九、滝沢馬琴など才能のある人物を見つけ育てて世に送り出した、18世紀の江戸の名物本屋の活躍と胸に秘めた渇望、波乱に満ちた生涯を描いた。 |
滝沢馬琴の情報まとめ

滝沢 馬琴(たきざわ ばきん)さんの誕生日は1767年7月4日です。東京出身の作家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/06 05:15更新
|
takizawa bakin
滝沢馬琴と同じ誕生日7月4日生まれ、同じ東京出身の人
TOPニュース
滝沢馬琴と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター