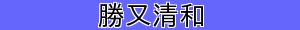勝又清和の情報(かつまたきよかず) 将棋 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

勝又 清和さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
勝又清和と関係のある人
森内俊之: 勝又清和によれば、「自陣飛車の似合う棋士は?」という質問をしたところ、多くの棋士から名前が挙がったと言う。 加藤一二三: また勝又清和によれば「昼はコンビニかスーパーでサンドイッチや果物を買う」ことが多かった。 藤井猛: 2007年2月5日の北浜健介との対局で突然「ゴキゲン中飛車」を指したことに関しては、勝又清和のインタビューで「もう鰻屋だけじゃやってけない。 佐々木勇気: 石田和雄の弟子で棋士となったのは、勝又清和以来、佐々木が15年半ぶり・2人目である。 大山康晴: この転向について、勝又清和は「ファンに喜ばれる将棋を指そうと考えたため」と説明しているが、大山の場合は多忙の中、兄弟子の大野源一から序盤がある程度決まっている(序盤の研究を省略できる)振り飛車を勧められたためとも言われている。 瀬川晶司: 三段リーグには1992年から4年8期在籍していたが、最も高順位だったのは第16回(1994年後期)で、前半は8勝1敗と好調だったが年齢制限で後が無い勝又清和に敗れてから失速した末の8位であった(勝又は2位で四段昇段を果たす)結局昇段はかなわず、第18回(1995年後期)を最後に年齢制限(26歳)で退会。 羽生善治: 勝又清和は「大山の力強い受け、中原の自然流の攻め、加藤(一)の重厚な攻め、谷川の光速の寄せ、米長の泥沼流の指し回し、佐藤(康)の緻密流の深い読み、丸山の激辛流の指し回し、森内の鉄板流の受け、といった歴代名人の長所を状況に応じて指し手に反映させる‘歴代名人の長所をすべて兼ね備えた男’」としている。 瀬川晶司: 解説をしていた勝又清和は、瀬川がアマチュアらしからぬ手を連発するので非常に驚いていた。 |
勝又清和の情報まとめ

勝又 清和(かつまた きよかず)さんの誕生日は1969年3月21日です。神奈川出身の将棋棋士のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 18:36更新
|
katsumata kiyokazu
勝又清和と同じ誕生日3月21日生まれ、同じ神奈川出身の人
TOPニュース
勝又清和と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター