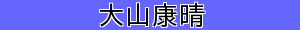大山康晴の情報(おおやまやすはる) 将棋 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

大山 康晴さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
大山康晴と関係のある人
廣津久雄: 大山康晴から、「振り飛車をやったらどうだね?振り飛車は、楽しいよ」と棋風を変えることを勧められたが、振り飛車党にはならなかった。 島田良夫: 2008年、70歳のときに、第15回「大山康晴賞」を日本将棋連盟から授与された。 米長邦雄: 1970年(昭和45年)、王位戦で大山康晴に挑戦。 林葉直子: 大山康晴十五世名人の大ファン。本人曰く「女流プロになりたての頃は、大山先生の魅力に気付かなかった私だが、今は、大山将棋の懐の深さと大山康晴に惚れてしまったのである」とのことで、2010年のLPSAでの復帰戦でも大山が揮毫した扇子を持って対局に挑んだほどである。 羽生善治: これにより、通算勝利数が1433勝となり大山康晴十五世名人が持つ最多勝利数記録に並び、1位タイとなった。 羽生善治: 大山康晴(3回戦)、加藤一二三(4回戦 = 準々決勝)、谷川浩司(準決勝)、中原誠(決勝)と、当時現役の名人経験者4人をすべて破るという、まるで作った舞台設定のような勝ち上がりで優勝した。 バトルロイヤル風間: 大山康晴との対談に自分の漫画を読んだことがあるか聞き、「ない。 行方尚史: 大山康晴十五世名人門下。 久保利明: これで、関西所属棋士としては谷川浩司(2004年度に王位・棋王の二冠から王位失冠)以来5年半ぶりとなる二冠王となり、振り飛車党が二冠王となるのは大山康晴以来、37年ぶりである。 内藤国雄: 1972年度の第13期王位戦七番勝負における大山康晴王位との戦いでは、第3局と第5局で大山得意の振り飛車に対し「鳥刺し」戦法含みの序盤戦術を見せて、いずれも勝利。 塚田正夫: なお、1958年に段位としての九段昇段規定が新設され、大山康晴と升田幸三が九段に昇段したが、塚田は、九段戦防衛により保持していた「タイトルとしての九段」を1956年に失冠してからは、永世称号に基づき「段位としての九段」を称していた。 高川格: この時将棋の指導に来ていた大山康晴は、高川が本因坊となったのと同じ1952年に名人となり、関西から囲碁と将棋で同時に最高位者を出したのは史上初めてとして話題にされ、以後大山とは対談などで顔を合わせるようになった。 升田幸三: 木見金治郎の弟子であり、木村義雄・塚田正夫・大山康晴と死闘を演じ、木村引退後は大山と戦後将棋界で覇を競った。 内藤國雄: 十五世名人である大山康晴を苦手とし、対戦成績も18勝50敗と大きく負け越している。 佐瀬勇次: 米長邦雄・丸山忠久と二人の名人の師匠となったが、これは近代将棋史上木見金治郎(大山康晴・升田幸三の師匠)と佐瀬のみの記録である。 河口俊彦: また大山康晴と周辺の人物を描いた「大山康晴の晩節」で将棋ペンクラブ大賞を受賞した。 桐山清澄: 大山康晴に1-3で敗れ、奪取はならなかった。 村山聖: A級在籍のまま逝去したのは、山田道美、大山康晴に続き史上3人目である。 中原誠: その後、大山康晴、山田を相手に2期防衛して棋聖3連覇。 花田長太郎: 次の第7期名人戦では、第2期順位戦で前名人となった木村を押しのけて3位となり、升田幸三、大野源一、大山康晴と共に挑戦者決定戦の出場資格を得た。 斎藤栄: 1997年、第4回大山康晴賞を受賞。 木見金治郎: 近代将棋黎明期の祖となっている人物としては下記の通り、最も多い11人となる弟子を輩出した名伯楽として知られ、特に戦後の将棋界を牽引した升田幸三と大山康晴が有名。 植山悦行: 一次予選決勝では佐藤康光を、二次予選決勝では大山康晴を破った。 南芳一: 二次予選通過後、本戦で4人のタイトル経験者(米長邦雄、高橋道雄、大山康晴、加藤一二三)をなで斬りし、桐山清澄棋聖に挑戦。 塚田正夫: 1960年の第1期王位戦、1962年の第1期棋聖戦でタイトル戦登場を果たすが、いずれも大山康晴に敗れた。 升田幸三: 生涯のライバル大山康晴との対局について、王将戦の記録係を務めた内藤國雄はこう語っている。 羽生善治: 一方、第68回NHK杯戦では、羽生本人も含めた羽生世代の棋士4人(羽生・森内俊之・丸山忠久・郷田真隆)が若手の強豪を退けてベスト4を占める中、羽生は準決勝で丸山、決勝で郷田を破り、NHK杯11回目の優勝と一般棋戦で大山康晴の44回を超える45回目の優勝を果たした。 花村元司: 大山康晴や中原誠には大きく負け越ししているものの、通算成績は棋戦優勝3回、A級通算16期。 荒巻三之: 名人経験者の塚田正夫に勝利する健闘を見せたものの、升田幸三・大山康晴ら強豪の壁は厚く2勝6敗の成績に終わり、残留はできずに1期でB級に陥落することとなった。 久保利明: また、対抗型を自らの土俵としていることもあり、振り飛車党相手には居飛車側を持って戦うことも多い(いわゆる大山康晴の棋風タイプである。 |
大山康晴の情報まとめ

大山 康晴(おおやま やすはる)さんの誕生日は1923年3月13日です。岡山出身の将棋棋士のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/06 08:04更新
|
ooyama yasuharu
大山康晴と同じ誕生日3月13日生まれ、同じ岡山出身の人
TOPニュース
大山康晴と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター