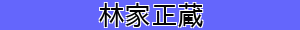林家正蔵の情報俳優 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

林家 正蔵さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
林家正蔵と関係のある人
春風亭小朝: 元妻の泰葉は初代林家三平の次女であり、9代目林家正蔵(旧名:こぶ平)と2代目林家三平(旧名:いっ平)は小朝と泰葉の結婚時代は義弟であった。 日高のり子: アフレコ現場では、共演していた林家こぶ平(現・林家正蔵)と共に上杉達也役の三ツ矢雄二を始めとする先輩声優や、音響監督の藤山房伸から毎回厳しい演技指導を受け、時にプレッシャーを感じることもあった。 海老名美どり: 妹は泰葉、弟は9代目林家正蔵と2代目林家三平。 春風亭小朝: 林家正蔵との関係 林家木久扇: 林家彦六(八代目林家正蔵)- 木久扇の師匠。 野中直子: 林家正蔵のサンデーユニバーシティ 下嶋兄: 9代目林家正蔵 - 叔父、母・美どりの弟 関根勤: 林家正蔵 所ジョージ: しかし、収録再開後も体調不良は三週間に渡って続き、『所さんの世田谷ベース』や『所さんの目がテン!』などの収録は、体調が回復するまでキャンセルされた(「所さんの目がテン!」では、MCの代役に林家正蔵や峰竜太を立てて収録された)。 立川談志: 同業の先輩である8代目林家正蔵(のちの林家彦六)からは「談志は自殺するのでは」と危惧された。 林家正雀: 1974年2月、八代目林家正蔵に入門。 林家たま平: 2013年4月 - 父・九代目林家正蔵の七番弟子として入門し、落語界初の四世落語家として歩み出す。 林家木久扇: 同年3月、八代目林家正蔵一門へ移籍、「木久蔵」と改名し、新宿末廣亭で初高座(演題は「寿限無」)。 海宝直人: 「林家正蔵の演芸図鑑」(2023年1月22日・29日、NHK) 泰葉: 祖父:七代目林家正蔵(本名・海老名 春風亭昇太: なお、同じ笑点メンバーである春風亭一之輔は林家彦六(八代目林家正蔵)の一門で、元々は3代目柳家小さんの系統である。 林家こん平: 正蔵の弟でこん平の直弟子である2代目林家三平(当時の芸名は林家いっ平)もメンバーになる前の2005年4月に番組内で行われた9代目林家正蔵襲名披露口上の席上で、師匠快癒を祈念して「チャラーン」を披露した。 小沢昭一: 12月14日に千日谷会堂で行われた本葬では生島ヒロシ、永六輔、乙武洋匡、加藤武、桂米團治、神津善行、黒柳徹子、篠田正浩、春風亭小朝、露木茂、長峰由紀、中村メイコ、野坂昭如、林家正蔵、林家三平、吉行和子ら850人が参列した。 林家木久扇: 彦六が8代目として名乗っていた「林家正蔵」という名は、7代目林家正蔵没後、7代目の子息・初代三平(海老名家)から一代限りという約束で借りたものなので、8代目林家正蔵はその義理から、自分の一門で「林家」の亭号を増やさないように、弟子が真打になると全員春風亭・橘家など「林家」以外の名に改名させることとした。 三笑亭笑三: 三笑亭笑三 - 後∶初代林家正蔵 林家正楽: 林家正楽 - 後∶四代目林家正蔵 日髙のり子: アフレコ現場では、共演していた林家こぶ平(現・林家正蔵)と共に上杉達也役の三ツ矢雄二を始めとする先輩声優や、音響監督の藤山房伸から毎回厳しい演技指導を受け、時にプレッシャーを感じることもあった。 海老名香葉子: 絵本作品の中でも『うしろの正面だあれ』は自身の少女時代の戦争経験を元にした作品であり、長男である林家こぶ平(現:九代目林家正蔵)が本名の海老名泰孝名義で出演する劇場用映画も制作されるなどしていて特に著名な作品として知られる。 拡森信吾: 林家正蔵の東京みち探検隊! 石川真紀: 林家正蔵のサンデーユニバーシティ(日曜 7:30 - 8:00)(野中直子アナウンサーの定年退職を受け、2011年4月10日 - 2018年4月1日まで担当) 林家時蔵: 1973年2月、八代目林家正蔵に入門。 下嶋兄: また従弟に落語家の林家たま平、ぽん平兄弟がいる(いずれも母・美どりの長弟である林家正蔵(旧名・こぶ平)の実子)。 はやし家林蔵: 1965年 - 八代目林家正蔵門下へ移籍し二ツ目昇進、「時蔵」と改名。 三遊亭好楽: 高校卒業後の1966年4月、19歳の時に八代目林家正蔵(のち彦六)に弟子入りを志願するも、その時は「私は来月70歳になるから」と弟子入りを断られた。 林家時蔵: 1973年2月 - 八代目林家正蔵に入門。 |
林家正蔵の情報まとめ

林家 正蔵()さんの誕生日は1894年3月31日です。愛知出身の俳優のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 22:49更新
|
林家正蔵と同じ誕生日3月31日生まれ、同じ愛知出身の人
TOPニュース
林家正蔵と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター