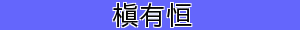槇有恒の情報(まきゆうこう) 登山家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

槇 有恒さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
槇有恒と関係のある人
板倉勝宣: また、同じ頃に新進気鋭の登山家が集まっていることで知られた慶應義塾大学山岳部と交遊を持ち、1922年8月にドイツに向かう鹿子木員信(慶応山岳部初代部長)の壮行を兼ねて、鹿子木や同部の精鋭である槇有恒・三田幸夫・大島亮吉・早川種三らと共に穂高連峰の岩登り合宿に参加している。 板倉勝宣: 1923年1月、立山(雄山)へ槇有恒、三田幸夫(2人とも後に日本山岳会会長に就任する)らとスキー登山を敢行した。 深田久弥: なお山房の扁額の揮毫は槇有恒、彫刻は佐藤久一朗による。 今西壽雄: 1956年、槇有恒率いる日本山岳会第三次マナスル登山隊に参加し、シェルパのギャルツェン・ノルブとともにマナスル世界初登頂に成功した。 鹿子木員信: 鹿子木の創設した慶應義塾大学山岳部からは槇有恒・三田幸夫・大島亮吉・早川種三ら著名な登山家を輩出した。 槇文彦: 伯父・槇有恒(登山家) 松方三郎: 1926年(大正15年)8月 - エンゲルヘルナー群峰の岩登りに槇有恒らとともに秩父宮雍仁親王に随伴。 |
槇有恒の情報まとめ

槇 有恒(まき ゆうこう)さんの誕生日は1894年2月5日です。宮城出身の登山家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 02:00更新
|
maki yuukou
槇有恒と同じ誕生日2月5日生まれ、同じ宮城出身の人
TOPニュース
槇有恒と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター