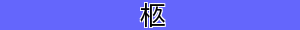柩の情報(ひつぎ) ミュージシャン 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

柩さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
柩と関係のある人
赤座美代子: 赤い霊柩車シリーズ 第34作「偽りの代償」(2014年) - 池部鈴子 高橋克彦: 『総門谷』『竜の柩』などのアクション伝奇小説(広義のSF)、『炎立つ』『火怨』などの歴史小説のほか、ホラー、ミステリー、時代小説など、幅広いジャンルで活躍する。 小沢象: 赤い霊柩車シリーズ 第12作「二度死んだ死体」(2000年) - 比良山新平 朝加真由美: 「赤い霊柩車シリーズ」(1996年) - 原田映子 棟里佳: 赤い霊柩車シリーズ16 (2002年)- 井上冬子 役 井上芳夫: 山村美紗サスペンス 赤い霊柩車(7)双子の棺 猫屋敷に横たわる2つの死体!!孤独な老婦人と数奇な運命に引き裂かれた双子の姉妹愛憎の再会 (1997) 塩田貞治: 山村美紗サスペンス 赤い霊柩車30(2012年9月28日・10月5日、フジテレビ系列) - 二条路信也役 山田麻衣子: 金曜プレステージ・赤い霊柩車(2011年) - 川嶋加代子 役 浅利香津代: 釈迦内柩唄(地人会)(金沢市民劇場主演女優賞・関西十三夜会賞受賞) 島かおり: 「赤い霊柩車シリーズ26 黒い同窓会」(2010年) - 河合治子 岡崎由紀子: 「山村美紗サスペンス赤い霊柩車34」 矢田亜希子: 山村美紗サスペンス 赤い霊柩車38(2020年4月3日、フジテレビ) - 静川佐和子 役 永井智雄: 第62話「散歩する霊柩車」(1960年) 楠木誠一郎: 『十二階の柩―明治を探検する』(1996年、講談社ノベルス) 奈良富士子: 赤い霊柩車シリーズ 第36作「惻隠の誤算」(2016年) - 朱雀尚美 岡まゆみ: 「赤い霊柩車シリーズ22」(2007年) - 岡田千枝 千葉一伸: シナプスの柩 I・II(海堂) 松木ひろし: 散歩する霊柩車(1964年) 脚本 小高恵美: 赤い霊柩車 「大江山鬼伝説殺人事件」(1998年) - 中田雪子 役 篠田三郎: 金曜プレミアム / 赤い霊柩車シリーズ36 惻隠の誤算(2016年、CX) - 朱雀正山 西崎莉麻: 探偵Xからの挑戦状! Season2 「嵐の柩島で誰が死ぬ」(2009年10月14日、NHK) 明治天皇: 霊柩は午後7時に殯宮を出て轜車に移された。前侍従長徳大寺実則、侍従北条氏恭、主馬頭藤波言忠らが衣冠帯剣素服で霊柩の綱を引いた。祭詞が奏された後、新天皇が玉座を離れ、霊柩に進んで拝礼し、桂太郎首相が捧げる御誄を取って読み上げた。明治天皇の柩は遺言に従い御霊柩列車に乗せられ、東海道本線等を経由して伏見桃山陵に移動、9月14日に埋葬された。 吉野真弓: 赤い霊柩車4 二つの墓標(1995年) 小六禮次郎: 山村美紗サスペンス 赤い霊柩車 第2作~第5作(1993年~1996年、フジテレビ) 内田康夫: 皇女の霊柩 (106) 村上聡美: 赤い霊柩車(9)・大江山鬼伝説殺人事件(1998年10月2日、金曜エンタテイメント) 川岡大次郎: 金曜プレステージ 赤い霊柩車27・魔女の囁き(2011年4月8日、フジテレビ) - 沢イサオ 役 金児憲史: 山村美紗サスペンス・赤い霊柩車シリーズ38「結婚ゲーム」(2020年4月3日) - 沢田圭一 岩本千春: 赤い霊柩車 代理妻殺人事件 (2007年10月5日) 倉田てつを: 赤い霊柩車シリーズ17 毎月の脅迫者(2003年6月13日、CX) - 石田陽一 |
柩の情報まとめ

柩(ひつぎ)さんの誕生日は1982年3月5日です。宮城出身のミュージシャンのようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2025/06/27 11:56更新
|
hitsugi
TOPニュース
柩と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】話題のアホネイター