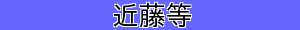近藤等の情報(こんどうひとし) フランス文学者 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

近藤 等さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
近藤等と関係のある人
豊住芳三郎: (1983年、DIW) ※with トリスタン・ホンシンガー、近藤等則、ペーター・コヴァルト 吉野大作: 神曲/吉野大作、近藤等則、石塚俊明、ロケット・マツ、金井太郎、坂本弘道、松井亜由美(1997) ハインリヒ=ハラー: 『チベットの七年』近藤等訳 新潮社 1955 植村直己: また、ガストン・レビュファ/著『星と嵐』(近藤等/訳)や、同じ兵庫県出身の加藤文太郎/著『単独行』を読み、感銘を受けた。 金子飛鳥: 近藤等則 富樫春生: 吉田美奈子バンド(のちにデュオ)や後藤次利バンドを経て1985年に近藤等則・IMAに参加。 近藤等則: 2014年(平成26年)、音楽ダウンロード販売サイト 近藤等則レコーディングス|Toshinori Kondo Recordings をスタートさせる。 芳野満彦: 川崎隆章,近藤等編『山岳講座.第1巻』(白水社,1954年) ハインリヒ=ハラー: 『石器時代への旅 秘境ニューギニアを探る』近藤等・植田重雄訳 新潮社 1964 近藤等則: 2014年(平成26年)、音楽ダウンロード販売サイト*近藤等則レコーディングス|Toshinori Kondo Recordingsをスタートさせる。 山木秀夫: 同年、近藤等則 & IMAに加入(1993年解散まで所属)。 土取利行: 近藤等則、坂本龍一、阿部薫、高木元輝、音楽評論家の間章らと音楽活動を展開。 古謝美佐子: 2005年には1991年に佐原一哉が江州音頭の桜川唯丸のために作詞作曲した「黒い雨」をシングルとしてリリース、黒田征太郎、近藤等則らのピカドン・プロジェクトの一環として制作されたCD絵本『ふたつの黒い雨』にも都はるみと共に参加した。 近藤等則: 1983年(昭和58年)には、バンド「Tibetan Blue Air Liquid Band」(後に「近藤等則 & IMA」に改名)を結成。 池津祥子: わたしが子どもだったころ(2008年) - 近藤等則の母 役 アンリ=トロワイヤ: 近藤等訳、白水社 1956年 寺山修司: イベント「冥土への手紙ー寺山修司生誕80年記念音楽祭」 - J・A・シーザー(演劇実験室◎万有引力)と悪魔の家2015、大槻ケンヂ、カルメン・マキ、近藤等則、SUGIZO(LUNA SEA, X JAPAN)、瀬間千恵、PANTA、山崎ハコ、犬神サアカス團、近藤等則、渚ようこ、新高けい子、元ちとせ、未唯mie、蘭妖子、ROLLY、他。 |
近藤等の情報まとめ

近藤 等(こんどう ひとし)さんの誕生日は1921年9月2日です。京都出身のフランス文学者のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 10:02更新
|
kondou hitoshi
近藤等と同じ誕生日9月2日生まれ、同じ京都出身の人
TOPニュース
近藤等と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター