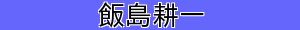飯島耕一の情報(いいじまこういち) 詩人 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

飯島 耕一さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
飯島耕一と関係のある人
辻征夫: 二十代の終わりに辻は、詩人の飯島耕一に会った際、雑談の折に「旅に出ると一度はどうしても、そういう一郭に足を踏み入れてみたくなります」といって、勘違いした飯島に「悪い病気にでも罹ると取り返しがつかないからやめた方がいい」とたしなめられたことがある。 安藤元雄: 飯島耕一の詩集『ゴヤのファーストネームは』(青土社)の装幀を担当する。 ギョーム=アポリネール: 第1巻:堀口大學訳「動物詩集 ― またはオルフェ様の供揃え」/ 飯島耕一、入沢康夫、窪田般彌訳「アルコール」/ 飯島耕一訳「カリグラム ― 平和と戦争の詩 (1913-1916)」/ 堀口大學訳「遺稿詩篇」 大岡信: 1957年(昭和32年)3月、清岡卓行、平林敏彦、飯島耕一らの詩誌『今日』に7号より参加。 マン=レイ: 『写真家 マン・レイ』飯島耕一訳、みすず書房、1983年 大岡信: 1959年(昭和34年)8月、 吉岡実・清岡卓行・飯島耕一・岩田宏らと「鰐」を結成。 石川喬司: 東京大学文学部仏文学科に進み、渡辺一夫や鈴木信太郎に師事し、飯島耕一や東野芳明、村松剛、栗田勇らと同人誌『カイエ』を作る。 大岡信: 栗田勇、飯島耕一、東野芳明らを知る。 安藤元雄: 外国語研究室で飯島耕一、渋沢孝輔を知り、少しずつ詩作を再開、発表先もひろがった。 ギョーム=アポリネール: 飯島耕一訳『アポリネール詩集』彌生書房(世界の詩45)1967年 アンリ=カルティエ=ブレッソン: 『カルティエ=ブレッソンのパリ』飯島耕一訳、みすず書房、1994年。 ギョーム=アポリネール: (鈴木信太郎、川口篤、佐藤朔、室井庸一、渡辺一民訳「異端教祖株式会社」、渡辺一民訳「キュービスムの画家たち」、福永武彦、村松剛、菅野昭正、渡辺一民訳「アルコール」、鈴木信太郎、山川篤、佐藤朔、菅野昭正、渡辺明正、渡辺一民、室井庸一訳「虐殺された詩人」、佐藤朔、窪田啓作、菅野昭正、飯島耕一、渡辺一民訳「カリグラム」、渡辺一民訳「波浪」、渡辺一民訳「軍旗」、佐藤朔訳「カーズ・ダルモン」、窪田啓作、渡辺一民訳「発射光」、飯島耕一訳「月の色の砲弾」、菅野昭正訳「星がたに傷ついた頭」、若林真「新精神と詩人たち」、清水徹訳「新しい詩人たち」、鈴木信太郎、渡辺一民訳「腐ってゆく魔術師」、白井浩司、阿部良雄訳「美術論集」、金子博訳「作家論集」)(目次・書誌情報) ギョーム=アポリネール: (訳詩のほか、滝田文彦「アポリネールの今日的意義」、湯浅博雄「アポリネールの現代性」、宇佐美斉「夢みられた自伝」、堀田郷弘「ルーへの手紙」、河盛好蔵「ミラボー橋界隈」、佐藤朔「アポリネールのシャンソン」、ジャン・モレ(フランス語版)、ジャン・コクトー、アントワーヌ・フォンガロのアポリネール論、飯島耕一、鈴木志郎康の対談「現代詩から見たアポリネール」) 池田満寿夫: 詩人との交際が増え、飯島耕一、西脇順三郎、鍵谷幸信、吉岡実、萩原葉子らを知る。 吉岡実: 飯島耕一「吉岡実の死」(「朝日新聞」1990年6月4日) ジャン=ジュネ: 飯島耕一「青海波――あるいは吉岡実をめぐる走り書」(「現代詩読本」1991年4月、思潮社) 加藤郁乎: 江戸俳諧にしひがし 飯島耕一共著 みすず書房, 2002 大岡信: 6月、江原順、飯島耕一、東野芳明らと共にシュルレアリスム研究会を設立。 ギョーム=アポリネール: 第3巻:宇佐美斉訳「坐る女 ― 現代の風俗と驚異の物語(フランスおよびアメリカ年代記)」/ 飯島耕一訳「一万一千の鞭(抄)」/ 窪田般彌訳「若きドン・ジュアンの手柄咄」/ 安東信也訳「ティレシアスの乳房 ― シュルレアリスム演劇」/ 釜山健訳「時の色 ― 韻文による三幕劇」/ 窪田般彌訳「カザノヴァ ― パロディ風喜劇」 ギョーム=アポリネール: 飯島耕一『アポリネール』美術出版社(美術選書)1966年(目次・書誌情報) 長谷川龍生: その後、万博の終幕と共に会社勤めを退き詩作に集中するようになるが、書き上げる詩は「(早くも戦後詩集の代表作ともなった)『パウロウの鶴』の自己模倣に過ぎない(飯島耕一)」と指摘されることもあり、苦難の日々が続いた。 菊池武一: 飯島耕一がゐた。 瀧口修造: 飯島耕一は、「瀧口修造の仕事は、言わば「ある大きな虚」に向かっての、小さな手仕事による燔祭であった。 安藤元雄: 作品論飯島耕一、詩人論新井豊美・和合亮一。 アンリ=ミショー: 『アジアにおける一野蛮人』(飯島耕一訳、筑摩書房) 1970、のち改訂(小海永二訳、弥生書房) 1983 ギョーム=アポリネール: 飯島耕一訳『一万一千の鞭』河出書房新社(河出文庫)1997年 東野芳明: 1956年、大岡信、飯島耕一らと共にシュルレアリスム研究会を設立。 吉岡実: 1956年2月下旬、偶然、飯島耕一に出会い、詩集『静物』(1955年8月刊行)を渡し、あまりにも反響がないので詩をやめようと思うと語ったが、飯島はそれはいけないと引き止めた。 アンリ=バルビュス: 『地獄』布施延雄訳、新潮社〈泰西最新文芸叢書〉1921年 / 小牧近江訳、新潮社『世界文学全集32』1929年、新潮社〈新潮文庫〉1953年、蒼樹社、1950年 / 井上勇訳、創藝社〈近代文庫〉1952年、創藝社〈創芸新書〉1955年 / 田辺貞之助訳、岩波書店〈岩波文庫〉1954年 / 飯島耕一訳、東西五月社、1961年 / 秋山晴夫訳、二見書房〈コレクション・アモール〉1968年、角川書店〈角川文庫〉1969年 / 菅野昭正訳、集英社『デュエット版 世界文学全集50』1970年 /『地獄物語』安島健編・抄訳、世界思潮研究会〈世界パンフレット通信〉1923年 吉岡実: 飯島耕一「青海波――あるいは吉岡実をめぐる走り書」(「現代詩読本」1991年4月、思潮社) |
飯島耕一の情報まとめ

飯島 耕一(いいじま こういち)さんの誕生日は1930年2月25日です。岡山出身の詩人のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/03 21:30更新
|
iijima kouichi
飯島耕一と同じ誕生日2月25日生まれ、同じ岡山出身の人
TOPニュース
飯島耕一と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター