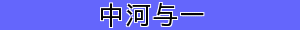中河与一の情報(なかがわよいち) 作家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

中河 与一さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
中河与一と関係のある人
中島健蔵: 中河与一ブラックリスト事件 山崎豊子: 山崎は、秘書が資料を集めた際に起った手違いであると弁明したが、その後さらに芹沢光治良『巴里夫人』や中河与一『天の夕顔』からの盗用も判明したため日本文芸家協会から退会した(1969年に再入会)。 川端康成: 湯ヶ島には、梶井の同人『青空』の面々(淀野隆三、外村繁、三好達治)、十一谷義三郎、藤沢桓夫、小野勇、保田与重郎、大塚金之助、日夏耿之介、岸田国士、林房雄、中河与一、若山牧水、鈴木信太郎、尾崎士郎、宇野千代、萩原朔太郎らも訪れた。 林房雄: 1937年(昭和12年) - 松本学・中河与一・佐藤春夫らと新日本文化の会を結成。 江川宇礼雄: 中河与一はのちに『続・探美の夜』(1958年)で二人のことを書いている(江川は実名、三千子は仮名)。 三島由紀夫: 戦時中に三島が属していた日本浪曼派の保田與重郎や佐藤春夫、その周辺の中河与一や林房雄らは、戦後に左翼文学者や日和見作家などから戦争協力の「戦犯文学者」として糾弾された。 三島由紀夫: 同年夏、蓮田善明が終戦時に自決していたことを初めて知らされた三島は、11月17日に清水文雄、中河与一、栗山理一、池田勉、桜井忠温、阿部六郎、今田哲夫と共に成城大学素心寮で「蓮田善明を偲ぶ会」を開き、〈古代の雪を愛でし 君はその身に古代を現じて雲隠れ玉ひしに われ近代に遺されて空しく 靉靆の雪を慕ひ その身は漠々たる 塵土に埋れんとす〉という詩を、亡き蓮田に献じた。 蒔田さくら子: 高瀬一誌らと中河幹子(小説家・中河与一の妻)に師事。 横光利一: 小田切秀雄は1946年6月、新日本文学会の機関誌『新日本文学』に「文学における戦争責任の追及」を発表し、そこで「菊池寛、久米正雄、中村武羅夫、高村光太郎、野口米次郎、西條八十、斎藤瀏、斎藤茂吉、岩田豊雄、火野葦平、横光利一、河上徹太郎、小林秀雄、亀井勝一郎、保田與重郎、林房雄、浅野晃、中河与一、尾崎士郎、佐藤春夫、武者小路実篤、戸川貞雄、吉川英治、藤田徳太郎、山田孝雄らは最大かつ直接的な戦争責任者である」と問いただし、「文学界からの公職罷免該当者である」と断定した。 大野芳: 1975年、岩手県遠野市でかっぱ伝承に触れ、中河与一を村長としてかっぱ村を設立した。 曽野綾子: 中河与一主宰の同人誌『ラマンチャ』(1951年5月)に載った「裾野」が臼井吉見の目にとまり、臼井の紹介で現在の夫・三浦朱門や阪田寛夫らの第十五次『新思潮』に加わる。 横光利一: 10月、川端康成とともに、今東光、中河与一、石浜金作、酒井真人、佐々木味津三、鈴木彦次郎、南幸夫ら文藝春秋同人と重なる新進作家を糾合して『文藝時代』を創刊する。 十返肇: 在学中から中河与一主宰「翰林」の同人となり、文芸時評を連載。 三島由紀夫: 以前、保田與重郎に謡曲の文体について質問した際に期待した浪漫主義的答えを得られなかった思いを「中世」に書き綴ることで、人工的な豪華な言語による絶望感に裏打ちされた終末観の美学の作品化に挑戦し、中河与一の厚意によって第1回と第2回の途中までを雑誌『文藝世紀』に発表した。 中島健蔵: 戦時中、作家の中河与一が、左翼的な文学者の「ブラックリスト」を警察に提出したという噂が戦後流れた。戦後の、戦争責任追及行為は、中島の戦争協力を隠すためだったとする見方が今では有力である(森下節『ひとりぽっちの闘い-中河与一の光と影』) 川端康成: 10月には、横光利一、片岡鉄兵、中河与一、佐佐木茂索、今東光ら14人で同人雑誌『文藝時代』を創刊し、さらに岸田国士ら5人も同人に加わった。 |
中河与一の情報まとめ

中河 与一(なかがわ よいち)さんの誕生日は1897年2月28日です。東京出身の作家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 18:31更新
|
nakagawa yoichi
中河与一と同じ誕生日2月28日生まれ、同じ東京出身の人
TOPニュース
中河与一と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター