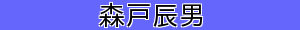森戸辰男の情報(もりとたつお) 社会学者、政治家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

森戸 辰男さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
森戸辰男と関係のある人
渡辺銕蔵: 大正9年(1920年)、同学部の助教授・森戸辰男が機関誌にクロポトキンの論文を掲載(森戸事件)。 岩下浩: 憲法はまだか(1996年) - 森戸辰男 鹿島信哉: 日本の青空(2007年) - 森戸辰男 内村鑑三: 岩永裕吉、金井清、川西実三、黒崎幸吉、沢田廉三、膳桂之助、高木八尺、田中耕太郎、田島道治、塚本虎二、鶴見祐輔、前田多門、三谷隆正、森戸辰男、藤井武らがメンバーになった。 幸徳秋水: 同年2月1日に、秋水に心酔していた第一高等学校の弁論部の河上丈太郎・森戸辰男の主催で「謀叛論」を講演したが、校長である新渡戸稲造らの譴責問題に発展し、校内で騒動となった。 大塚洋: NHKスペシャル「憲法70年“平和国家”はこうして生まれた」(2017年4月30日、NHK) - 森戸辰男 役 高野岩三郎: 弟子には森戸辰男、大内兵衛、舞出長五郎など、のちに著名となる多くのマルクス経済学者がいる。 徳冨蘆花: この講演を依頼した学生が、戦後に社会党委員長となる河上丈太郎や文部大臣となる森戸辰男だった。第二次大戦後、言論の自由が保障されてから田中耕太郎、森戸辰男が演説に言及した。 皇至道: 広島高等師範学校講師、広島文理科大学教授、広島大学教育学部教授、同教育学部長(連続5期)を経て、1963年(昭和38年)、森戸辰男の後を継ぎ、第2代学長に就任した。 高野岩三郎: 戦後、鈴木安蔵、森戸辰男、馬場恒吾らと憲法研究会を設立、「憲法草案要綱」発表。 長谷川如是閑: 東京帝大助教授であった森戸辰男が無政府主義者クロポトキンの研究によって起訴された1920年(大正9年)の森戸事件においては、学問の自由・研究の自由・大学の自治を主張して、同誌上で擁護の論陣を張った。 |
森戸辰男の情報まとめ

森戸 辰男(もりと たつお)さんの誕生日は1888年12月23日です。広島出身の社会学者、政治家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 10:21更新
|
morito tatsuo
森戸辰男と同じ誕生日12月23日生まれ、同じ広島出身の人
TOPニュース
森戸辰男と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター