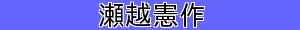瀬越憲作の情報(せごえけんさく) 囲碁 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

瀬越 憲作さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
瀬越憲作と関係のある人
岸信介: この会社は永野護がプロモートして広島県呉市に工場を建設した会社で、岸が会長、社長が足立正、取締役が永野、藤山愛一郎、津島寿一、三好英之、監査役瀬越憲作であった。 橋本宇太郎: 大阪府出身、瀬越憲作名誉九段門下。 賀屋興宣: 広島第一中学校では囲碁棋士の瀬越憲作と同級。 呉清源: 1928年10月18日 来日し、瀬越憲作名誉九段に入門。 呉清源: 敗戦後の1946年に師の瀬越憲作が日華親善のためとして薦めて、呉は中華民国籍としたが、これは連合国の中国(中華民国政権)代表団が呉の日本国籍取り消しを指示したとも、在日華僑により半強制的に手続きをとったとも言われる(夫人はこの時に無国籍状態となってしまっていた)。 菊池康郎: 『圍碁』誌 高段者二子局シリーズ(1952/4-53/2月号) 10-1(○宮下秀洋、○瀬越憲作、○雁金準一、○坂田栄男、○木谷實、○鈴木為次郎、○高川秀格、○橋本宇太郎、○岩本薫、×藤沢朋斎、○藤沢秀行) 杉内雅男: 1933年に小学校を卒業すると、瀬越憲作に入門を依頼し、瀬越門下の井上一郎四段(当時)の内弟子として、日本棋院院生となる。 梶原武雄: 木谷門下の多くの棋士に加え、瀬越憲作門下の曺薫鉉らも参加し、大いに影響を受けた。 柄本明: 呉清源〜極みの棋譜〜(2006年) - 瀬越憲作 橋本宇太郎: 久保松勝喜代八段門を経て、1920年に上京して方円社の瀬越憲作に入門し、1922年入段。 岩本薫: 1945年の東京大空襲による日本棋院焼失時には、自宅を仮事務所にするなどして、瀬越憲作らと日本棋院復興に尽力した。 前田陳爾: しかし戦後1948年の呉清源と本因坊薫和の十番碁の際、読売新聞紙上での瀬越憲作と加藤信の対談において、瀬越の「(あの160の手は)前田という男が考えた」という酒席での発言が掲載されてしまい、当時日本棋院理事長だった瀬越は理事長を辞任するという事件に至った。 本因坊秀哉: この頃には方円社の鈴木為次郎や瀬越憲作も秀哉に迫って来ていた。 本因坊秀哉: 大正初期の囲碁界は、本因坊門、方円社及び裨聖会(雁金準一、鈴木為次郎、瀬越憲作ら)との三派鼎立状態であった。 杉内雅男: 1800年代生まれの棋士(瀬越憲作など)、1900年代生まれの棋士(多数)、そして2000年代生まれの棋士(大西竜平)との対戦経験を持つ(将棋棋士では加藤一二三が同様の経験を持つ)。 岩本薫: 1961年に日本棋院理事でもあった永野護が、瀬越憲作、岩本らが、中央会館と別に「国際囲碁連盟」の設立を進めたが、伊予本桃市が、これへの日本棋院の協力に反対する。 前田陳爾: 大手合が東西対抗形式となった1927年の前期甲組で、初戦で瀬越憲作六段に勝ったのを始めとして6勝2敗で優勝して四段に進む。 呉清源: 呉が噂にたがわぬ腕を持つと分かると、訪中経験もある日本の棋士瀬越憲作と、呉を日本に呼ぶことが相談される。 呉清源: 中国福建省出身、日本棋院瀬越憲作名誉九段門下。 |
瀬越憲作の情報まとめ

瀬越 憲作(せごえ けんさく)さんの誕生日は1889年5月22日です。広島出身の囲碁棋士のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/06 16:52更新
|
segoe kensaku
瀬越憲作と同じ誕生日5月22日生まれ、同じ広島出身の人
TOPニュース
瀬越憲作と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】話題のアホネイター