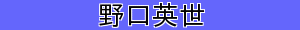野口英世の情報(のぐちひでよ) 医学者(細菌学) 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

野口 英世さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
野口英世と関係のある人
水野哲: 野口英世物語(19??)野口英世の少年時代役 藤野恒三郎: 野口英世記念会評議員 稲垣昭三: ヒューマン・ダイナモ 人間発動機 野口英世(2005年) 嶋崎伸夫: ヒューマン・ダイナモ〜人間発動機、野口英世 星里もちる: 週刊マンガ日本史第46号『野口英世』(2010年、朝日新聞出版) 二反長半: 『野口英世』(小学館、小学館の幼年文庫) 1956 川合将嗣: ヒューマン・ダイナモ 人間発動機 野口英世(2005年 紀伊国屋サザンシアター 東京ギンガ堂) 三浦謹之助: 野口英世、米国で会った。 光田健輔: 済生学舎の同期に野口英世がいる。 松岡依都美: 再びこの地を踏まず −異説・野口英世物語−(2018年9-10月 地方公演 演出:西川信廣)- メイジー 役 小柳洋子: 東京ギンガ堂公演 ヒューマン・ダイナモ 人間発動機 野口英世(2005年、紀伊国屋サザンシアター) 宮脇紀雄: 『野口英世』(偕成社、児童伝記全集) 1957 こわせたまみ: 『(伝記絵本ライブラリー)野口英世』(絵:かどたりつこ)ひさかたチャイルド、2006年 今井朋彦: 再びこの地を踏まず−異説・野口英世物語−(2015年11月 紀伊國屋サザンシアター他) - 野口英世 役 今井朋彦: 再びこの地を踏まず−異説・野口英世物語−(2019年9月-10月 地方公演) - 野口英世 役 ※再演 堀田あきお: 『野口英世』集英社 学習漫画・世界の伝記 1984年 村野守美: まんが少年野口英世(野口英世記念館 2004年10月) サイモン=フレクスナー: 1898年から1899年までジョンズ・ホプキンス大学病理学教授、1899年から1903年までペンシルベニア大学で病理学教授、1903年から1935年はロックフェラー医学研究所の初代所長を務め、野口英世と共に蛇毒を研究した。 原千果子: ゴースト・野口英世 浅野進治郎: 『野口英世の少年時代』 : 監督関川秀雄、製作・配給東映教育映画部、1956年2月25日公開 - 父佐代助、48尺で現存(NFC所蔵) 西村知道: VisaCM(野口英世) 中山茂: 「野口英世」(朝日新聞社〈朝日評伝選〉 1978、朝日選書 1989 オンデマンド版2005、岩波同時代ライブラリー(改訂版) 1995) 小林温: 野口英世の恩師・小林栄の親類筋にあたる。 高月清: 1983年 - 野口英世記念医学賞、武田医学賞 今井朋彦: 再びこの地を踏まず−異説・野口英世物語−(2018年9月-10月 地方公演) - 野口英世 役 ※再演 真木ひでと: 芸名は野口英世にあやかって野口ヒデトと名乗る。 福澤諭吉: 現在「最高額紙幣の人」としても知られているが、昭和59年(1984年)11月1日の新紙幣発行に際して、最初の大蔵省(現:財務省)理財局の案では、十万円札が聖徳太子、五万円札が野口英世、一万円札が福澤諭吉となる予定だった。 亀渕友香: 2008年には「第1回・野口英世アフリカ賞」の授賞式および記念晩餐会で、上皇明仁・上皇后美智子夫妻や歴代の内閣総理大臣、アフリカ各国の大統領や国王の前で演奏。 谷口維紹: 1985年 - 野口英世記念医学賞 小林健: 22「会津若松〜殺人無罪の乗客・チップでもらった野口英世の謎!? 女三人の愛憎が仕組む二つのえん罪!!」(2006年9月16日) |
野口英世の情報まとめ

野口 英世(のぐち ひでよ)さんの誕生日は1876年11月9日です。福島出身の医学者(細菌学)のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 21:18更新
|
noguchi hideyo
野口英世と同じ誕生日11月9日生まれ、同じ福島出身の人
TOPニュース
野口英世と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター