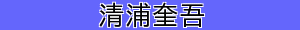清浦奎吾の情報(きようらけいご) 政治家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

清浦 奎吾さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
清浦奎吾と関係のある人
秦郁彦: 在学中は戦史や、清浦奎吾ら政治家の研究に没頭した。 大隈重信: 改革派は児玉源太郎、清浦奎吾、大浦兼武ら外部から党首を迎え、桂太郎首相に接近しようとする動きも見せていた。 芳川顕正: 続く第2次松方内閣では8日間の間留任し、清浦奎吾に跡を譲った。 原敬: 後継首相奏薦に当たる山縣に、側近の清浦奎吾は衆議院・貴族院・枢密院と良好な関係にある原しかいないと強く勧めた。 原敬: すでに2年近く首相を務めてきた原はこの辺りが引き時であると感じており、田中の辞職とともに総辞職し、後継首相には清浦奎吾を迎えることを考えていた。 山本権兵衛: 1922年(大正11年)の高橋内閣総辞職の際、元老の一人西園寺公望は病中であり、松方正義は、摂政宮裕仁親王(後の昭和天皇)より枢密院議長の清浦奎吾とともに山本を協議に加える許可を得た。 大麻唯男: 1924年(大正13年)、同郷の小橋一太(元文部大臣)の推挙により、清浦奎吾首相秘書官を務める。 徳川家達: 1924年(大正13年)1月、第2次山本内閣の総辞職後、後継首相となった元貴族院議員の清浦奎吾が貴族院の最大会派である研究会を中心とした組閣を行ったことで護憲三派などから「特権内閣」と批判された。 水野錬太郎: 1924年(大正13年)、清浦奎吾内閣が成立するとふたたび内相となり、帝都復興院総裁も兼任した。 山県有朋: 松方の推した徳川家達貴族院議長が拝辞した後、松方は山縣直系である清浦奎吾を推薦した。 平沼騏一郎: 辞職を希望する一木喜徳郎枢相が後任に平沼を推す一方、平沼派は一木枢相の後任に平沼でなく清浦奎吾を推していた(ただし清浦は西園寺とほぼ同世代で天皇機関説事件当時85歳)。 大倉喜八郎: 政界からは首相・田中義一を始め若槻禮次郎、浜口雄幸、床次竹二郎、清浦奎吾、関屋貞三郎など、実業界からは三井高棟(三井財閥)、岩崎小弥太(三菱財閥)、安田善三郎(安田財閥)、馬越恭平、浅野総一郎(浅野財閥)ら、国外からは張作霖、陳宝琛、段祺瑞、蔣介石などであった。 大隈重信: 山縣が次いで推薦した清浦奎吾が辞退に追い込まれた後(鰻香内閣)、元老会議は大隈しかいないという空気になった。 鈴木喜三郎: 司法官僚から、貴族院議員、清浦奎吾内閣の司法大臣、田中義一内閣の内務大臣を歴任し、衆議院議員から再度貴族院議員となった。 夏川結衣: 知られざる清浦奎吾の生涯 熊本初の総理大臣(九州地方限定放送、2000年) 西園寺公望: 山縣有朋の死後、牧野宮相や松方によるご下問の範囲を山本権兵衛や清浦奎吾に拡大し、元老を再生産しようという動きや、枢密院が諮問範囲に加わるように求める動きはあったが、西園寺はその動きを認めなかった。 山県有朋: しかしこれは山縣に無断で行われたものであり、山縣系の閣僚である清浦奎吾農商務大臣や寺内陸軍大臣にも伝えられていなかった。 平田東助: 陸軍および内務系官僚に広範な「山縣閥」を築いた山縣側近の中で、陸軍の側近が桂太郎・児玉源太郎・寺内正毅らとすれば、平田は清浦奎吾・田健治郎・大浦兼武らと並ぶ官僚系の山縣側近として人脈を形成した。 清浦夏実: 第23代内閣総理大臣・清浦奎吾の玄孫にあたる。 細川護煕: 熊本県出身の総理大臣は清浦奎吾以来69年ぶり。 原敬: 徳川家達・清浦奎吾といった候補者の内閣は成立せず、山縣と井上馨は大隈重信を奏薦した。 高橋是清: 政友会はその後も迷走し、清浦奎吾の超然内閣が出現した際には支持・不支持を巡って大分裂、脱党した床次竹二郎らは政友本党を結成し清浦の支持に回った。 加藤高明: 第二次護憲運動の高まりを受けた第15回衆議院議員総選挙で護憲三派勢力が圧勝したため、清浦奎吾首相は辞意を表明し清浦内閣は退陣、大命降下を受けた加藤は大正13年(1924年)6月11日、立憲政友会、憲政会、革新倶楽部からなる護憲三派内閣を率いる内閣総理大臣となった。 細川護熙: 熊本県出身の総理大臣は清浦奎吾以来69年ぶり。 平野龍一: 同郷(熊本県鹿本町来民)の内閣総理大臣清浦奎吾(内務官僚、検事、司法次官、司法大臣、総理大臣、戦前の刑事訴訟法策定)の影響を受け、刑事法研究の世界に入り、小野清一郎に師事する。 平田東助: 立憲政友会を与党とした第1次山本内閣がシーメンス事件のスキャンダルに見舞われた際には、茶話会は清浦奎吾率いる会派・研究会とともに、海軍予算7,000万円減を成立させ、3,000万円減の衆議院と対立。 西園寺公望: 12月29日、虎ノ門事件の責任を取って第2次山本内閣が総辞職すると、西園寺が主導権を握って清浦奎吾を後継首相に推薦した。 谷干城: しかし長期的な衰退は避けられず、山縣の側近平田東助・清浦奎吾がそれぞれ茶話会・研究会を押さえ両会派を連携させ、無所属団結成および無所属団と茶話会の大半を入れた幸倶楽部派と研究会の連携も成功すると懇話会・朝日倶楽部の劣勢が明らかになった。 山県有朋: 山縣はなおも婚約辞退にむけて動きを続けたが、山縣閥の有力者清浦奎吾枢密院副議長も久邇宮側に配慮する姿勢を見せ、原首相や元老たちも問題から距離を置くようになっていった。 山県有朋: 8月の第2次伊藤内閣総辞職後にできた第2次松方内閣は、大隈重信を外相とし、進歩党の支援も受けていたが、清浦奎吾法相をはじめとする山縣閥の官僚とその同調者が4人閣僚入りしている。 |
清浦奎吾の情報まとめ

清浦 奎吾(きようら けいご)さんの誕生日は1850年3月27日です。熊本出身の政治家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 03:27更新
|
kiyoura keigo
清浦奎吾と同じ誕生日3月27日生まれ、同じ熊本出身の人
TOPニュース
清浦奎吾と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】話題のアホネイター