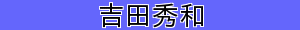吉田秀和の情報(よしだひでかず) 音楽評論家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

吉田 秀和さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
吉田秀和と関係のある人
磯村和英: また、2010年に水戸芸術館館長吉田秀和の命により、同館の専属楽団として、庄司紗矢香、佐藤俊介、石坂団十郎、小菅優らと、「新ダヴィッド同盟」を結成した。 大田黒元雄: 趣味は野球や相撲や推理小説など幅広く、著書の内容も音楽評論以外に『西洋の汽車』『野球春秋』『ネクタイ談義』『英米探偵小説案内』など多岐にわたり、食道楽としても知られ、吉田秀和から「大正リベラリズムが生んだひとつの典型。 スビャトスラフ=リヒテル: 音楽評論家の吉田秀和は彼のベートーヴェン演奏について、聴き手にベートーヴェンの時代のピアノでこれほどのダイナミクスの大きな演奏が可能だったのかと疑問を抱かせる一方で、ベートーヴェンの創造的想像力の中では確かにこうした響きが鳴っていたに違いないと感じさせる説得力があると述べている。 井口愛子: 1948年、同年に兄の井口基成、伊藤武雄、齋藤秀雄、吉田秀和らが開設した「子供のための音楽教室」で講師を務める。 大田黒元雄: 吉田秀和の随筆集『響きと鏡』の中には、吉田が園遊会のような席で、大田黒のことを英語で「日本で最初の音楽批評家」と紹介している場面が出てくる。 堀江敏幸: 吉田秀和賞(2023年- ) 一柳慧: 同年8月に大阪で行われた「二十世紀音楽研究所第4回現代音楽祭」を皮切りに、さまざまな演奏会でケージを代表とするアメリカの前衛音楽および自己の作品を紹介し、音楽評論家吉田秀和をして「ケージ・ショック」と言わしめるほどの衝撃を日本の音楽界に与えた。 ゲオルク=ショルティ: 音楽評論家の吉田秀和は、ショルティがウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮した交響曲第3番 (ベートーヴェン)の録音の第二楽章について、「こういう音楽を大真面目でやれるというには、何か一種の反知性的な気質か、さもなければ劇場的性格か、あるいは、そういうことを超越した本当に崇高なまでの精神的態度か、何かそういうものが要るのではなかろうか?そうして、ショルティには、この中で劇場的なもの theatrical な効果というものに対する本能が極度に強く発達しているのではなかろうか?」と述べ、次にリヒャルト・シュトラウスの『エレクトラ』の録音を挙げた上で「ショルティほどに、無慚な手つきでこういう響きを引き出している指揮者は、ほかに誰がいるのだろうか?」と、その劇的表現力を評している。 小澤征爾: 2013年4月1日、前年死去した吉田秀和の後任として水戸芸術館の2代目館長に就任。 井口基成: 1948年、伊藤武雄、齋藤秀雄、吉田秀和と「子供のための音楽教室」を開設。 池田満寿夫: 年長者では詩人・西脇順三郎、森鷗外の娘で作家の森茉莉、音楽評論家・吉田秀和らの名前が挙がる。 黛敏郎: これを仲介した吉田秀和が黛を紹介したことから、『金閣寺』が作曲されることとなった。 池田満寿夫: 土方巽、吉田秀和夫婦、白石かずこ、森茉莉、萩原葉子、澁澤龍彦、ジミー鈴木、西脇順三郎で、大半は1964年に制作された。 秋山邦晴: 1991年 第1回吉田秀和賞受賞(著書「エリック・サティ覚え書」により) 青柳いづみこ: 99年『翼のはえた指』で吉田秀和賞受賞、2001年『青柳瑞穂の生涯』で日本エッセイストクラブ賞受賞、09年『六本指のゴルトベルグ』で講談社エッセイ賞受賞。 武満徹: 1958年に行われた「20世紀音楽研究所」(吉田秀和所長、柴田南雄、入野義朗、諸井誠らのグループ)の作曲コンクールにおいて8つの弦楽器のための「ソン・カリグラフィI」(1958年)が入賞したことがきっかけとなり、1959年に同研究所に参加。 黛敏郎: 1957年、3月20日、音楽評論家・吉田秀和を所長に二十世紀音楽研究所を結成。 丸谷才一: 桐朋学園に教師として在籍したことがあるという経緯もあって、音楽評論家の吉田秀和の批評眼や、さまざまな業績と日本音楽会への貢献などを高く評価している。吉田秀和の『ソロモンの歌』『調和の幻想』『このディスクがいい*25選』などの書評を発表し、吉田の文化勲章を祝う会の祝辞で「彼は一時代を導いて、自分のものの考へ方と趣味を文明全体に、文明の重要な部分に浸透させた」と述べ、没時のコメントでは「戦後日本の音楽は吉田秀和の作品である。 小倉朗: このころから柴田南雄、入野義朗、吉田秀和、別宮貞雄、遠山一行らとの交友が始まる。 立花隆: 2016年(平成28年)、『武満徹・音楽創造への旅』で吉田秀和賞を受賞した。 |
吉田秀和の情報まとめ

吉田 秀和(よしだ ひでかず)さんの誕生日は1913年9月23日です。東京出身の音楽評論家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 13:15更新
|
yoshida hidekazu
吉田秀和と同じ誕生日9月23日生まれ、同じ東京出身の人
TOPニュース
吉田秀和と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター