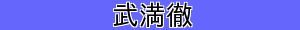武満徹の情報(たけみつとおる) 作曲家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

武満 徹さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
武満徹と関係のある人
ユーディ=メニューイン: 後年、武満徹が、アンドレイ・タルコフスキーの死を悼んで作曲した弦楽合奏曲『ノスタルジア』を絶賛し、自らこの曲を演奏した。 岩城宏之: 武満徹:『ノヴェンバー・ステップス』(琵琶:鶴田錦史、尺八:横山勝也) 大岡信: 同月、ニューヨークのカーネギー・ホールにて武満徹作『2本のヴァイオリンのための 揺れる鏡の夜明け』が演奏される。 大岡信: また、1962年(昭和37年)に武満徹の管弦楽曲のために「環礁」を書き下ろして以来、クラシック音楽の作曲家ともたびたび共作している。 立花隆: 2016年(平成28年)、『武満徹・音楽創造への旅』で吉田秀和賞を受賞した。 矢代秋雄: 團は矢代の死を翌日第1回日中文化交流協会音楽家代表団の一員(団長)として滞在中の北京で偶然知り、死因が作曲を続けながら芸大主任教授を務めていたことによる疲労であったこと、また、同じく代表団で同席していた武満徹が松村禎三に対し、「松村君、芸大なぞは辞めなさい。武満徹は矢代から芸大講師に就任を打診されたこともあるが、終生音楽学校での教鞭を執ることがなかった。 遠野なぎこ: 系図 -若い人たちのための音楽詩- (武満徹) - 語り手(1995年 日本初演) 黛敏郎: 1996年2月20日、武満徹の葬儀の際には、『MI・YO・TA』のメロディを何度も繰り返し歌った。 湯浅譲二: 詩人・瀧口修造を中心に集まった芸術家グループ・実験工房に加わり、武満徹らと共に活動し電子音楽や自作を含む現代音楽の演奏会の製作にかかわった。 小澤征爾: この時期は作曲家の武満徹と親交を大きく持ち、深い友情関係を築いた。 池辺晋一郎: 東京芸術大学在学中に書いた室内楽曲「クレパ七章」で注目され、武満徹の目に留まり、一時期映画音楽のアシスタントを務めた。 吉原幸子: 初期の劇団四季に入団、「江間幸子(えま さちこ)」の芸名で第6回公演のアヌイ作『愛の條件 オルフェとユリディス』(音楽・武満徹)にて主役を務めるも同年秋に退団。 大岡信: 同月、磯崎新、大江健三郎、武満徹、中村雄二郎、山口昌男らと編集同人となり、『季刊へるめす』創刊。 美輪明宏: 三島を歓喜させた当初のプラン通り、葵上では、舞台デザインにサルバドール・ダリと尾形光琳を取り入れ、音楽は、武満徹の『ノヴェンバー・ステップス』を取り入れ、99歳の老婆から19歳の美女への早替り(卒塔婆小町)など趣向を凝らした舞台となる。 佐藤勝: 黒澤作品の音楽で最もよく知られる「ドーン、ドーン」という打楽器の音は、元々佐藤が作ったものであるが、『影武者』の池辺晋一郎、『乱』の武満徹がティンパニのみで表現したのに対し、佐藤のそれは和太鼓を交えるものであり、作品世界に奥行きを与えるものに仕上がっている。 山口昌男: 1984年から1994年まで磯崎新、大江健三郎、大岡信、武満徹、中村雄二郎と共に学術季刊誌『へるめす』(途中から隔月刊、岩波書店)の編集同人として活躍した。 大竹伸朗: 10月、個展「10・08 武満徹『SONGS』+大竹伸朗」展(ナディッフ・ギャラリー、東京)。 中村紘子: 古典派およびロマン派中心ではあるが、矢代秋雄のピアノ協奏曲の初演を行った他、三善晃や武満徹といった日本の現代作曲家の作品も多く採り上げている。 ツトム・ヤマシタ: 武満徹 井沢満: 島へ(作曲:武満徹) 芥川也寸志: ポスト・ヴェーベルン的な点描様式と日本の間の美学が組み合わされ、その静謐な作品は武満徹に捧げられた。 コシミハル: 1995年、武満徹の作品を石川セリが歌ったアルバム『翼〜武満徹ポップ・ソングス』にアレンジと演奏で参加し、武満から「この人は天才だよ!」と絶賛された。 篠田正浩: 心中天網島 (1969年) 原作:近松門左衛門、脚本:富岡多恵子・武満徹・篠田正浩 五木寛之: 燃える秋(作曲:武満徹/歌:ハイ・ファイ・セット、1978年) 園田高弘: バッハやウィーン古典派などのレパートリーに加えて、リストやラフマニノフなどのヴィルトゥオーソ作品、シェーンベルクやスクリャービン、ジョリヴェなどのモダンな作品、くわえてリゲティやクセナキスのほか、武満徹、湯浅譲二、一柳慧、松村禎三らを含んだ現代音楽の4種類の演奏・解釈が課題として審査される。 山口勝弘: 大学卒業後の1951年秋、詩人・瀧口修造の下に集まった北代省三、武満徹(音楽家)らと共に、インターメディアの活動を目的とするアーティスト集団「実験工房」を結成した。 オーレル=ニコレ: 武満徹は遺作『エア』を70歳の誕生日を祝して書き、『ヴォイス』もニコレのために書かれた作品である。 湯浅譲二: 裸体(1962年、成沢昌茂監督)※武満徹と共作 富岡多恵子: 1969年、映画シナリオ『心中天網島』でシナリオ賞秀作賞受賞(篠田正浩、武満徹との共作) 中村雄二郎: 1984年から1994年まで「へるめす」(岩波書店)で磯崎新、大江健三郎、大岡信、武満徹、山口昌男とともに編集同人として活躍し、その思想は『かたちのオディッセイ』や『悪の哲学ノート』に結実した。 |
武満徹の情報まとめ

武満 徹(たけみつ とおる)さんの誕生日は1930年10月8日です。東京出身の作曲家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 01:04更新
|
takemitsu tooru
武満徹と同じ誕生日10月8日生まれ、同じ東京出身の人
TOPニュース
武満徹と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】話題のアホネイター