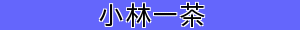小林一茶の情報(こばやしいっさ) 俳人(俳句) 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

小林 一茶さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
小林一茶と関係のある人
童門冬二: 『小林一茶』毎日新聞社 1998 のち人物文庫 宗左近: 『小林一茶』集英社新書 2000 三田和代: 小林一茶(1990年、こまつ座 作:井上ひさし 演出:木村光一) 熊谷健太郎: 茜さすセカイでキミと詠う(小林一茶) キムラ緑子: 小林一茶(2005年) - 第12回読売演劇大賞 優秀女優賞受賞 杉田智和: ねこねこ日本史(2016年 - 2021年、斎藤一、後白河法皇、高橋至時、長尾晴景、平国香、小林一茶、松平定信、龍造寺剛忠) - 4シリーズ 里中茶美: 「茶美」という名前は本名で父・辺土名求が小林一茶を好きだったことから「チャーミング」な子になるようにとつけられた、そんな茶美の兄弟には全員「茶」の文字が付いている。 矢崎滋: 浅利慶太演出の『ブラックコメディ』で主演もするが、74年フリーとなり、井上ひさしの『小林一茶』などに主演して注目され、1987年東京芝居倶楽部を設立し座長、福山大学客員教授として演技・演出論を担当。 宮脇紀雄: 『ものがたり小林一茶』(偕成社、児童伝記全集) 1967.2 二見忠男: 小林一茶 田辺聖子: また古典文学の流れから歴史小説にも活躍の場を広げ、同じ大阪出身の歴史小説家である司馬遼太郎とも親睦を結んでいるほか、自身も江戸時代の俳諧師・小林一茶の生涯を描いた『ひねくれ一茶』で吉川英治文学賞を受賞している。 矢代静一: つくづく赤い風車 小林一茶を題材にした作品。 洞口依子: 「おらが春~小林一茶」(NHK総合) 石田ゆり子: NHK正月時代劇・おらが春〜小林一茶(2002年1月1日、NHK総合) 菅沼赫: 小林一茶 田口主将: NHK正月時代劇「おらが春 ~小林一茶~」(2002年1月1日) 荻原井泉水: 父の終焉日記 一茶遺稿/ 小林一茶 岩波文庫 1934 矢崎滋: 小林一茶(1979年、作:井上ひさし)主演 北村有起哉: 小林一茶(2005年、こまつ座) 金子兜太: 小林一茶、種田山頭火の研究家としても知られる。 雨宮陽平: 2011年7月3日、2012年2月2日に放送された『キョクタ→ン』(TBS) では歴史好きを公言し、歴史上の偉人たち(小林一茶、夏目漱石、森鷗外、徳川家康、源義経、一休宗純、ハンス・クリスチャン・アンデルセン、アイザック・ニュートン他)にも同様の歌を捧げた。 かたせ梨乃: NHK正月時代劇「おらが春〜小林一茶〜」(2002年1月3日) おにぎり: 文化元年(1804年、江戸時代中期) - 小林一茶が俳諧集『文化句帖』を刊行。 藤貴子: おらが春〜小林一茶〜(2001年) 石井一孝: こまつ座第108回公演「小林一茶」(2015年) - 竹里 役 ふくまつ進紗: 小林一茶 柳澤壽男: 亀井文夫監督の『小林一茶』を見て、ドキュメンタリー映画への道を志すことになり、1942年に松竹を退社した。 嶋岡晨: 『小林一茶 物語と史蹟をたずねて』成美堂出版 1986 のち文庫 真下五一: 『小林一茶』春陽文庫 1973 永江智明: 小林一茶(2005) - 立花屋源七 |
小林一茶の情報まとめ

小林 一茶(こばやし いっさ)さんの誕生日は1763年6月15日です。長野出身の俳人(俳句)のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 15:20更新
|
kobayashi issa
小林一茶と同じ誕生日6月15日生まれ、同じ長野出身の人
TOPニュース
小林一茶と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター