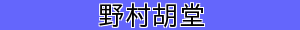野村胡堂の情報(のむらこどう) 作家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

野村 胡堂さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
野村胡堂と関係のある人
中一弥: 山本周五郎、藤沢周平、海音寺潮五郎、池波正太郎、山手樹一郎、野村胡堂などの作品、主に時代小説の挿絵画家として多くの作品を残す。 小中陽太郎: 2013年、『翔べよ源内』で第1回野村胡堂文学賞を受賞。 塚本靑史: 2014年8月、『サテライト三国志』で第2回野村胡堂文学賞受賞。 米内光政: 東京の料亭で開かれた盛岡尋常中学校時代の恩師・冨田小一郎への謝恩会も両大臣の呼びかけで行われたもので、他にも作家の野村胡堂、言語学者の金田一京助など、冨田の教え子たちが多く集った。 石川啄木: 短歌の会「白羊会」を結成したのもこの年である(メンバーに先輩の野村長一(後の野村胡堂)や後輩の岡山儀七がいた)。 金田一京助: 同窓生に及川古志郎や野村胡堂がいる。 津田健次郎: 啄木鳥探偵處(野村胡堂) 石ノ森章太郎: なお、テレビ原作者(アニメ・実写)としてのクレジットは放映期間のべ六十数年分に及び、野村胡堂、長谷川町子らを凌駕して国内最高で、2020年現在も更新し続けている。 徳川家達: 野村胡堂が贔屓の力士がいないように思えるとたずねたところ、好きな力士はいるが「家来や側近の者たちに、差別的な顔を見せてはならぬ。 板垣征四郎: 盛岡中学では三級上に米内光政、一級上に金田一京助や及川古志郎、野村胡堂などが、一級下には石川啄木がいた。 陣出達朗: 初代会長は野村胡堂。 神谷美恵子: 父 多門は後述の野村胡堂と共にソニーの前身である東京通信工業に出資しており、名誉職であるが初代社長を務めた。 比佐芳武: 同年、マキノとともに日活に入社、ひきつづきマキノとのコンビで野村胡堂原作の『七人の花嫁』の脚本を書き、荒井良平らにも脚本を提供したが、マキノの日活馘首後は、1934年(昭和9年)、嵐寛寿郎プロダクションに移籍した。 佐々木たづ: 1956年(昭和31年)、童話作家を志し、伯母の知り合いであった野村胡堂の指導を受ける。 神谷美恵子: 一彦は『銭形平次捕物控』の作者として知られる野村胡堂の長男であり、野村家と前田家は一家ぐるみで交際をしていた。 福士秀樹: 「銭形平次捕物控 / 闇夜の暗殺」野村胡堂(1998年12月31日、ホテルニューオータニお正月プラン イベント / 東映事業部) 夏川椎菜: 朗読付き電子書籍レーベル YOMIBITO 『流行作家の死』(野村胡堂)(2022年) 若桜木虔: 鳴神響一 (角川春樹小説賞と野村胡堂文学賞を受賞) 石山透: 大岡政談 池田大助捕物帳 (野村胡堂原作。 田坂勝彦: 1955 銭形平次捕物控 どくろ駕籠 野村胡堂原作 木俣清史: 中期の主な作品の一つは野村胡堂の代表的人気作品『銭形平次捕物控』初期の初版挿絵。野村胡堂の作品と人柄をのこした岩手のあらえびす記念館にも一部作品を寄贈している。 木村直巳: 銭形平次捕物控(原作:野村胡堂、漫画時代劇、ガイドワークス2017年8月20日発行~2023年5月8日発売号) 中澤まさとも: 野村胡堂「銭形平次捕り物控」(百助) 荻昌弘: 最初の妻の松田瓊子は野村胡堂の次女。 神保朋世: また、1926年、国民新聞連載の講談の挿絵など各種新聞の挿絵も描いており、第二次世界大戦戦前の1931年から『オール読物』において連載が開始されていた野村胡堂の「銭形平次捕物控」では、著者の胡堂が逝去するまで30年に亘って挿絵を描き続けた。 |
野村胡堂の情報まとめ

野村 胡堂(のむら こどう)さんの誕生日は1882年10月15日です。岩手出身の作家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2025/06/25 16:54更新
|
nomura kodou
野村胡堂と同じ誕生日10月15日生まれ、同じ岩手出身の人
TOPニュース
野村胡堂と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター