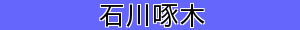石川啄木の情報(いしかわたくぼく) 歌人(短歌) 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

石川 啄木さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
石川啄木と関係のある人
田中正造: 正造の天皇直訴の当時、盛岡中学(現・岩手県立盛岡第一高等学校)の学生であった石川啄木は、天皇直訴の報を聞いて、「夕川に 葦は枯れたり 血にまどふ 民の叫びのなど悲しきや」と、その思いを三十一文字に託した。 坂西志保: 『一握の砂』(英訳)(石川啄木、読書展望社) 1947 与謝野鉄幹: 北原白秋、吉井勇、石川啄木などを見い出し、ロマン主義運動の中心的な役割を果たした。 長谷川海太郎: 中学3年頃から石川啄木に傾倒、白楊詩社という文芸グループに参加し作詩に励み、4年の時には野球の応援団長として活躍した。 西本鶏介: 石川啄木 さすらいの天才詩人 1985.7 (講談社火の鳥伝記文庫) 枡野浩一: 『石川くん』(絵:朝倉世界一、2001年11月、朝日出版社) 石川啄木の短歌を現代語に翻訳。 国広富之: 獅子のごとく(1978年、TBS)– 石川啄木 土岐善麿: 1910年(明治43年)に刊行した第一歌集『NAKIWARAI』の批評を、当時東京朝日新聞にいた石川啄木が執筆。 尾崎行雄: 別荘の「莫哀山荘」には、石川啄木や与謝野鉄幹・晶子夫妻が滞在したり、九条武子と柳原白蓮が訪れお茶会を催したり、また駐日米国大使のジョセフ・グルーに別荘を貸し出したりした。 花上晃: 新しき明日 石川啄木(1965年5月13日、NET) 杉村楚人冠: 明治期の旧制中学校では生徒のストライキは珍しくなく、石川啄木も教員排斥のストライキを首謀して中学を退学している。 岡本健一: 妻をめとらば -晶子と鉄幹-(2006年6月2日 - 26日、新歌舞伎座 / 2006年7月1日 - 25日、御園座) - 石川啄木 役 斎藤茂吉: 1909年(明治42年):森鴎外の観潮楼歌会に初めて出席、与謝野鉄幹、北原白秋、石川啄木、上田敏、佐佐木信綱などの歌人を知る。 友木りえこ: 呼子と口笛(著者:石川啄木) 藤沢幾之輔: 石川啄木の歌集『悲しき玩具』に収められている「藤沢といふ代議士を/弟のごとく思ひて、/泣いてやりしかな。 佐藤春夫: 和歌山県立新宮中学校(現・和歌山県立新宮高等学校)在学中、佐藤潮鳴の筆名で校友会誌に「おらば籠」、1908年(明治41年)には『熊野実業新聞』に短歌6首掲載、『明星』に「風」の題で投稿し短歌が石川啄木の選に入り、和貝彦太郎主宰の「はまふゆ」の同人となり、「馬車・食堂」(短歌・詩)を発表。 若山牧水: 1912年(明治45年)友人であった石川啄木の臨終に立ち合う。 金田一京助: もともと岩城は京助の著書『石川啄木』に影響を受けて研究を志し、最初の私家版の論文を京助に送って交友が始まった。 上田庄三郎: 『青年教師石川啄木』国土社、1992年11月。 小林研一郎: 小学5年生の時には、石川啄木の短歌「東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹とたはむる」によるピアノ伴奏付きの歌曲を作曲するほどの腕前になる。 板垣征四郎: 盛岡中学では三級上に米内光政、一級上に金田一京助や及川古志郎、野村胡堂などが、一級下には石川啄木がいた。 飯田三郎: 石川啄木歌曲集 原ひさ子: 特に、現代劇『石川啄木』では啄木の妻役で出演し、好評を博し当り役とした。 平田満: 内田洋一 (2011年10月18日). “シス・カンパニー「泣き虫なまいき石川啄木」作者井上ひさしとの苦悩の二重唱”. 三富朽葉: 佐藤義亮 編『石川啄木集・山村暮鳥集・三富朽葉集』新潮社〈現代詩人全集 第6巻〉、1929年8月。 津田仙: 長女の智恵子は函館の尋常高等小学校訓導時代に同僚の石川啄木から恋愛感情を持たれていたとされ、果樹園跡地に啄木の歌碑が建つ。 平井康三郎: ふるさとの(石川啄木) 坂西志保: 『A Handfel of Sand』(出版社:M.Jones) 1934年(昭和9) - 石川啄木「一握の砂」の英訳 小田嶽夫: 『石川啄木』(鶴書房、1967年) 須藤晃: 自ら少年時代は石川啄木や寺山修司に憧れて詩人志望であったと語る通り文学、特に詩の分野に関しての造詣が深く、言葉(歌詞)にこだわったプロデューススタイルでメッセージ性の強い作品を生み出している。 |
石川啄木の情報まとめ

石川 啄木(いしかわ たくぼく)さんの誕生日は1886年2月20日です。岩手出身の歌人(短歌)のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/06 12:31更新
|
ishikawa takuboku
石川啄木と同じ誕生日2月20日生まれ、同じ岩手出身の人
TOPニュース
石川啄木と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター