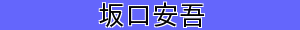坂口安吾の情報(さかぐちあんご) 作家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

坂口 安吾さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
坂口安吾と関係のある人
出口裕弘: 『坂口安吾 百歳の異端児』(新潮社) 2006 小栗虫太郎: 一方で、探偵小説の本格性を重視しペダントリーを嫌った坂口安吾は、S・S・ヴァン・ダインの亜流として作風自体を否定している。 西部邁: 西部が高く評価している日本人は山本常朝、福澤諭吉、中江兆民、夏目漱石、田中美知太郎、坂口安吾、秋野不矩、秦野章、福田恆存、三島由紀夫、色川武大、立川談志、唐牛健太郎などである。 福山潤: 文豪ストレイドッグス(2016年 - 2023年、坂口安吾) - 4シリーズ 佐々木久子: またおなじころ、前年1955年2月に小説家であり夫の坂口安吾を亡くし、1956年早々に東京・銀座で文壇バー「クラクラ」を開いたばかりの坂口三千代に、『クラクラ日記』の執筆を勧めたのも佐々木であった。 坂口綱男: 群馬県桐生市において、無頼派作家 坂口安吾と三千代の長男として生まれる。 林忠彦: 特に文士を撮影したものは有名で、銀座のバー「ルパン」で知り合った織田作之助・太宰治・坂口安吾の酒場での姿や、坂口安吾の紙屑に囲まれた仕事場の風景は、林忠彦の名を世に知らしめた。 新木宏典: 舞台 文豪ストレイドッグス - 坂口安吾 役 林房雄: 1947年(昭和22年) - 「小説時評」で坂口安吾らを「新戯作派」と名付ける。 宇垣美里: 今まで読んだ本の中で自分の原点に最も近いものとして坂口安吾の『堕落論』、山田詠美の『風葬の教室』の2冊を挙げている。 織田作之助: 戦後、太宰治、坂口安吾、石川淳らと共に無頼派、新戯作派と呼ばれ「織田作(おださく)」の愛称で親しまれる。 織田作之助: 坂口安吾の「反スタイルの記」では、ヒロポンを常用していた様子が描写されている。 田中和将: 自身が好きな作家に坂口安吾や安部公房、阿佐田哲也の名を挙げている。 趣里: 日本文学シアター Vol.6【坂口安吾】「風博士」(2019年12月、世田谷パブリックシアター/ 2020年1月、大阪 森ノ宮ピロティホール) 川原一馬: ミュージカル 走れメロス(2012年9月、Bunkamuraオーチャードホール 他) - 坂口安吾 役 石川淳: 『現代日本小説大系別冊1 戦後篇1 坂口安吾、太宰治、織田作之助、石川淳』河出書房 1950 出口裕弘: 2007年、『坂口安吾 百歳の異端児』で伊藤整文学賞、蓮如賞を受賞。 中田譲治: 高校生の頃は根暗であり、人とコミュニケーションを取ることに苦手意識があり、アルチュール・ランボー、坂口安吾を愛読しているような学生だった。 近藤ようこ: 2007年には坂口安吾の説話体小説「夜長姫と耳男」を漫画化、続いて2008年に同作者の「桜の森の満開の下」を漫画化し、2012年には安吾の「戦争と一人の女」の漫画化を6年がかりで描き下ろした。 壇一雄: 1948年(昭和23年)に太宰が自殺した後は坂口安吾とも交流をもつ。 福士秀樹: 「白痴」坂口安吾 安岡章太郎: 第25回芥川賞の選考では、岸田國士や坂口安吾など安岡の「ガラスの靴」を評価する選考委員もいたが、佐藤春夫や瀧井孝作は一作だけではまだ評価できないとし、授賞には至らなかった。 北村総一朗: 2017年には初の舞台演出に取り組み、新藤兼人監督の映画『ふくろう』の舞台版を、翌2018年には坂口安吾とその妻・三千代をモデルにした『改訂版 無頼の女房』を演出した。 斎藤十一: 同人誌を読んで無名の新人作家を発掘し続けた反面、坂口安吾や佐藤春夫といった大作家の原稿も気に入らなければ没にする、連載を打ち切ることで知られ、共にクラシック音楽を愛好し親交の深かった小林秀雄からは「斎藤さんは天才だ。 坂口綱男: ^ 坂口安吾デジタルミュージアム 2020年3月15日閲覧。 石川淳: 『現代日本文学全集 石川淳・坂口安吾・太宰治集』筑摩書房 1954 織田作之助: 1941年8月には内閣情報局により風俗壊乱の恐れのある小説の一つとして『青春の逆説』が発禁処分(当時は発禁対象小説の題名は秘匿されていた)を受けたが、当時の世俗を活写した短編「世相」を発表するなど、太宰治、坂口安吾、石川淳らと共に新戯作派(無頼派)として活躍し、「オダサク」の愛称で親しまれた。 牧野信一: なお、牧野信一は、坂口安吾の『風博士』をいち早く絶賛し、坂口が新進作家として世に出るきっかけを作った他、宇野浩二、井伏鱒二、青山二郎、小林秀雄、河上徹太郎らと交流を持ち、雑誌『文科』を創刊主宰して、これらの作家の作品発表の場を作った。 天願大介: カンゾー先生(1998年) 脚色 原作:坂口安吾 監督・脚色:今村昌平 又吉直樹: 好きな作家として、太宰治、京極夏彦、坂口安吾、芥川龍之介、古井由吉、中村文則、田丸雅智等を挙げている。 |
坂口安吾の情報まとめ

坂口 安吾(さかぐち あんご)さんの誕生日は1906年10月20日です。新潟出身の作家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 07:17更新
|
sakaguchi ango
坂口安吾と同じ誕生日10月20日生まれ、同じ新潟出身の人
TOPニュース
坂口安吾と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター