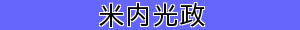米内光政の情報(よないみつまさ) 軍人 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

米内 光政さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
米内光政と関係のある人
阿南惟幾: 米内内閣は首相米内光政の方針により日独伊三国同盟の締結には反対であったが、陸軍内で日に日に高まる同盟推進論に「人の和」を重視する阿南と沢田も抗しきれず、7月8日に内大臣木戸幸一に、陸軍は日独伊三国同盟を推進するため、近衛文麿を首班とする内閣を要望していることを伝えて、沢田、武藤と図って陸軍大臣の畑俊六大将に辞職を進言した。 山本五十六: 総理大臣・岡田啓介の救出にも米内光政と共に関わった。 緒方竹虎: また緒方は、蔣介石の重慶国民政府を相手とする和平工作(繆斌工作)を首相・小磯國昭とともに推進したが、外務大臣・重光葵、陸軍大臣・杉山元、海軍大臣・米内光政、さらに昭和天皇の反対に遭い失敗、内閣総辞職となった。 中村育二: 日本のいちばん長い日(2015年、原田眞人監督、松竹) - 米内光政 役 松野鶴平: 政友会では鳩山一郎派に所属し、内務政務次官、政友会幹事長、米内光政内閣の鉄道大臣などを歴任した。 大角岑生: 横須賀鎮守府でも、留守の長官・米内光政に代わって参謀長・井上成美が陸戦隊の編制を命じ、戻った米内も後押しして東京突入の準備が早々に完了した。 東久邇宮稔彦王: また海軍大臣には元首相の米内光政が留任した。 白鳥敏夫: 内閣秘書官長の風見章は白鳥を大臣にすることに同意していたが、海軍大臣の米内光政はこれに強く反対した。 山村聰: 激動の昭和史 軍閥(1970年) - 米内光政 武見太郎: 翌年には、研究活動の傍ら東京・銀座の教文館ビルに武見診療所を開業し、開業医として生計を立てながら政財界の要人とも交わるようになり、吉田茂に指示されて、高血圧症を患っていた米内光政を往診したこともあった。 岸信介: 宮中の重臣間では、木戸幸一内大臣を中心に早期和平を望む声が上がり、木戸と岡田啓介予備役海軍大将、米内光政海軍大将らを中心に、東條内閣の倒閣工作が密かに進められた。 近衛文麿: たまりかねた海相・米内光政が「だいたい、永定河と保定の間あたりで作戦を中止することになっているようである」と口をはさんだ。 鈴木貫太郎: こうした状況で、木戸幸一と米内光政の働きかけにより、6月22日の御前会議でソ連に米英との講和の仲介を働きかけることが決定された。 風見章: 風見と米内光政とはとても親しい間柄でさかんに行き来や文通をしていた。 板垣征四郎: 天皇が「関係大臣との連絡はどうか」と問うと板垣は、宇垣一成外相も米内光政海相も賛成であると答えた。 柄本明: 聯合艦隊司令長官 山本五十六(2011年) - 米内光政 金田一京助: 同じように朝稽古に来ていたのが2年上級の米内光政で、2人で柔道の稽古をするようになった。 末次信正: 1937年(昭和12年)2月の林内閣成立時、末次は林銑十郎から海軍大臣就任の要請を受け了承したが、海軍人事に影響力があった伏見宮博恭王の信頼を失っており、海軍大臣・永野修身は海軍次官・山本五十六が推した米内光政を後任に選ぶ。 小磯国昭: 後任を決める重臣会議では、南方軍総司令官の寺内寿一、朝鮮総督の小磯、支那派遣軍司令官の畑俊六の3人に候補が絞られるが、前線指揮官の寺内を呼び戻すことに東条が反対、畑についても重臣の多くが反対し、米内光政、平沼騏一郎らの推す小磯に落ち着いた。 梅津美治郎: その一方、5月11日から開催された最初の最高戦争指導会議構成員会合では、海軍大臣の米内光政が「対ソ工作も結局するところ米英との仲介の労を取らせて大東亜戦争を終結することに最後はなると思うが」と発言した際に「その通りだ」と返答したり、6月9日に昭和天皇に関東軍の視察報告を上奏した際に「兵力が8個師団分しかなく、弾薬は大会戦の一回分しかない」と伝えるなど、戦争の継続に対して懐疑的な態度を見せたこともあった。 若槻礼次郎: 1948年10月 - 東京裁判のジョセフ・キーナン首席検事に宇垣一成、岡田啓介、米内光政と共に招待される。 近衛文麿: 平沼の後は陸軍出身の阿部信行と海軍出身の米内光政がそれぞれ短期間政権を担当した。 岡田啓介: 若槻禮次郎、近衛文麿、米内光政、またかつては政治的に対立していた平沼騏一郎といった重臣達が岡田を中心に反東條で提携しはじめる。 東郷平八郎: 岡田啓介、米内光政、山本五十六なども、東郷の神格化については否定的な態度をとっている。 迫水久常: 事前に平沼がポツダム宣言受諾に傾いているという情報を得ていた迫水は従来の6人の参加者から議長役で発言権のない鈴木総理を除いた5人の意見が受諾反対3(阿南陸相、梅津総長、豊田総長):受諾賛成2(東郷茂徳外相、米内光政海軍大臣)に分かれ、そこに受諾賛成の平沼の1票を加えて3:3の膠着状態に持ち込みその状況打開のために鈴木総理が昭和天皇に聖断を促すという筋書きを練り、御前会議の決定を枢密院に諮る手間と時間の省略を名目に平沼をメンバーに加えたのだ。 高松宮宣仁: 開戦後も宣仁親王は和平を唱え、嶋田海相の辞任や東條内閣の総辞職を度々主張し、後の終戦後史上唯一の皇族の総理となる東久邇宮稔彦王、弟・三笠宮崇仁親王等の和平派皇族や、米内光政元首相等をはじめとする海軍左派、近衛文麿前首相及び、首相を戦後に務める吉田茂等の政界の和平派と結んだ。 阿部牧郎: 『神の国に殉ず 小説東条英機と米内光政』祥伝社 2010 のち文庫 岡田啓介: さらにその直後、現役を退いていた和平派の米内光政を現役に戻し小磯内閣の海軍大臣として政治の表舞台に復活させ、終戦への地ならしを行った。 宇垣一成: 東京裁判を主導した主席検察官のキーナンは、米内光政・若槻礼次郎・岡田啓介と並んで宇垣を「ファシズムに抵抗した平和主義者」と呼び賞賛し、四人をパーティに招待し歓待している。 豊田穣: 『激流の孤舟 提督・米内光政の生涯』講談社 1978 のち文庫 |
米内光政の情報まとめ

米内 光政(よない みつまさ)さんの誕生日は1880年3月2日です。岩手出身の軍人のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 18:07更新
|
yonai mitsumasa
米内光政と同じ誕生日3月2日生まれ、同じ岩手出身の人
TOPニュース
米内光政と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】話題のアホネイター