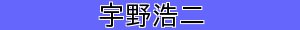宇野浩二の情報(うのこうじ) 作家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

宇野 浩二さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
宇野浩二と関係のある人
三富朽葉: 大学の同期には宇野浩二・廣津和郎がいる。 三上於菟吉: 1912年同級の宇野浩二らと同人誌『しれねえ』を創刊するが、三上の「薤露歌」が風俗壊乱として発禁になり、1号で終刊する。 梶井基次郎: この頃、初恋の思い出の草稿を宇野浩二の『蔵の中』に影響された饒舌体で書き、草稿「犬を売る男」や「病気」を原稿用紙にまとめ直そうとしていたと推定されている。 稲垣足穂: 宇野浩二は「新鮮な特異な物語」と評し、星新一は「星をひろった話」について「ひとつの独特の小宇宙が形成」された「感性による詩の世界」と述べている。 中島敦: 同作品は石塚友二(横光利一の弟子)の「松風」とともに最後まで選考で争ったが、室生犀星と川端康成の2人の選考委員が高く評価したのみで、ほかの選考委員の宇野浩二などからの支持が得られず落選した(石塚の作品も)。 古川ロッパ: 谷崎潤一郎・宇野浩二・菊池寛・川口松太郎などの作家や歌舞伎・新派・演劇関係者・小林一三・森岩雄ら興業関係者、鈴木文史朗らマスコミ関係者・嘉納健治らの侠客とも幅広い交友関係を持っていた。 水上勉: 北海道の『大道』という雑誌に書いた自身の日常そのままを短編にした「雁の日」で宇野に褒められて発奮、ついで1948年に文潮社から長編の身辺小説『フライパンの歌』を刊行し、宇野浩二の序文や「昭和の貧乏物語」という文句の広告もあって良い売れ行きを示した。 水上勉: 考えたことは『誰を殺すか』ではなくて、『誰を生かさねばならぬか』ということのようであった」(『金閣と水俣』)と考えており、直木賞受賞を機に師の宇野浩二や中山義秀からも人間を書くようにと言われたことで、推理小説からは遠ざかるようになった。 水上勉: 紅の製造にかけた人々を描く『紅花物語』や、和紙の紙すきの人々を描く『弥陀の舞』を、村松定孝は「作者の詩魂の根底に和讃を誦すような衆生済度のねがいがこめられている」と評し、また日本の日本の日記文学・紀行文学の語りの面白さとして、谷崎潤一郎『吉野葛』宇野浩二『山恋い』などを受け継ぐ作家であり、「庶民の心を肌で感じとり、貧しく虐げられた社会の底辺にうごめく衆生の姿を如実に捉えている」水上が、「師(宇野浩二)の話術を学び取り同時に浩二の私小説特有の湿りを自作ににじみこませた物語文学の新分野を拓いた」と述べ、泉鏡花、谷崎潤一郎を受け継いで「見事に文学的開花を成し遂げた」「純文学にして大衆小説、私小説のしめりをきかせ、しかもロマンの骨格を有する」3人目の才豊かな作家ともしている。 水上勉: 禅寺を出奔して様々な職業を経ながら宇野浩二に師事、社会派推理小説で好評を博して、次第に純文学的色彩を深め、自伝的小説や女性の宿命的な悲しさを描いた作品で多くの読者を獲得。 安部公房: 「壁 - S・カルマ氏の犯罪」は1951年上半期の第25回芥川賞の候補となり、選考委員の宇野浩二からは酷評されたものの、川端康成と瀧井孝作の強い推挙が決め手となり、同じく候補に挙げられていた石川利光の『春の草』とともに受賞を果たす。 石野径一郎: この頃比嘉春潮に郷土史、宇野浩二、川端康成、青野季吉に小説を師事。 石川達三: 志賀直哉・宇野浩二・徳田秋声のような私小説には最初からはっきり異質感をもったという。 坂口安吾: この「風博士」を牧野信一から激賞、「黒谷村」も島崎藤村と宇野浩二にも認められ、一躍新進作家として文壇に注目された。 水上勉: 1968年、日本文芸家協会出版著作評議員、また『宇野浩二全集』(中央公論社)の編集委員を務める。 斎藤茂吉: また、文才に優れ、柿本人麻呂、源実朝らの研究書や、『ドナウ源流行』『念珠集』『童馬山房夜話』などのすぐれた随筆も残しており、その才能は宇野浩二、芥川龍之介に高く評価された。 ニコライ=ゴーゴリ: 芥川龍之介の『芋粥』は導入部分が『外套』に酷似しているほか、宇野浩二の饒舌体、後藤明生の『笑い地獄』『挟み撃ち』など、ゴーゴリの小説作法に学んだ作品が数多く存在する。 林房雄: 1933年(昭和8年) - 小林秀雄、武田麟太郎、川端康成、深田久弥、広津和郎、宇野浩二らと同人誌『文学界』を創刊。 川端康成: 10月には、小林秀雄、林房雄、武田麟太郎、深田久彌、宇野浩二、広津和郎、豊島与志雄らと文芸復興を目指した雑誌『文學界』創刊の同人となった。 水上勉: 1970年(昭和45年) - 第19回菊池寛賞(『宇野浩二伝』) 水上勉: この頃、信州松本に疎開中の宇野浩二に執筆依頼に行き、宇野がかつて「水上潔」の変名を使っていたことで知遇を得、宇野が東京本郷に移ってからも腱鞘炎を患っていた宇野の口述筆記を長く行なうようになって、文学の師と仰ぐようになり、『苦の世界』なども刊行する。 水上勉: 宇野浩二没後には、遺品の机を贈られている。 鈴木三重吉: しかし代作が多く、実際に執筆した作家として井伏鱒二、内田百閒、宇野浩二、宇野千代、上司小剣、小島政二郎、豊島与志雄、中村星湖、林芙美子、広津和郎、室生犀星らがいた。 安岡章太郎: 宇野浩二は「この二つの作品にも頸をひねる」「『陰気な愉しみ』は、すっと読めるが、たよりなさ過ぎ、『悪い仲間』は、『愛玩』よりずっと落ちる上に、趣向は面白いけれど、荷が勝ち過ぎているように思われる」と評した。 佐藤春夫: 4月に3年間に長篇を2作ずつ書く約束で、菊池寛、宇野浩二、里見弴と共に報知新聞社客員記者となり、中国へ旅行する。 芥川龍之介: 堀辰雄、宇野浩二、小沢碧童らの訪問を受ける。 二反長半: その後、寄稿していた少年雑誌の編集者の薦めで児童文学を手がけるようになり、1939年に川端・大宅・井伏鱒二・宇野浩二・小川未明・坪田譲治・豊島与志雄・村野四郎と少年文芸懇話会を結成。 牧野信一: 『随筆』の編集を通じ、宇野浩二、葛西善蔵、久保田万太郎らと知り合う。 葛西善蔵: 宇野浩二は、私小説について書いた文章「「私小説」私見」の中で、「日本人の書いたどんな優れた本格小説でも、葛西善蔵が心境小説で到達した位置まで行ってゐるものは一つもないと思はれる」といい、「小説も此高さ、此境地に迄立って見たなら、多くの他の小説は何等かの意味で通俗的だといへないだらうか」と、絶賛といってよい評価をしていた。 牧野信一: なお、牧野信一は、坂口安吾の『風博士』をいち早く絶賛し、坂口が新進作家として世に出るきっかけを作った他、宇野浩二、井伏鱒二、青山二郎、小林秀雄、河上徹太郎らと交流を持ち、雑誌『文科』を創刊主宰して、これらの作家の作品発表の場を作った。 |
宇野浩二の情報まとめ

宇野 浩二(うの こうじ)さんの誕生日は1891年7月26日です。福岡出身の作家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 18:15更新
|
uno kouji
宇野浩二と同じ誕生日7月26日生まれ、同じ福岡出身の人
TOPニュース
宇野浩二と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター