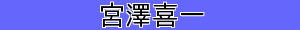宮澤喜一の情報(みやざわきいち) 政治家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

宮澤 喜一さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
宮澤喜一と関係のある人
熊谷弘: また「宮澤喜一財務相はアルツハイマーだ。 斎藤正彦: 宮澤喜一 服部安司: 党内では宏池会(池田勇人→前尾繁三郎→大平正芳→鈴木善幸→宮澤喜一派)に所属し、第2次池田内閣第1次改造内閣の内閣官房副長官などを歴任後、1977年、福田改造内閣の郵政大臣として初入閣。 吉川芳男: 1990年の衆院選で二階堂グループは解散状態に追い込まれるが、選挙翌日の同年2月19日、吉川の宏池会(宮澤喜一派)入りが内定した。 田沢吉郎: 自民党内では宏池会(池田勇人→前尾繁三郎→大平正芳→鈴木善幸→宮澤喜一派)に属し、衆議院議院運営委員長、国土庁長官、自民党国会対策委員長、農林水産大臣、防衛庁長官などを歴任。 中山太郎: 中曽根康弘、宮澤喜一両元首相が2003年(平成15年)に引退して以降、現職議員の中では最高齢になったため、衆議院本会議場の座席は主に歴代首相経験者が並ぶ位置に置かれるようになった。 前尾繁三郎: インドネシア出向中に知り合った宮澤喜一は、GHQと前尾の処遇を巡り交渉するが事態は変化せず、前尾に詫びるが前尾は気にする様子もなく局長室で好きな読書三昧の生活を送る。 中島衛: 宮澤改造内閣の発足に際しては、中島が金丸の直系であったため入閣の望みは薄かったが、金丸が宮澤喜一首相に対して中島の入閣を懇請したため、首相就任以来経世会を後ろ盾にしてきた宮澤首相はこれを受け入れ、羽田派から中島を科学技術庁長官に、船田元を経済企画庁長官に任命した。 田中秀征: 石田の政界引退決定後、宮澤喜一に師事したいと石田に報告すると、「宮澤も石橋湛山の信望者だ」と喜ばれる。 御厨貴: 『知と情――宮澤喜一と竹下登の政治観』(朝日新聞出版、2011年3月/ちくま文庫、2016年7月) 河野太郎: 当選後の河野太郎は自民党内ではしばらく無派閥で活動し、その後に麻生太郎の勧めで宮澤喜一が会長を務めていた宮澤派(宏池会)に所属した。 大屋政子: 高い声と年齢に合わないピンク色を基調とした派手な衣装を好み、高齢になってもなおミニスカートを愛用する等、日本国内では“色物タレント”として認知される傾向が強いが、フランスのフランソワ・ミッテラン大統領と電話したり、元日の『平成あっぱれテレビ』に出演した際に宮澤喜一のことを「喜一ちゃん」と呼んで電話を掛けたり出来る(ただしその時は宮澤は不在で繋がらなかった)ほどで、世界的には有名な“セレブ”であった。 中馬弘毅: 自民党では宏池会(宮澤喜一派)に入会。 増岡博之: 平成3年(1991年)、首相に就任した宮澤喜一は自派の増岡を党国会対策委員長に起用したが、増岡は国対の経験に乏しく野党とのパイプもなく、宮澤はPKO協力法案の成立と政治改革の実現を目指したがPKO協力法案は継続審議になり政治改革は進まなかった。 小川平二: 文相時代の1982年に歴史教科書問題が起き、中韓との外交関係を重視する首相官邸及び外務省サイドと、修正要求に応じることによる教科書検定制度の形骸化を危惧する文部省事務方との間で対応に苦慮しながら調整に務め、内閣官房長官宮澤喜一の談話で一応の事態収拾をみた。 藤尾正行: 内閣総理大臣・宮澤喜一は「中国の要請を握りつぶしたら悔いが残る」と考えていた。 永野厳雄: 永野の後継として補欠選挙で当選したのが永野の後継知事であった宮澤弘(宮澤喜一の弟)だった。 白洲次郎: 為政者があれだけ抵抗したということが残らないと、あとで国民から疑問が出て、必ず批判を受けることになる」(日本国憲法制定を巡ってのGHQとの攻防の折、宮澤喜一に対して) 奥田敬和: 宮澤喜一内閣では運輸大臣として入閣し、成田空港問題シンポジウムに出席するなど、空港反対派(旧熱田派)と対話した。 宮澤裕: 内閣総理大臣などを務めた宮澤喜一は長男。 岸田文武: 自由民主党にあっては、都市局長、資源・エネルギー対策調査会副会長、中小企業調査会副会長、調査局次長、行財政調査会副会長などを歴任し、1988年12月からは党経理局長として、竹下登、宇野宗佑、海部俊樹、宮澤喜一の4代の総裁のもとで、幹事長を補佐した。 鈴木善幸: そこで引き続き宏池会からの総裁選出の流れとなったが、首相臨時代理を務めていた伊東正義は本人が消極的で、やがて派閥を継承することが有力だった宮澤喜一は田中に好かれておらず、また生前の大平と必ずしも関係が良好でなかったこともマイナスに働いた。 橋本龍太郎: 宮澤喜一首相の後継総裁に後藤田正晴と並んで本命視されたが、自民党分裂の原因である竹下派の内部分裂に責任があるとして辞退し、河野洋平総裁の下で政務調査会長に就任した。 谷畑孝: 日本社会党に所属していた1991年12月4日、参議院本会議における代表質問にて、宮澤喜一内閣総理大臣の著書『戦後政治の証言』について、「国内の治安は米軍と丸腰に近い日本の警察が当ってきたのだが、第三国人の横暴などには手が出せず、そのつど米軍などをわずらわせていた。 車谷長吉: 宮澤喜一や竹中正久の靴を揃えたこともあり、特に竹中からは「あんたのようなええ若い者(もん)が、なんでこんなところで下足番しとんや」と言われ、1万円のチップを貰ったという。 植木光教: 派閥は宏池会(池田勇人→前尾繁三郎→大平正芳→鈴木善幸→宮澤喜一派)に所属した。 細川護煕: 宮澤内閣の下で政治腐敗防止のために政治資金規正や政権交代を容易にする小選挙区制度導入といった政治改革実現の目途は立たず、1993年5月、ついに首相の宮澤喜一がテレビの特別番組で「政治改革を必ず実現する」「どうしてもこの国会でやる」と断言し、決意を示したものの党内の根強い反対論を覆せず、再び断念に追い込まれた。 大平正芳: 大蔵省の先輩である前尾繁三郎をヘッドとする大蔵省出身者の池田の政策ブレーンとなり、宮澤喜一や黒金泰美らとは、池田勇人側近の「秘書官トリオ」と呼ばれる。 津島雄二: 1976年の初当選以来、宏池会(大平正芳→鈴木善幸→宮澤喜一派)に属していたが、1994年に下記の自民党離党に伴い離脱。 児島喜久雄: 三女・汪子 - 外交官宮沢泰(宮澤喜一の弟)の妻 |
宮澤喜一の情報まとめ

宮澤 喜一(みやざわ きいち)さんの誕生日は1919年10月8日です。広島出身の政治家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/06 11:00更新
|
miyazawa kiichi
宮澤喜一と同じ誕生日10月8日生まれ、同じ広島出身の人
TOPニュース
宮澤喜一と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター