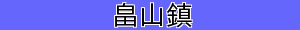畠山鎮の情報(はたけやままもる) 将棋 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

畠山 鎮さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
畠山鎮と関係のある人
今泉健司: 2016年度、11月17日の王位戦予選で畠山鎮に勝利して直近30局の対戦成績を20勝10敗(勝率.667)とし、順位戦C級2組への昇級条件の一つ「2.良い所取りで、30局以上の勝率が6割5分以上であること」を満たして順位戦C級2組への昇級を決めた。 藤森哲也: なお、同棋戦では翌年度も予選突破するが、本戦1回戦で畠山鎮に敗退した。 斎藤慎太郎: 斎藤は10歳のときに畠山鎮に弟子入りしている。 斎藤慎太郎: 本戦1回戦では、師匠である畠山鎮が解説を務める放送で、平藤眞吾に勝利した。 稲葉陽: 2016年2月18日、第74期順位戦B級1組第12回戦にて畠山鎮七段に勝利し、最終局を残して2位以上が確定。 久保利明: 2013年1月10日、第71期順位戦B級1組11回戦で畠山鎮七段に勝利し8勝2敗となり2局残して、A級復帰するとともに、通算600勝となり将棋栄誉賞を達成する。 丸山忠久: 第4期竜王戦では6組ランキング戦を優勝し、本戦でも5組優勝者の畠山鎮に勝利。 今泉健司: 再度の奨励会退会後、畠山鎮の紹介で証券会社に勤めた後、地元福山市で介護職として働く。 斎藤慎太郎: 畠山鎮八段門下。 斎藤慎太郎: 三段リーグでは毎回のように昇段争いに加わりながら終盤に崩れて脱落していたが、8期目となる2011年度後期(第50回)で15勝3敗・1位の成績を修め、畠山鎮門下初のプロ四段となった。 中井広恵: 2003年度のNHK杯テレビ将棋トーナメントでは、1回戦で畠山鎮に、2回戦では当時A級棋士だった青野照市に勝利した(3回戦で中原誠に敗退)。 今泉健司: なお中尾は、畠山成幸と畠山鎮以来の兄弟棋士を目指した松本秀介(第17回にプロ入りした松本佳介の3学年下の弟)が敗れたため、昇段を果たした。 屋敷伸之: 特に2001年度(第60期)における畠山鎮との昇級争いでは、両者の勝敗数が2期連続同じであったため、2期前の僅か星1つの差が効いてしまった。 桐山清澄: 2022年4月27日の5組残留決定戦・畠山鎮戦が最終局となり現役を引退した。 |
畠山鎮の情報まとめ

畠山 鎮(はたけやま まもる)さんの誕生日は1969年6月3日です。神奈川出身の将棋棋士のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 12:43更新
|
hatakeyama mamoru
畠山鎮と同じ誕生日6月3日生まれ、同じ神奈川出身の人
TOPニュース
畠山鎮と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター