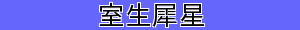室生犀星の情報(むろうさいせい) 詩人 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

室生 犀星さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
室生犀星と関係のある人
萩原朔太郎: 1925年(大正14年)には妻と娘二人を伴い上京し、東京府荏原郡大井町(現・品川区内)、北豊島郡滝野川町田端(現・北区内)へ移り住み、近隣の芥川龍之介や室生犀星と頻繁に往来し、8月に『純情小曲集』を刊行。 水芦光子: 今で謂うファンレターの手紙を出した事が縁で、最初は室生犀星に師事し、戦後 室生の援助で1946年(昭和21年)に詩集「雪かとおもふ」を出版するが、のちに小説も手がけるようになる。 室生朝子: 『室生犀星文学年譜』本多浩、星野晃一共編 明治書院、1982 室生朝子: 『室生犀星句集 魚眠洞全句』編. 北国出版社, 1977.11 堤清二: 異邦人(ユリイカ、1961年)、第2回室生犀星詩人賞受賞 三好達治: 室生犀星や萩原朔太郎など先達詩人からの影響を出立点とし、フランス近代詩と東洋の伝統詩の手法をそれぞれに取り入れ、現代詩における叙情性を知的かつ純粋に表現し独自の世界を開いた。 森茉莉: 室生犀星も慕っており、エッセイには彼のことを書いた文章が多く出てくる。 室生朝子: 詩人の室生犀星の長女。 宮城まり子: また、同じく作家室生犀星にも可愛がられていた。 室生朝子: 『室生犀星詩集』編 (銀河選書) 大和書房, 1964 井上あずみ: 当時の芸名は、井上杏美(金沢市出身の作家・室生犀星の「杏っ子」から命名)。 富岡多恵子: 1961年、『物語の明くる日』で第2回室生犀星詩人賞受賞 会田千衣子: 1963年『鳥の町』で室生犀星詩人賞、1977年『フェニックス』で現代詩女流賞受賞。 水芦光子: 室生犀星の女性初の弟子でもある。 立原道造: 一高在学中に三中の先輩でもある堀辰雄を知り、また室生犀星に師事。 東雅夫: 文豪怪談傑作選10 室生犀星集 童子 ちくま文庫 2008年 ISBN 4480424873 磯村英樹: 1963年、詩集『したたる太陽』で室生犀星詩人賞受賞。 中野重治: 1923年、関東大震災に被災し金沢で避難生活を送っていた室生犀星のもとを初めて訪ね、以後師事した。 加賀乙彦: 室生犀星とは7親等の血縁。 大沢在昌: 萩原朔太郎を目指し室生犀星も好きで、高校入学時に、詩の高校生同人誌「街路」の同人となるが、同年齢の女性の才能にショックを受け、勝てないとやめ、小説を書くことにする。 谷川俊: 性に目覚めるころ 室生犀星 NHK 森茉莉: ただし生活能力のなさから、家はかなり散らかった様子で、室生犀星などは、そのことを気にして夜も眠れなかったという。 中野重治: 『室生犀星』筑摩叢書 1968 大中寅二: 大田区立萩中小学校校歌(1955、詞:室生犀星) 堀辰雄: 室生犀星宅で中野重治や窪川鶴次郎たちと知り合うかたわら、小林秀雄や永井龍男らの同人誌『山繭』に「甘栗」を発表する。 寺内小春: あにいもうと TX 1995 演出 深町幸男,原作・室生犀星 室生朝子: 娘は室生犀星記念館名誉館長の室生洲々子。 萩原朔太郎: 1913年(大正2年)に北原白秋の雑誌『朱欒』に初めて「みちゆき」ほか五編の詩を発表、詩人として出発し、そこで室生犀星と知り合い、室生とは生涯の友となる。6月に室生犀星が前橋を訪れ、そこで山村暮鳥と3人で詩・宗教・音楽の研究を目的とする「人魚詩社」を設立。 葛西善蔵: 弔辞は徳田秋声、谷崎精二が務め、文壇では「葛西善蔵遺児養育資金」が集められ、志賀直哉、佐藤春夫、室生犀星といった面々が協力した。 安宅夏夫: 『愛の狩人室生犀星』 社会思想社 (現代教養文庫) 1973 |
室生犀星の情報まとめ

室生 犀星(むろう さいせい)さんの誕生日は1889年8月1日です。石川出身の詩人のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 06:40更新
|
murou saisei
室生犀星と同じ誕生日8月1日生まれ、同じ石川出身の人
TOPニュース
室生犀星と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】話題のアホネイター