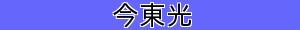今東光の情報(こんとうこう) 作家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

今 東光さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
今東光と関係のある人
尾崎士郎: 戒名は文光院殿士山豪雄大居士(今東光の撰)。 水の江瀧子: たんぽぽは今東光が命名した。 梶山季之: 今東光は「先日もなァ、『酒を無茶飲みするな、自殺行為だぞ』と注意したんだが、梶山はゲラゲラ笑ってな。 清水崑: 今東光『河内カルメン』(アサヒ芸能 1964年 - 1965年) 三島由紀夫: 村松が川端の政治嫌い、イデオロギー嫌いは前から分かっていたことではないかと慰め的に言うと、「政治嫌いといったって、今東光の選挙のときには、応援に熱心に走りまわっていたじゃないか」と三島は川端の祝辞拒否の理由が解せず失望していた様子だったという。 今村昌平: 盗まれた欲情(1958年5月)日活 原作:今東光 阪東妻三郎: 今東光を顧問に据え、自ら陣頭に立ち、映画制作を開始する。 梶山季之: 第1回の賞金は10万円で、贈呈者は今東光が務めた。 野坂昭如: この頃、今東光を会長とする無頼派作家の集まり「野良犬会」のメンバーとなる。 梶山季之: 今東光が命名した戒名は「文麗院梶葉浄心大居士」、棺には愛飲していたサントリーオールドを注がれ、缶入りピース、原稿用紙とモンブランの万年筆、『李朝残影』が納められて、大宅壮一と同じ鎌倉瑞泉寺に葬られた。 今日出海: 『今東光・今日出海集 日本文学全集59』集英社、1972年 熊井啓: その後も初の時代劇『お吟さま』(今東光原作)、戦後の日本映画で初の中国ロケを敢行した『天平の甍』(井上靖原作)などを経て、1986年には戦時中に九州で起きた米軍捕虜生体解剖事件をもとに医師の戦争責任を問うた遠藤周作原作の『海と毒薬』を発表し、ベルリン国際映画祭銀熊賞 (審査員グランプリ)、毎日映画コンクール大賞、3度目のキネマ旬報ベストテンベストワン及び監督賞を受けるなど国内外で評価された。 諸井三郎: 命名者は今東光・今日出海兄弟の父である今武平)を結成し、河上徹太郎、三好達治、小林秀雄、中原中也、大岡昇平らと親交を持つ。 田宮二郎: 同年秋に勝新太郎と共演した田中徳三の監督映画『悪名』(今東光原作)にて勝の相棒「モートルの貞」役に 阿部豊: 今東光原作の話題作『春泥尼』、小林旭主演の『二連銃の鉄』などのヒット作を量産した。 稲垣足穂: 関西学院では今東光などと同級になった。 関口淳: 4月1日、柴田錬三郎の肝煎りで、今東光、吉行淳之介、梶山季之、黒岩重吾、藤本義一といった作家20余名を前にスプーン曲げをおこなう。 瀬戸内寂聴: 1973年に51歳で今春聴(今東光)大僧正を師僧として中尊寺において天台宗で得度、法名を寂聴とする。 江川宇礼雄: 以後監督業に専念して、「紅蓮地獄」(原作は今東光)などを撮った。 川端康成: 今東光と共に芥川龍之介も見舞い、3人で被災した町を廻った。 横山まさみち: 奥州藤原四代(原作:今東光) 依田義賢: 1978年 - お吟さま 原作今東光、監督熊井啓 片岡鉄兵: しかし1928年(昭和3年)ごろから左傾化し始め、更に同時期に今東光の脱退や仲間内での意見の対立などにより新感覚派は事実上消滅した。 木村威夫: 『お吟さま』(1978年、熊井啓監督、依田義賢脚本、今東光原作、岡崎宏三撮影、伊福部昭音楽)宝塚映画=大和新社共同作品。 横光利一: まず川端康成の下宿へ行ったが川端が不在だったため今東光を訪ねた。その横光の身代わりのように、横光に同調して反駁文を書いて『新潮』へ送った今東光は、結果として『文藝時代』を一人脱退し菊池と喧嘩する破目に陥った。 ヘンリー小谷: ^ 今東光『十二階崩壊』中央公論社、1978年 矢野隆司: 作家今東光の研究者としても知られ岩手県浄法寺町が計画した「今東光・瀬戸内寂聴両師記念館」(仮称)世話人のほか、八尾市教育委員会主宰の「やお市民大学講座」や関西学院主催の「関西学院学院史月例研究会」などで講演。2010年、今東光文学研究会を共同主宰し研究誌『慧相』を発行、詳細な年譜を連載した。主な発表論文に「今東光 その生涯と関西学院」、「今東光研究補遺」、「今東光 見えざるものへの畏敬」などがあり、先行研究として引用されることも多い。また今東光夫人の逝去では『週刊新潮』にコメントを寄せた。 井上博道: 「中尊寺」淡交新社、今東光<文>(1967年) 水上勉: 今東光が参議院議員に立候補した際は、川端康成とともに応援演説に立った。 川端康成: 武田麟太郎や藤沢桓夫も、プロレタリア文学運動に加わり、石濱金作が転換、今東光と鈴木彦次郎が旧労農党に加入し、横光利一は極度に迷い動揺した。 |
今東光の情報まとめ

今 東光(こん とうこう)さんの誕生日は1898年3月26日です。神奈川出身の作家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 02:26更新
|
kon toukou
今東光と同じ誕生日3月26日生まれ、同じ神奈川出身の人
TOPニュース
今東光と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター