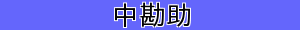中勘助の情報(なかかんすけ) 作家、詩人 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

中 勘助さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
中勘助と関係のある人
小宮豊隆: 同学年に安倍能成、中勘助、藤村操、尾崎放哉、岩波茂雄がいた。 富岡多恵子: 『中勘助の恋』創元社 1993 のち平凡社ライブラリー 橋本武: 2012年に小学館から発行された、中勘助著『銀の匙(小学館文庫)』には、橋本による案内(解説)が全編に併載されており、当時の「『銀の匙』授業」の様子を活字の形で追体験することが出来る。/中勘助×橋本武/夏目漱石が絶賛した、明治少年のみずみずしい見聞が、伝説教師の解説を全編に添え、新たな扉を開ける――。 今江祥智: このころ、岩波文庫めあての古書店めぐりに熱中し、中勘助『銀の匙』を読んで感動、座右の書とする。 中澤まさとも: 中勘助「漱石先生と私」(私〈中勘助〉) 和辻哲郎: 京子は幼少のころ中勘助に偏愛されたことでも知られる。 橋本武: 中学の3年間をかけて中勘助の『銀の匙』を1冊読み上げる国語授業「『銀の匙』授業」で知られる。 中庸助: 芸名の「中庸介」は、敬愛する中勘助に因んだもの。しばらく「中庸介」で通したが、二枚目風なのが気に入らず、「もともと中勘助から頂いた名前なので」ということで、「中庸助」に改名した。 橋本武: 具体的には『銀の匙 中勘助 橋本武案内』(小学館文庫、2012)に詳しい。 赤塚真人: 暴れん坊将軍III 第28話「偽りの拝領妻」(1988年) - 竹中勘助 橋本武: 「生徒の心に生涯残り、生きる糧となる授業をしたい」との思いから、1950年、新制灘中学校で新入生を担当することになった時点から、「教科書を使わず、中学の3年間をかけて中勘助の『銀の匙』を1冊読み上げる」国語授業を開始する。 富岡多恵子: 1994年、評論『中勘助の恋』で第45回読売文学賞受賞 |
中勘助の情報まとめ

中 勘助(なか かんすけ)さんの誕生日は1885年5月22日です。東京出身の作家、詩人のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 11:05更新
|
naka kansuke
中勘助と同じ誕生日5月22日生まれ、同じ東京出身の人
TOPニュース
中勘助と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター