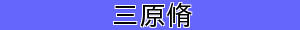三原脩の情報(みはらおさむ) 野球選手 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

三原 脩さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
三原脩と関係のある人
水原茂: 早稲田大学の三原脩とは、プロに進んで以降もライバルであり、ともに監督として日本シリーズを戦った。 長田幸雄: 周囲の奇異な視線で我を取り戻した時には、自分が立っていた左翼の位置には三原脩監督以下、大洋ナインや審判団が集まり「早く出て来い」と手招きしていた。 太田幸司: この登板は試合中の7回にコーチから伝えられたが、これは監督の三原脩が「前日に伝えて眠れなくなったりでもしたら困る」と考えてのことだった。 大石正彦: 三原脩監督時代には代走でも起用されるなど脚力があり、7盗塁を記録している。 中島治康: 翌1947年は開幕からチームが不調で、29試合(10勝19敗〔勝率.345〕)を消化した6月初旬に三原脩が助監督・技術顧問に就任して指揮を執ったため、実態として中島は監督職を解任された状態になった。なお、1949年4月に三原ポカリ事件で監督の三原脩が出場停止となった際には、約3ヶ月間に亘って選手兼任で監督代行も務め、37勝25敗(勝率.597)の記録を残している。 宮崎要: 当初西鉄は三原脩を監督に据えて宮崎を選手専任にしようとしたものの、旧クリッパース側の選手からの反発もあり、三原を総監督に据えて、宮崎は選手兼任でライオンズとしても初代監督となった。 アレックス=ラミレス: 通算336勝は別当薫、三原脩に次いで球団3位、3度のAクラス入りも別当、三原、権藤博に次ぐ球団4人目の快挙だった。 田宮謙次郎: 田宮は茨城出身ということもあってもともと巨人ファンで、監督の三原脩自ら交渉に訪れた巨人側も「まだ仮契約の段階。 田辺義三: ^ 三原脩「風雲の軌跡―わが野球人生の実記」ベースボール・マガジン社、1983年1月1日、ISBN 4583023448、p188。 平山菊二: この年から三番・青田昇、四番・川上哲治に次ぐ五番に入ってクリーンナップを打ち、打率.272(18位)に自己最高の11本塁打の成績を挙げると、翌1949年は主将を務めて監督・三原脩を助ける傍ら、引き続き五番を打って打率.273の成績を残し、巨人の戦後初優勝に貢献した。 梨田昌孝: 近鉄で1シーズン以上務めた歴代監督16人の中で、通算成績で勝ち越しているのは三原脩、西本幸雄、仰木彬、そして梨田の4人である。 水原茂: 張本は「私はいつも言うけど80年以上のプロ野球の歴史の中で、名将と言えるのは、三原脩さん、水原さん、鶴岡さん、川上哲治さん、この4人だと思うんですよ。 黒沢俊夫: 責任感の強い黒沢は、体調が優れないことを監督の三原脩に隠して試合に出場し続けたが、これが結果的に命取りになったとも言われている。 武末悉昌: 監督に名将・三原脩が就任する。 金光秀憲: シリーズ通算15打数6安打4打点で首位打者となるが、初戦の本塁打は0対0の7回に三原脩監督から「初球ストレートが来る」と言われ、中西のカーブを打った。 藤原真: また、三原脩監督の構想から外れたことで、球団にトレードを直訴。 高木喬: 翌1968年、近鉄は三原脩監督就任に伴い、小玉明利監督時代の主力選手を大幅に入れ替えることになり、菊川昭二郎と共に、清俊彦、トニー・ロイとの2対2のトレードで西鉄ライオンズへ移籍。 米川泰夫: 西鉄への移籍については、米川が西鉄に強かったために他チームに取られてはまずいとの、三原脩監督の意向があったともされる。 大下弘: 西鉄の低迷により監督・三原脩への批判が高まり、西日本鉄道社長・木村重吉は西鉄球団代表・西亦次郎に対して、指揮権の合議制化を要求。 石本秀一: 西鉄は三原脩を三顧の礼で監督に迎えたにもかかわらず、優勝候補だった3年目の1953年も優勝出来ずBクラスに沈んだ。 芝野忠男: 1960年に三原脩監督が就任。 仰木彬: 甲子園出場時に練習した大阪スタヂアムで南海の選手を見て憧れていたこともあって仰木本人は南海入団希望であり、南海と中日の契約金は100万円だったのに対し西鉄は60万円だったにもかかわらず、監督の三原脩が自ら自宅を訪れ「私に任せなさい」と肩をたたかれたことで「運命を感じた」と、1954年、西鉄に年俸36万円で入団した。 荒川博: シーズン終了後の11月26日に三原脩の後任として監督に昇格し、コーチ陣に広岡、小森、沼澤と早大出身の後輩を招聘して「早大カルテット」と称された。 城之内邦雄: 非常に無口で、あるときヤクルト監督の三原脩と対談したが、会話録に城之内の発言が全くなかった。 大沢啓二: シリーズ後、滅多なことでは選手をほめない鶴岡が「大沢、本当によくやってくれた」と直々に労い、西鉄の三原脩監督はこのシリーズの総括として、「MVPの杉浦は副賞として自動車を与えられたが、大沢にも小型の自動車を与えるべき」と語っている。 大下弘: 表向きはあまり練習もせず練習嫌いとも言われていたが、西鉄時代の監督であった三原脩は大下が陰で練習している事を知っていた様である。 牧野直隆: 1934年に鐘淵紡績に入社した後もアマチュア野球選手としてプレーを続け、同年の第8回全日本都市対抗野球大会では三原脩と共に全大阪チームのメンバーとして出場して優勝したほか、アメリカ・大リーグ選抜が2度目の来日をした際には全日本チームのメンバーに選ばれた経験も持つ。 田村大五: 『昭和の魔術師―宿敵 三原脩・水原茂の知謀と謀略』 川崎徳次: しかし、頼られると意気に感じて投げる川崎は、中尾より監督の三原脩に頼りにされていたという。 稲川誠: 第2試合は5回表に代打金光秀憲の適時打と伊藤勲の犠飛で大洋が2点を勝ち越したが、7回、8回と先発の高橋重行が1点づつを失い同点となったところで、三原脩監督は鈴木隆を挟んでから稲川をマウンドに送った。 |
三原脩の情報まとめ

三原 脩(みはら おさむ)さんの誕生日は1911年11月21日です。香川出身の野球選手のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/06 22:56更新
|
mihara osamu
三原脩と同じ誕生日11月21日生まれ、同じ香川出身の人
TOPニュース
三原脩と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター