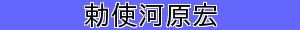勅使河原宏の情報(てしがはらひろし) 華道家、映画監督 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

勅使河原 宏さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
勅使河原宏と関係のある人
武満徹: 1960年代には小林正樹監督の『切腹』(1962年、第17回毎日映画コンクール音楽賞受賞)、羽仁進監督の『不良少年』(1961年、第16回毎日映画コンクール音楽賞受賞)、勅使河原宏監督の『砂の女』(1964年、第19回毎日映画コンクール音楽賞受賞)、『他人の顔』(1966年、第21回毎日映画コンクール音楽賞受賞)などの映画音楽を手がけ、いずれも高い評価を得ている。 濱口竜介: 作品賞と脚色賞でのノミネートは日本映画初、監督賞のノミネートは36年ぶりで、『砂の女』を監督した勅使河原宏(第38回)、『乱』を監督した黒澤明(第58回)に続き3人目となった。 森田富士郎: 『利休』(1989年、勅使河原宏監督) 富士正晴: 同年秋には『豪姫』が勅使河原宏監督、宮沢りえ主演で映画化された。 井川比佐志: 1962年、安部公房原作・脚本、勅使河原宏の監督映画『おとし穴』に主演して注目を浴びる。 安部公房: 5月、花田清輝、佐々木基一、関根弘、野間宏、勅使河原宏、長谷川龍生らと「記録芸術の会」を結成する。 安部公房: 4月、勅使河原宏から譲り受けた調布市若葉町仙川の敷地に真知の設計になる新居を建て、家族とともに転居する。 細川護熙: 1989年には勅使河原宏監督の映画『利休』に織田有楽斎役で1カットのみカメオ出演している。 勅使河原蒼風: 勅使河原霞(草月流 2代目家元)、勅使河原宏(同 3代目家元)の父、勅使河原茜(同 4代目家元)の祖父。 木下恵介: このいわゆる「木下学校」からは小林正樹、川頭義郎、松山善三、勅使河原宏、吉田喜重、山田太一など、多数の映画人が巣立っていっている。 赤瀬川原平: 『シナリオ利休』勅使河原宏共著 淡交社 1989 吉原幸子: 『ふしぎな森〜勅使河原宏いけばな作品集 I 』 吉原幸子(詩)主婦の友社 1982 蛭子能収: 映画にも関心を持ち、勅使河原宏監督の『砂の女』など前衛映画も進んで鑑賞した。 原將人: この時の審査員は、植草甚一、武満徹、勅使河原宏、松本俊夫、粟津潔、飯村隆彦、山田宏一。 勝新太郎: 勝プロは、既に経営が立ち行かなくなった末期の大映が傾倒した若者向けの暴力・エロ・グロ路線の作品とは一線を画し、三隅研次・安田公義・森一生・増村保造ら大映出身の監督たちと時代劇の伝統を絶やさぬよう拘りぬいた映画制作を続け、勅使河原宏・五社英雄・斎藤耕一・黒木和雄ら、当時インディペンデントな場から台頭しつつあった監督(斎藤のみは元日活であるがスチルマン出身である)たちとも手を組み、『燃えつきた地図』、『人斬り』などを製作・主演した。 小林トシ子: 1956年、映画監督の勅使河原宏と結婚し、後に三人の娘をもうける。 赤瀬川原平: 1989年には、勅使河原宏と共同脚本を担当した映画『利休』で、日本アカデミー賞脚本賞を受賞。 森田富士郎: 同年の『鬼龍院花子の生涯』(五社英雄監督)、1989年(平成元年)の『利休』(勅使河原宏監督)で、日本アカデミー賞優秀撮影賞を受賞している。 ワダ・エミ: その後は勅使河原宏『利休』や大島渚『御法度』のような日本映画だけでなく、メイベル・チャン『宋家の三姉妹』、チャン・イーモウ(張芸謀)『HERO』、ピーター・グリーナウェイ『プロスペローの本』など国内外の著名監督の作品に多数かかわった。 勅使河原蒼風: 第三代 勅使河原宏 1980年〜2001年 假屋崎省吾: 家元の勅使河原宏に師事する。 三木淳: イサム・ノグチは彫刻「土門さん」と中庭造園、勅使河原宏は造園「流れ」とオブジェ「樹魔」、亀倉雄策は銘板と年譜、草野心平は銘石「拳湖」を寄贈した。 植野葉子: 利休(1989年、勅使河原宏監督) - 勢以 大樋年朗: 1991年 -「大樋長左衛門・加山又造・勅使河原宏 三人展」 大島渚: また、ジャン=リュック・ゴダールは『ゴダールの映画史』(1998年)において溝口健二、小津安二郎、勅使河原宏とともに大島を取り上げた。 赤瀬川原平: 『豪姫』 監督:勅使河原宏、脚本:赤瀬川原平+勅使河原宏 1992 入江美樹: 日本テレビ系『シャボン玉ホリデー』にマスコットガールとして出演し、1965年に第16回NHK紅白歌合戦の審査委員を務める、1966年に勅使河原宏監督の映画『他人の顔』に出演する。 近藤明男: 在学中から勅使河原宏監督『燃えつきた地図』、三隅研次監督『雪の喪章』の他、『ザ・ガードマン』などのTVドラマの助監督としてキャリアをスタートする。 赤瀬川原平: 『利休』 監督:勅使河原宏、脚本:赤瀬川原平+勅使河原宏 1989 今福将雄: 利休(1989年、勅使河原宏監督) - 長次郎 |
勅使河原宏の情報まとめ

勅使河原 宏(てしがはら ひろし)さんの誕生日は1927年1月28日です。東京出身の華道家、映画監督のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 05:48更新
|
teshigahara hiroshi
勅使河原宏と同じ誕生日1月28日生まれ、同じ東京出身の人
TOPニュース
勅使河原宏と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター