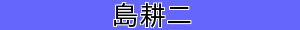島耕二の情報(しまこうじ) 映画監督 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

島 耕二さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
島耕二と関係のある人
目黒幸子: 胡椒息子(1953年、島耕二監督) - お静 林寛: 『風の又三郎』 : 監督島耕二 - 一郎の祖父 如月寛多: 『エノケンのびっくりしゃっくり時代』 : 大映東京撮影所、島耕二監督 滝花久子: 瀧の白糸(監督:島耕二。 目黒幸子: 馬賊芸者(1954年、島耕二監督) - 染奴 目黒幸子: 夕やけ小やけの赤とんぼ(1961年、島耕二監督) - 石毛花江 轟夕起子: マキノとの離婚(昭和25年)、島耕二との再婚(昭和28年)、離婚(昭和40年)を繰り返すなど私生活は波乱万丈だった。 目黒幸子: 慕情の河(1957年、島耕二監督) - 女プロデューサー 目黒幸子: 総会屋錦城 勝負師とその娘(1959年、島耕二監督) - 浜田 東坊城恭長: 当時の俳優仲間には、のちに映画監督となる島耕二や渡辺邦男がいた。 湯浅憲明: 恰幅がよく丸顔でもあり『ガメラ創世記 -映画監督・湯浅憲明-』によると、『大怪獣ガメラ』撮影時に島耕二からは「ガメラはぬいぐるみじゃなくて、湯浅監督本人がそのまま演じればいいんだよね」と冷やかされたという。 轟夕起子: 映画監督のマキノ雅弘、島耕二は元夫。 東坊城恭長: 消防手 1934年 監督 脚本畑本秋一、主演島耕二、森静子、月田一郎 新興キネマ作品 村田実: 1932年(昭和7年)8月、中谷貞頼専務が、名物所長として知られた池永浩久とその一派を駆逐し所内の実権を握ろうとした内紛劇が起こり、さらに中谷が経営合理化の名目で撮影所従業員186名を大量解雇したことによる大争議が勃発、他の幹部監督らと従業員側に立って争議を指導したが、やがて激化する従業員側と会社側との板挟みになり、9月には争議を「収拾する能力なくその任に耐えず」と伊藤大輔・内田吐夢・田坂具隆・小杉勇・島耕二・製作部の芦田勝の「脱退七人組」と共に退社した。 津村謙: しばらくヒットに恵まれなかったが、1951年(昭和26年)に、「上海帰りのリル」(作詞:東条寿三郎、作曲:渡久地政信)が大ヒット(島耕二監督によって1952年に映画化/後に根津甚八がカバーする)。 滝花久子: 細雪(監督:島耕二。 若杉光夫: 1951年に島耕二の助監督を経験し、劇団民藝演出部に入団。 久保明: 十代の性典(1953年、島耕二監督) 東坊城恭長: 靴 1927年 原作・脚本 監督内田吐夢、主演島耕二、小杉勇 八木保太郎: 1932年(昭和7年)、日活に争議が起こり、八木は馘首となり、村田実、田坂具隆、内田吐夢、小杉勇、島耕二らも同社を退社した。 目黒幸子: 宇宙人東京に現わる(1956年、島耕二監督) - 磯辺徳子 水の江瀧子: 島耕二 村田知栄子: 1936年日活多摩川撮影所に移り、『人生劇場』で小杉勇と共演し、『恋は雨に濡れて』では岡譲二、時代劇『裸の町』では島耕二の相手役を務めた。 光岡龍三郎: 『瀧の白糸』 : 監督島耕二、1954年 目黒幸子: 複雑な彼(1966年、島耕二監督) - 女中 杉狂児: 1938年(昭和13年)以降は千葉泰樹監督や、監督に転向した島耕二作品で主演に起用された。 目黒幸子: 浅草物語(1953年、島耕二監督) - けい子 東坊城恭長: 死の宝庫 前・中篇 1926年 監督田坂具隆、伊奈精一、主演星野弘喜、島耕二 小杉勇: 同期に八木保太郎、吉村廉、島耕二などがいる。 小田切みき: その他の映画出演作に『十代の性典』(1953年、島耕二)、『ひめゆりの塔』(1953年、今井正)、『雁』(1953年、豊田四郎)、『太陽のない街』(1954年、山本薩夫)、『警察日記』(1955年、久松静児)、『潮騒』(1971年、森谷司郎)、『親鸞 白い道』(1987年、三国連太郎)など。 |
島耕二の情報まとめ

島 耕二(しま こうじ)さんの誕生日は1901年2月16日です。長崎出身の映画監督のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 11:03更新
|
shima kouji
島耕二と同じ誕生日2月16日生まれ、同じ長崎出身の人
TOPニュース
島耕二と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター