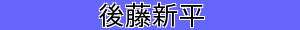後藤新平の情報(ごとうしんぺい) 政治家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

後藤 新平さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
後藤新平と関係のある人
池田成彬: 中條には平田東助、後藤新平も学んでいる。 椎名悦三郎: 椎名素夫は次男、血縁のない叔父に後藤新平がいる。 島安次郎: 技術幹部として蒸気機関車等の開発に手腕をふるいつつ、当時鉄道院総裁だった後藤新平の指示で国鉄の広軌化(広軌改築。 金子直吉: 明治32年(1899年)、直吉は当時の台湾総督府民政長官後藤新平と交渉し、専売制を目論んでいた後藤と通じ台湾樟脳油の販売権のうち65%を獲得。 津嘉山正種: 復興せよ! 後藤新平と大震災2400日の戦い(2012年1月22日、読売テレビ) - 後藤新平 役 工藤美代子: 工藤は、その著書『関東大震災「朝鮮人虐殺」の真実』(2009年)において震災時に朝鮮人暴動は実際にあったとし、最終的にその根拠を、当時の内務大臣であった後藤新平が警視庁官房主事の正力松太郎に、暴動が実際にあった、(したがって、自警団の朝鮮人殺害は正当だが)朝鮮人の報復がお上に向かうといけないから自警団には引いてもらう、自警団はねぎらうつもりだと述べたことだとする。 鶴見俊輔: 1922年6月25日、東京府東京市麻布区(現在の東京都港区)で、父・祐輔と母・愛子(後藤新平の娘)の間に、4人きょうだいの2番目(長男)として生まれる。 長与専斎: 石黒の紹介で、愛知医学校長兼愛知病院長であった後藤新平を見出して明治16年(1883年)、衛生局に採用し、明治25年(1892年)、衛生行政の後継者として後藤を衛生局長に据えたが、後藤が相馬事件に連座して失脚するとこれを見捨て、以後は石黒が医学界における後藤の後ろ盾となった。 井上勝: 鉄道事業は後に、原敬や後藤新平に引き継がれた。 司馬凌海: 教え子に後藤新平。 水野錬太郎: 1918年(大正7年)4月23日、後藤新平からの慫慂で寺内正毅内閣の内務大臣となる。 鶴見和子: 1918年6月10日、東京府麻布区で、父・祐輔と母・愛子(後藤新平の娘)の間に、4人きょうだいの1番目(長女)として生まれる。 乃木希典: 乃木による台湾統治について、官吏の綱紀粛正に努め自ら範を示したことは、後任の総督である児玉源太郎とこれを補佐した民政局長・後藤新平にとって大いに役立ったと評価されている。 八田與一: 日本統治時代の台湾では、初代民政長官であった後藤新平以来、マラリアなどの伝染病予防対策が重点的に採られ、八田も当初は衛生事業に従事し、嘉義・台南・高雄など各都市の上下水道の整備を担当した。 御厨貴: 『時代の先覚者・後藤新平 1857-1929』(藤原書店、2004年) 小市慢太郎: 復興せよ! 後藤新平と大震災2400日の戦い(2012年1月22日、YTV) - 太田圓三 役 津田英三: 復興せよ! 〜後藤新平と大震災2400日の戦い〜(2012年1月22日 / 読売テレビ系列) 尾崎秀実: 5ヵ月後、父が台湾総督府の後藤新平の招きを受け、台湾日日新報社漢文部主筆として赴任したことから、日本統治時代の台湾で育ち、台北第一中学校(現・台北市立建国高級中学)に進学。 内山尚三: 政治家の後藤新平は義祖父(章子の祖父)、社会学者の鶴見和子は義姉(章子の姉)、哲学者の鶴見俊輔は義兄(章子の兄)。 一海知義: 『決定版 正伝 後藤新平』鶴見祐輔 藤原書店 全8巻 2004-2006。 古本新之輔: 復興せよ! 後藤新平と大震災2400日の戦い(2012年1月22日、読売テレビ) - 十河信二 役 椎名悦三郎: 川島と椎名は戦前から関わりが有り、また二人は後藤新平を介しての親類や側近としての繋がりも持っていた。 堤康次郎: 首相桂太郎による立憲同志会の結成計画に永井らも参加すると、これを追って創立委員に名を連ね、桂を介して後藤新平を、更に財界の大物だった藤田謙一を紹介される。 杉原千畝: 後藤新平が制定した同校のモットー「自治三訣」は、「人のお世話にならぬよう、人のお世話をするよう、そして報いを求めぬよう」というものであった。 たかまつなな: 2011年には『第13回後藤新平・新渡戸稲造記念 拓殖大学 高校生・留学生作文コンクール』で最優秀賞(後藤新平賞)を受賞。 織田萬: 1906年(明治39年)、台湾総督府民政長官だった後藤新平に請われ、臨時台湾旧慣調査委員を引き受ける。 吉川勇一: 山村工作隊、東大ポポロ事件、砂川闘争などに参加し、講和・安保両条約発効に抗議する全学ストライキを指導して退学処分を受けた後は、共産党員として専従活動家の道を歩み、全学連書記局員、日本戦没学生記念会(わだつみ会)事務局員(組織部長)、日本平和委員会事務局員、同常任理事などを歴任して実務能力を身につけ、所感派の山村工作隊出身ながら「日本共産党第6回全国協議会(六全協)」後も党に留まり、1958年4月には、後藤新平の義理の姪婿で鶴見和子・俊輔姉弟と姻戚に当たる平野義太郎の仲人で結婚していたが、1965年、前年の原水爆禁止世界大会で共産党の方針に反対意見を表明したことで党から除名処分を受ける。 佐野利器: 9月末には、内務大臣後藤新平が帝都復興院を置いて総裁に就き、その依頼で佐野も帝都復興院理事・建築局長に就任し、関東大震災後の復興事業・土地区画整理事業を推進したが、これに消極的で拙速主義を取り、予算を削減しようとする副総裁宮尾舜治、理事・計画局長池田宏らと対立した。 相馬半治: 祝は台湾に純民間の製糖会社を作るのは時期尚早と難色を示すが、小川は民政長官の後藤新平の説得に成功、結果、1906年(明治39年)、渋沢栄一を相談役、小川を取締役社長、相馬を専務として明治製糖が設立された。 水野錬太郎: 1923年(大正12年)8月26日に加藤首相が死去し第2次山本内閣に代わるも、9月1日に関東大震災があったため後任の内相(後藤新平)が決まるまで(9月2日)陣頭指揮をした。 |
後藤新平の情報まとめ

後藤 新平(ごとう しんぺい)さんの誕生日は1857年7月24日です。岩手出身の政治家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 05:37更新
|
gotou shinpei
後藤新平と同じ誕生日7月24日生まれ、同じ岩手出身の人
TOPニュース
後藤新平と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター