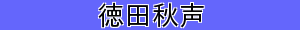徳田秋声の情報(とくだしゅうせい) 作家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

徳田 秋声さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
徳田秋声と関係のある人
川端康成: 康成は、武者小路実篤などの白樺派や、上司小剣、江馬修、堀越亨生、谷崎潤一郎、野上彌生子、徳田秋声、ドストエフスキー、チェーホフ、『源氏物語』、『枕草子』などに親しみ、長田幹彦の描く祇園や鴨川の花柳文学にかぶれ、時々、一人で京都へ行き、夜遅くまで散策することもあった。 坂口安吾: 徳田秋声を批判したこの随筆が縁で、尾崎士郎と知り合う。 野溝七生子: 島崎藤村・田山花袋・徳田秋声の選で『山梔』が「福岡日日新聞」懸賞小説特選となり、同紙に連載。 葛西善蔵: 友人の紹介で徳田秋声に師事、坪内逍遙に学ぶため聴講生として早稲田大学英文科の講義を受講、相馬泰三や広津和郎たちと知り合い、同人雑誌「奇蹟」のメンバーとして迎えられ(雑誌名の「奇蹟」は、広津や舟木重雄と井の頭公園に行った際に無口だった葛西が突然扇子を持って踊り出したのを舟木が奇蹟だと感じたことから命名された)、1912年、「奇蹟」創刊号に葛西歌棄名義で『哀しき父』を発表。 田山花袋: 5月12日には重体となり、徳田秋声、近松秋江、前田晁、白石実三、中村星湖、中村白葉らが駆けつけるも翌5月13日、東京府代々幡町の自宅で死去した。 舟橋聖一: このほかにも、今日出海らと「蝙蝠座」を、小林秀雄や井伏鱒二らと「新興芸術派クラブ」を、飯塚友一郎らと「演劇学会」を結成して盛んに文芸活動に身を投じる一方、『あらくれ会』同人になり徳田秋声の門下生となっている。 島田清次郎: この舟木芳江事件の顛末を、徳田秋声は『解嘲』[2]として発表した(1925年)。 鈴木三重吉: ^ 運動の当初の賛同者には泉鏡花、小山内薫、徳田秋声、高浜虚子、野上豊一郎、野上弥生子、小宮豊隆、有島生馬、芥川龍之介、北原白秋、島崎藤村、森鷗外、森田草平の他数十名、1年後には小川未明、谷崎潤一郎、久米正雄、久保田万太郎、有島武郎、秋田雨雀、西條八十、佐藤春夫、菊池寛、三木露風、山田耕筰、成田為三、近衛秀麿らも加わっている。 尾崎紅葉: 泉鏡花、田山花袋、小栗風葉、柳川春葉、徳田秋声など優れた門下生がいる。 武田麟太郎: 1943年(昭和18年)には、武田が「文学の神」と崇めていた徳田秋声が亡くなっていた。 増村保造: 爛(1962年、大映東京)原作:徳田秋声、脚本:新藤兼人 新藤兼人: 爛(ただれ)(1962年3月14日公開、増村保造監督、大映)※原作:徳田秋声 渡辺拓海: 文豪とアルケミスト(徳田秋声) 宇野浩二: 徳田秋声の還暦祝賀会に出席した。 新藤兼人: 甘い秘密(1971年8月25日公開、吉村公三郎監督、近代映画協会・松竹)※原作:徳田秋声 赤澤遼太郎: 舞台「文豪とアルケミスト 捻クレ者ノ独唱(アリア)」(2022年2月3日 - 13日、シアター1010 / 2月18日 - 20日、森ノ宮ピロティホール) - 主演・徳田秋声 役 藤澤清造: 安野に紹介された徳田秋声の縁で三島霜川が編集主任であった演芸画報社に入社し、訪問記者として勤める。 岩野泡鳴: 正宗白鳥は泡鳴を評して「子供に対してほとんど愛情らしいものを感じないのは、日本の作家のうち類例を絶している」と述べ、徳田秋声も子供を不幸な運命にしている例として、島村抱月、島崎藤村、田山花袋とともに泡鳴の名を挙げている。 宇野浩二: 近松秋江の病気療養費を調達するために徳田秋声・正宗白鳥・上司小剣らと『近松秋江傑作選集』を編集した。 杉浦茂: その後、1936年には本郷区本郷森川町にある徳田秋声の経営する不二ハウスへ移った。 佐々木孝丸: この間、硯友社の文学者を始め、島崎藤村・田山花袋・徳田秋声・正宗白鳥・国木田独歩らの本を濫読し、同人たちと神戸文学会を結成して回覧雑誌を発行していた。 津田信: 1947年に帰国後、小島政二郎に師事し、徳田秋声の作品を研究。 葛西善蔵: 弔辞は徳田秋声、谷崎精二が務め、文壇では「葛西善蔵遺児養育資金」が集められ、志賀直哉、佐藤春夫、室生犀星といった面々が協力した。 武田麟太郎: 武田はその家から東京に通い、共に徳田秋声を尊敬する川端と協力し、秋声の作品集の刊行に向け勤しんでいたが、秋声の息子・徳田一穂の突然の不可解な変心により出版は翌年の3月初旬に頓挫した。 新藤兼人: 縮図(1953年)原作:徳田秋声 - キネマ旬報ベストテン10位 渡辺拓海: 文豪とアルケミスト 〜審判ノ歯車〜(徳田秋声) 紅野敏郎: 『論考徳田秋声』桜楓社, 1982 円地文子: 10月『女人芸術』に一幕劇「晩春騒夜」を発表し、徳田秋声の賞賛を得る。 川端康成: 1934年(昭和9年)1月に、「文藝懇話会」が結成されて、島崎藤村、徳田秋声、正宗白鳥、横光利一が名を連ね、川端も会員となった。 吉屋信子: 1919年、初の長編『地の果まで』が大阪毎日新聞で一等に選ばれた(撰者は幸田露伴・徳田秋声・内田魯庵)。 |
徳田秋声の情報まとめ

徳田 秋声(とくだ しゅうせい)さんの誕生日は1872年2月1日です。石川出身の作家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 01:01更新
|
tokuda syuusei
徳田秋声と同じ誕生日2月1日生まれ、同じ石川出身の人
TOPニュース
徳田秋声と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター