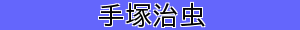手塚治虫の情報(てづかおさむ) 漫画家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

手塚 治虫さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
手塚治虫と関係のある人
手塚るみ子: 1964年、東京都練馬区で手塚治虫の長女(第2子)として生まれる。 宮腰義勝: 1958年、上京し、手塚治虫のアシスタントになる。 永野愛: 手塚治虫のブッダ -赤い砂漠よ!美しく- 出﨑統: 小学4~5年生の頃より手塚治虫に憧れてストーリー漫画を描くかたわら、学校をさぼって映画館に通うほどの映画好きであった。 小室孝太郎: 19歳から手塚治虫の門弟として修業し、1968年に独立する。 大島ミチル: 2011年 - 手塚治虫のブッダ -赤い砂漠よ!美しく- 水野英子: 漫画史的にみると、手塚治虫が少年漫画で用いたダイナミックで映画的な表現技法を少女漫画に移植し、それを女性ならではの感性で昇華することによって(登場人物の衣装や髪型の緻密な描写、カラー原稿における華やかな色使い、恋愛感情の表現など)、当時の主流だった男性漫画家が描いた少女漫画にはない、女性の視点から描いた新しい少女漫画の世界を創出したとされる。 米澤嘉博: 手塚治虫や水木しげる作品のファンで、中学時代に同人活動を始め、同人サークル「アズ漫画研究会」に自作の漫画を多数発表した。 業田良家: 2013年、『機械仕掛けの愛』で第17回手塚治虫文化賞短編賞を受賞。 石ノ森章太郎: 高校2年生の春(5月)、手塚治虫より仕事を手伝って欲しいとの電報が届き、『鉄腕アトム』のアシスタントを務める。 秋田貞夫: 1970年代になり少年誌の『週刊少年チャンピオン』が『ドカベン』(水島新司)、『バビル2世』(横山光輝)、『魔太郎がくる!!』(藤子不二雄Ⓐ)、『ブラック・ジャック』(手塚治虫)、『あばしり一家』『キューティーハニー』(永井豪)、『番長惑星』(石ノ森章太郎)、『恐怖新聞』(つのだじろう)、『ふたりと5人』(吾妻ひでお)、『百億の昼と千億の夜』(原作:光瀬龍、漫画:萩尾望都)、『がきデカ』(山上たつひこ)、『月とスッポン』(柳沢きみお)、『青い空を、白い雲がかけてった』(あすなひろし)、『750ライダー』(石井いさみ)、『エコエコアザラク』(古賀新一)、『ゆうひが丘の総理大臣』(望月あきら)、『マカロニほうれん荘』(鴨川つばめ)などの大人気作品に後押しされ、『週刊少年ジャンプ』(集英社)と競い合う形で、1977年には200万部を突破してトップに立ち、また、少女誌の『月刊プリンセス』は『悪魔の花嫁』(原作:池田悦子、作画:あしべゆうほ)、『イブの息子たち』(青池保子)、『王家の紋章』(細川智栄子 佐藤元: “フウムーン”. 手塚治虫公式サイト. 2016年5月20日閲覧。 エルヴィン=ロンメル: 『ジャングル大帝』、日本の漫画とアニメ、手塚治虫原作。 北野英明: 原作:手塚治虫・文:辻真先) 永井豪: 手塚治虫が多くの原稿を抱えてしめ切りも迫った状況でアメリカのコミックイベントに参加するための旅行に永井も他の漫画家仲間と一緒に参加した時を振り返って。 菅生隆之: 手塚治虫のブッダ -赤い砂漠よ!美しく- 日野由利加: 手塚治虫のブッダ -赤い砂漠よ!美しく-(2011年、マーヤー妃) 徳南晴一郎: 雑司が谷にあった手塚治虫の住居"並木ハウス"に居候していたこともある。 堤義明: また、人気面でも子供が好むブルーや手塚治虫のジャングル大帝の「レオ」をチームカラーやシンボルマークに採用するなど従来のイメージを一新。 村上克司: 少年時代から絵を描くのが得意で、手塚治虫や小松崎茂に大きな影響を受けた。 山本ルンルン: 影響を受けた人物は、イラストレーターでは金子國義、横尾忠則、宇野亜喜良、漫画家では佐々木マキ、手塚治虫、藤子不二雄。 近藤日出造: 近藤は『週刊朝日』1949年4月24日号の特集「子どもの赤本 俗悪マンガを衝く」で横山隆一、清水崑とともにインタビューに答え、当時隆盛だった赤本漫画に対し「絵というようなものじゃない」と断じ、さらに『中央公論』1956年7月号では「子供漫画を斬る」と題するエッセイを発表し、「これらの作者と一緒くたにして『漫画家』と呼ばれることが、腹立たしいほどだ」と述べた(ただし、赤本出身である手塚治虫については「さすが格段の腕前」とおおむね許容的であった)。 中山昌亮: ブラック・ジャック〜青き未来〜(原作:手塚治虫、脚本:岩明均、『週刊少年チャンピオン』、2011年41号 - 2011年46号、2012年8号 - 2012年11号、秋田書店) 松本大洋: のちの『IKKI』編集長江上英樹は『IKKI』に松本を起用したことについて、「『ガロ』が白土三平、『COM』が手塚治虫を擁したのと同じ意味合いで、彼の存在は、この増刊号に不可欠なものと言えた」と振り返っている。 ジョージ秋山: 「漫画は嫌い」「漫画を読むとバカになる」「手塚治虫の作品は読んだことがない」と述べているが、テレビアニメ『戦え!オスパー』の仕事をともにした漫画家のとりいかずよしによると、実際には漫画を愛しており、手塚治虫についてもとても尊敬していて、手塚の写真を額に入れて飾っていたという。 松尾諭: 関西テレビ55周年記念ドラマ 神様のベレー帽〜手塚治虫のブラック・ジャック創作秘話〜(2013年9月24日、関西テレビ・フジテレビ系) - 坪田茂雄 役 松山薫: 手塚治虫の姪。 下田岺易: 手塚治虫のブッダ -赤い砂漠よ!美しく-(2011年) 有間しのぶ: 2019年、『その女、ジルバ』で第23回手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞。 武器屋桃太郎: 漫画に関しては手塚治虫作品(特に『火の鳥』『ブラックジャック』) 『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ、『ふしぎ遊戯』『魔法陣グルグル』などを特に好きな作品として発言。 |
手塚治虫の情報まとめ

手塚 治虫(てづか おさむ)さんの誕生日は11月3日です。大阪出身の漫画家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/06 05:16更新
|
teduka osamu
手塚治虫と同じ誕生日11月3日生まれ、同じ大阪出身の人
TOPニュース
手塚治虫と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター