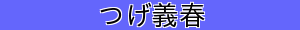つげ義春の情報(つげよしはる) 漫画家 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

つげ 義春さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
つげ義春と関係のある人
松本隆: つげ義春や永島慎二など『ガロ』系漫画や渡辺武信の現代詩に影響を受けた独特の作風で、都市に暮らす人々の心象風景を「ですます」調で描き、一部に熱狂的支持者を生むとともに、日本語ロック論争の発端となった。 菅野修: 1971年に画家をめざして上京するが、つげ義春、白土三平、勝又進などの影響を受け漫画家を目指すようになる。 岡田晟: ^ つげ義春を旅マップする【山手線のつげ義春Ⅰ】 呉智英: 漫画にも造詣が深く、漫画評論同人誌『漫画主義』の編集部に石子順造、山根貞男、梶井純、権藤晋がいたころに同誌につげ義春、白土三平、ジョージ秋山についての評論を発表。特につげ義春の『沼』に衝撃を受ける。 つげ忠男: 1960年頃から、兄・つげ義春の影響で漫画を描き始め(それ以前から兄の手伝いはしていた)、貸本誌『街』で『自殺しに来た男』が入賞しデビューするが、1959年の『回転拳銃』で実質的なデビューを果たしている。 安藤尋: つげ義春ワールド・義男の青春(1998年、テレビ東京) 水木しげる: 水木がこの頃、妖怪文化に熱中しはじめたきっかけについて、つげ義春が2019年にインタビューに答えているが(『つげ義春が語る 旅と隠遁』(筑摩書房)、P.318。 雁屋哲: 大学生時代につげ義春の『ねじ式』を読み「天地がひっくり返るような衝撃を受ける」。また、「目がくらむような人間だった」とも表現し、つげ義春全集や入手できる限りの著書を所有している。 横山あきお: つげ義春ワールド・ゲンセンカン主人より「李さん一家」(1993年) - 李さん 役 蛭子能収: 「夢をもとに漫画を描く」という創作方法は、20歳のときに読んだつげ義春の漫画作品『ねじ式』に大きな影響を受けている。 杉作J太郎: つげ義春ワールド ゲンセンカン主人(1993年) - 三流さん つげ忠男: 唯一かばってくれる2人の兄(一人はつげ義春)はろくに中学校も出ないままに働きに出ていたため昼間はいなかった。 中村映里子: “成田凌、中村映里子、森田剛が共演 つげ義春「雨の中の慾情」を片山慎三が映画化”. いましろたかし: 同時に主人公像は完全に枯れた物へ移行し、私小説的描写とも相まって「平成のつげ義春」という表現がより当てはまる作風になった。 蛭子能収: 、長崎商業高等学校卒業後、地元の看板店に就職するも、つげ義春の『ねじ式』に衝撃を受けて1970年に上京し、看板屋、ちり紙交換、ダスキンのセールスマンなどの職を経て『月刊漫画ガロ』(青林堂)1973年8月号掲載の入選作『パチンコ』で漫画家デビュー。 蛭子能収: つげ義春やATG映画に影響されたシュールで不条理なギャグ漫画や暴力的なモチーフを多用するダークな漫画を描くようになる。 池上遼一: つげ義春の熱烈なファンで、水木のアシスタントに入った時、その場につげもいて驚愕したという。 梶井純: 『つげ忠男の世界』、つげ義春研究会編、北冬書房、1994年1月(非売品) 水木しげる: アシスタントであったつげ義春が水木に最後に会ったのは2009年から2010年頃で、場所は地元の神社であった。 やまだ紫: 1993年には『ガロ』2・3合併号でやまだ紫特集が組まれ、その際はつげ義春、高橋章子、井坂洋子、内田春菊、黒川創らがコメントや文章を寄せた。 逆柱いみり: 「つげ義春 夢日記 昭和四十七年七月六日」(『アックス』Vol.119、2017年10月) 滝田ゆう: そして貸本漫画の東考社社長桜井昌一の紹介で、1967年(昭和42年)4月『月刊漫画ガロ』(青林堂)に組織の都合に振り回される男を描いた『あしがる』を発表し、つげ義春、林静一ら同誌の掲載陣の仲間入りを果たす。 赤塚不二夫: また既にプロの漫画家だったつげ義春が同じく赤塚の漫画に興味を持ち、しばしば遊びに来るようになった。 近藤ようこ: 1998年に発刊された新潮文庫版つげ義春作品集『義男の青春・別離』では、巻末に6頁にわたり、「夢とチボーの彼岸」と題する詳細な解説を書いている 藤宮史: つげ義春トリビュート展 第3弾 『続・拝啓 つげ義春様』展 北井一夫: 1970年代初頭には、漫画家のつげ義春らとともに、下北半島(青森県)や国東半島(大分県)などの僻地への撮影旅行を繰り返し、アサヒグラフに発表。その後、単行本『つげ義春流れ雲旅』(朝日ソノラマ 1971年、共著 絵:つげ義春、文章:大崎紀夫、写真:北井一夫)として刊行。 赤塚不二夫: 上京後は東京で工員などをしながら漫画修業にはげみ、つげ義春の推薦で曙出版から上梓した貸本漫画『嵐をこえて』で1956年(昭和31年)にデビュー。 岡田晟: つげ義春に文学、クラシック音楽、コーヒーを教える。 白土三平: 1965年、白土は『ガロ』誌上で雑誌『迷路』の時代から高く評価していたつげ義春に連絡を乞う。 植芝理一: 作者曰く、つげ義春の『ねじ式』や逆柱いみりの作品に影響を受けているといい、作中にもそれを見ることが出来る。 |
つげ義春の情報まとめ

つげ 義春(つげ よしはる)さんの誕生日は1937年10月31日です。東京出身の漫画家のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/04 21:08更新
|
tsuge yoshiharu
つげ義春と同じ誕生日10月31日生まれ、同じ東京出身の人
TOPニュース
つげ義春と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター