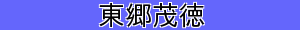東郷茂徳の情報(とうごうしげのり) 外交官 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

東郷 茂徳さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
東郷茂徳と関係のある人
中山仁: 聖断(2005年、TX) - 東郷茂徳 平沼騏一郎: しかし、東郷茂徳外相が受諾案において天皇の扱いを「国法上の地位を変更する要求を包含し居らざる了解の下受諾する」としていたことに異議を唱え、「国家統治の大権に変更を加うるが如き要求は之を包含し居らざる」に変更させ、連合国から当初の受諾案を拒絶される結果も招いた。 佐分利信: 日本の戦後 第1集「日本分割 知られざる占領計画」(1977年、NHK) - 東郷茂徳 汪兆銘: 9月1日、日本政府は閣議で「大東亜省」の設置を決定したが、東郷茂徳外相は二元外交の原因になりかねないとしてこれを批判し、結果として辞職した。 東條英機: 天皇への絶対忠信の持ち主の東條はそれまでの開戦派的姿勢を直ちに改め、外相に対米協調派の東郷茂徳を据え、一旦、帝国国策遂行要領を白紙に戻す。 佐藤尚武: 1942年(昭和17年)、東郷茂徳外務大臣に請われ、建川美次の後任として駐ソビエト連邦特命全権大使就任。 広田弘毅: 第二次世界大戦開戦後の1940年(昭和15年)10月の大政翼賛会発足後には後藤文夫、東郷茂徳、石黒忠篤、松本烝治とともに貴族院院内会派無所属倶楽部を組織した。 梅津美治郎: 東京裁判の法廷では、広田弘毅や重光葵等と同様に、証言台には立たず、沈黙を守り続けたが、東郷茂徳の証言内容に対しては、声を荒らげて反論する場面もあった。 東郷文彦: 東郷茂徳の娘だった東郷いせと結婚し婿入りして東郷姓になった。 吉田茂: 太平洋戦争開戦前には、ジョセフ・グルー米大使や東郷茂徳外相らと頻繁に面会して開戦阻止を目指すが実現せず、開戦後は牧野伸顕、元首相近衛ら重臣グループの連絡役として和平工作に従事(ヨハンセングループ)し、ミッドウェー海戦敗北を和平の好機とみて近衛とともにスイスに赴いて和平へ導く計画を立てるが、その後日本軍はアメリカ本土空襲やレンネル島沖海戦、オーストラリア空襲など一部勝利を重ねたため成功しなかった。 近衛文麿: 東郷茂徳は近衞の自殺を聞いて、次のようなメモを書き残している。 鈴木貫太郎: その結果、外務大臣・東郷茂徳の「この宣言は事実上有条件講和の申し出であるから、これを拒否すれば重大な結果を及ぼす恐れがある。 佐藤尚武: 7月に昭和天皇の意向で近衛文麿を和平交渉の特使としてモスクワに派遣することが決まると、7月12日に東郷茂徳外務大臣は佐藤に対して、特使派遣をモロトフに申し入れるよう訓令した。 武藤章: 1941年(昭和16年)11月1日の大本営政府連絡会議で東郷茂徳外相により突如提示された乙案に 鈴木貫太郎: 8月10日未明 から行われた天皇臨席での最高戦争指導会議(御前会議)では、ポツダム宣言受諾を巡り、東郷茂徳が主張し米内光政と平沼騏一郎が同意した1条件付受諾と、本土決戦を主張する阿南惟幾が参謀総長・梅津美治郎と軍令部総長・豊田副武の同意を受け主張した4条件付受諾との間で激論がたたかわされ、結論がでなかった。 東郷文彦: 1943年11月に東郷茂徳元外相の娘・いせと結婚。 東郷茂彦: 『祖父 東郷茂徳の生涯』(文藝春秋、1993年) 大西瀧治郎: 米内に激しく叱責された豊田と大西であったが、その後も終戦引き延ばし工作に奔走して、8月13日、御前会議出席前の外務大臣東郷茂徳を引き留めると、大西は「われわれは戦争に勝つための方策を陛下に奉呈して、終戦の御決定を考えなおしてくださるようにお願いしなければなりません」「われわれが特攻で2000万人の命を犠牲にする覚悟を決めるならば、勝利はわれわれのものとなるはずです」と主張したが、東郷は「われわれが真に勝利を得る、なんらかの希望があるのならば、誰もポツダム宣言を受諾することを瞬時も考えないであろう」と否定している。 小林桂樹: 命なりけり 悲劇の外相東郷茂徳(1994年、TBS) - 鈴木貫太郎 役 ※終戦記念ドラマ 新井量大: 「命なりけり・悲劇の外相東郷茂徳」(1994年8月15日) 迫水久常: 事前に平沼がポツダム宣言受諾に傾いているという情報を得ていた迫水は従来の6人の参加者から議長役で発言権のない鈴木総理を除いた5人の意見が受諾反対3(阿南陸相、梅津総長、豊田総長):受諾賛成2(東郷茂徳外相、米内光政海軍大臣)に分かれ、そこに受諾賛成の平沼の1票を加えて3:3の膠着状態に持ち込みその状況打開のために鈴木総理が昭和天皇に聖断を促すという筋書きを練り、御前会議の決定を枢密院に諮る手間と時間の省略を名目に平沼をメンバーに加えたのだ。 東郷和彦: 母方の祖父は第二次世界大戦終戦時に外務大臣を務めた元外交官の東郷茂徳。 倉成正: 東郷茂徳 笠信太郎: 和平工作時、スイスから和平締結を求める東郷茂徳外相宛て電報を緒方竹虎(当時内閣顧問)に送付(結果的には未達)したことで、緒方や近衛文麿など、政権中枢とのコネクションを有しているものと米国側に把握されていた。 賀屋興宣: 1941年(昭和16年)の太平洋戦争開戦時の東条内閣で再び大蔵大臣を務めて戦時経済を担当したが、東郷茂徳外務大臣と共に米英に対する開戦には終始反対だった。 宮口精二: 激動の昭和史 軍閥(1970年) - 東郷茂徳 役 原田清人: ドラマ特別企画 / 命なりけり・悲劇の外相東郷茂徳(1994年、TBS / 蟻プロダクション) - 近衛文麿 市毛良枝: 俳優座創立50周年記念「命なりけり 悲劇の外相東郷茂徳 戦争終結に全力を投じ、獄中に散った父」(1994年8月15日) 阿部牧郎: また、『危機の外相 東郷茂徳』、『英雄の魂 小説石原莞爾』、『豪胆の人 帝国陸軍参謀長・長勇伝』などの評伝小説も多い。 近衛文麿: これを受けて、外相・東郷茂徳は近衞に特使就任を依頼し、7月12日に正式に近衞は天皇から特使に任命された。 |
東郷茂徳の情報まとめ

東郷 茂徳(とうごう しげのり)さんの誕生日は1882年12月10日です。鹿児島出身の外交官のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2025/06/30 13:10更新
|
tougou shigenori
東郷茂徳と同じ誕生日12月10日生まれ、同じ鹿児島出身の人
TOPニュース
東郷茂徳と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター