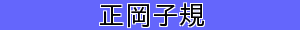正岡子規の情報(まさおかしき) 俳人(俳句) 芸能人・有名人Wiki検索[誕生日、年齢、出身地、星座]

正岡 子規さんについて調べます
|
■名前・氏名 |
正岡子規と関係のある人
真下五一: 『正岡子規』佼成出版社 1966 伊藤左千夫: 同年「日本」に掲載された正岡子規の『歌よみに与ふる書』を読んで感化され、1900年(明治33年)に子規庵を訪れて会話を交わしてからは三歳年下である子規の信奉者となり、毎月の歌会に参加して子規に師事するようになった。 夏目漱石: 赴任中は愚陀仏庵に下宿したが、52日間に渡って正岡子規も居候した時期があり、俳句結社「松風会」に参加し句会を開いた。 島木赤彦: 『アララギ』は1900年(明治33年)、正岡子規から始まった根岸短歌会が源である。 夏目漱石: 1月 - 正岡子規との親交が始まる。 斎藤志郎: 食いしん坊万歳!~正岡子規青春狂詩曲~(2017年、紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA) 小林一茶: 明治時代中期以降、正岡子規らに注目されるようになり、その後、自然主義文学の隆盛にともなって一茶の俳句は大きな注目を集めるようになり、松尾芭蕉、与謝蕪村と並ぶ江戸時代を代表する俳人としての評価が固まっていく。 歌原奈緒: 俳人正岡子規は遠縁である(子規の母方の祖母が歌原家の出身)。 伊藤左千夫: 短歌に関心をもったのは1893年頃で、正岡子規の『歌よみに与ふる書』に感動、1900年に門人となった。 長塚節: 正岡子規の『歌よみに与ふる書』に深い感銘を受け、1900年に入門。 原敬: 達は正岡子規の門人として抱琴の号を持ち、「ホトトギス」にも投稿する俳人でもあった。 島木赤彦: この時期の赤彦の短歌は正岡子規を中心とした根岸派同人としての作品であり、子規没後は、『馬酔木』の伊藤左千夫に師事し精一杯の力量を発揮している。 香川照之: NHKスペシャルドラマ『坂の上の雲』の出演に臨み、結核と脊椎カリエスに冒された正岡子規役を演じるため、食事制限やランニングなどで5か月間で15kg以上減量した。 坪内稔典: 大学時代はパチンコに勤しみ、その間に正岡子規などを読むような生活を送っていたが、学生結婚を機に本格的に子規研究を始めた。 佐山裕亮: 『KEIKI 〜夏目漱石推理帳〜』(2009年10月)- 正岡子規 保村真: 明治東亰恋伽(正岡子規) 石谷春貴: 声のプロフェッショナルが奏でる日本文学「吾輩は猫である-はじまりの漱石-」(2020年11月1日、紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYA) - 正岡子規、迷亭 役 河東碧梧桐: 少年の頃は正岡子規の友人で後に海軍中将となる秋山淳五郎(真之)を「淳さん」と敬愛していた。 加藤虎ノ介: 夏目漱石の妻(2016年9月24日、NHK) - 正岡子規 坪内稔典: 『正岡子規 俳句の出立』俳句研究社 1976年 坪内稔典: 『正岡子規 創造の共同性』リブロポート・シリーズ民間日本学者 1991年 夏目漱石: 1902年(明治35年)9月 - 正岡子規没。 粟津則雄: 『筆まかせ抄』(正岡子規、岩波文庫) 1985 福山潤: 火の鳥“道後温泉編”(正岡子規) 粟津則雄: 1982年:『正岡子規』により亀井勝一郎賞を受賞。 高橋是清: 共立学校の教え子には俳人の正岡子規やバルチック艦隊を撃滅した海軍中将・秋山真之がいる。 坪内稔典: 『正岡子規の<楽しむ力>』日本放送出版協会(生活人新書) 2009年 三浦光世: 正岡子規の影響により歌誌「アララギ」に入り、歌人として出発。 ジェームス三木: ミュージカル『正岡子規』(2010年、わらび座) おにぎり: 1898年(明治31年) - 正岡子規が俳句集『月見』を刊行。 |
正岡子規の情報まとめ

正岡 子規(まさおか しき)さんの誕生日は1867年10月14日です。愛媛出身の俳人(俳句)のようです。
wiki情報を探しましたが見つかりませんでした。
wikiの記事が見つからない理由同姓同名の芸能人・有名人などが複数いて本人記事にたどり着けない 名前が短すぎる、名称が複数ある、特殊記号が使われていることなどにより本人記事にたどり着けない 情報が少ない・認知度が低くwikiにまとめられていない 誹謗中傷による削除依頼・荒らしなどにより削除されている などが考えられます。 2026/02/05 12:38更新
|
masaoka shiki
正岡子規と同じ誕生日10月14日生まれ、同じ愛媛出身の人
TOPニュース
正岡子規と近い名前の人
注目の芸能人・有名人【ランキング】
話題のアホネイター